ニーチェの《生きる》からソクラテスのそれへ!?
ニーチェ論において次のような課題つきの回答をもらったところ その次にかかげるような応答をしました。
この問答そのものを主題として問いたいと思います。
無条件にご自由にご見解を述べておしえてください。
◆ 《或る回答》 ~~~~~~~~~~~~~
ニーチェの思想に対抗するなら
ソクラテスの思想になると思います。
「それはつまり、大切にしなければならないのは、ただ生きるということではなくて、
善く生きるということなのだというのだ。」
この「善く生きる」でしょう。
ソクラテスの自殺。
もしくは無理やり仏教の話題を出すなら
ブッダである、サーリプッタの自殺。
長生きしたゴータマ・シッダッタよりは
サーリプッタのほうが、生への執着を断っていると思います。
このヨーロッパとインドの自殺。
善く生きるなんて言ってソクラテスは自殺した。
さすがアイロニーの使い手のソクラテス。
結論が自殺なんですから。
ソクラテスの思想は難しいですね。
☆ 《応答》 ~~~~~~~~~~
おおきな主題を投げ入れてもらいました。
てめえで考えよというところも 結果的にあるようですが それはわたしはいぢわるですからハッキリと言っておきますが
◆ 善く生きるなんて言ってソクラテスは自殺した。
◆ ソクラテスの思想は難しいですね。
☆ というふうに触れておられるからには ご自身もこの主題を立てつつさらに問い求めるという姿勢でいられるものと思います。
そうですね。ボールはこちらのコートに入ったからには これはねじり鉢巻きで打ち返さねばなりませんね。
1.ニーチェにおいて《生きる》とは? ソクラテスの《善く生きる》とは?
● (渡邊二郎:補論 ニーチェ――生きる勇気を与える思想)~~~~
もうひとつ 『悦ばしき知識』におけるニーチェのもっと恐ろしい言葉を掲げよう。
*註 《もっと恐ろしい》:この議論は次の《恐ろしい言葉》の指摘のあとを承けている。
《小さな復讐は たいていの場合 まったく復讐しない
ことよりも なにかいっそう人間的なものである》
( Eine kleine Rache ist zumeist etwas Mensch-
licheres als gar keine Rache. )
(『ツァラトゥストラ』I 《まむしのかみ傷》)
《生きる( Leben )》とは 何かと言えば それは
《死のうとする何ものかをたえず自分から突き放すこと》
( fortwaehrend Etwas von sich abstossen, die sterben will )
である。したがって
《われわれの持つ 否われわれだけが持つばかりではない あらゆる弱化
するもの 老化するものに対して 残酷で仮借ない態度を取ること》
( grausam und unerbitterlich gegen Alles sein, was schwach
und alt an uns, und nicht nur an uns, wird )
である。それゆえ《生きる》とは
《死んでゆく者たち 哀れな者たち 年老いた者たちに対して 敬虔な念を
持たないこと》
( ohne Pietaet gegen Sterbende, Elende und Greise sein )
ではないのか それなのに 老いたモーセは 《汝 殺すなかれ!》と言ったが それは矛盾ではないのか と ここでニーチェは仮借なく鋭鋒を振りかざして しかも問題の矛盾点を指摘したまま ぷっつりと断想を打ち切ってしまうのである(『悦ばしき知識』26)。
(渡邊二郎編解説:『ニーチェ・セレクション』 2005 pp.302 )
~~~~~~~~~~~~~~~
論者の言おうとするところは ニーチェが恐ろしく過激な言い回しを用いているが 真意はそこにはない。です。
そう見ておいて たしかにニーチェも《生きる》ことについて考えを述べています。
回答者さんの主眼点は しかももしたとえその定義をふくむ議論を受け容れたとしても なおその上に問題は《善く生きる》という主題がわれわれ人間には持たれているのだ。にありましょうか?
◆ 「それはつまり、大切にしなければならないのは、ただ生きるということではなくて、
善く生きるということなのだというのだ。」
2. 《善く生きる》には 《自死》を避けることがむつかしいか?
しかも・しかも 《善く生きる》とき人は この人間の社会にあっては《自死》というかたちを取ることさえあるのではないか?
《アース役》を超えるか? の主題でもあるようです。
2-1. 幼い時からの親友でゴータマ・ブッダの同輩弟子であるマウドゥガリヤーヤナ(モッガラーナ)が死に臨むとき シャーリプトラ(サーリプッタ)は 《死のうとする何ものかをたえず自分から突き放すこと》をせずに 自死をえらんだのか?
それとも そのときには《死んでゆく者たち 哀れな者たち 年老いた者たちに対して 敬虔な念を持たないこと》を実行し その考えをみづからにもおよぼしたのか?
あるいは もうそのときには じゅうぶんこの世を見たのだ じゅうぶん過ぎるほどわれは生きたと捉えたということなのか?
2-2. マウドゥガリヤーヤナにしても かつて間違った考えを持った人たちにそのマチガイを指摘したことの恨みを買って とうとう攻撃を受けたとき それは 受けねばならないとさとって暴力に甘んじたというのは シャーリプトラと同じような心境だったのか?
2-3. それにしてもゴータマ氏は 自分の寿命のことについて話をしたとき弟子のアーナンダがそうではなくもっと説法をつづけてくださいと言うべきところを言わなかったそのことを うらみつつ 死地に就いた。寿命を延ばすことも出来たが アーナンダの振る舞い(無反応)があったから もう生き続けない・つまり自死をえらんだ。というのかどうか。の問題。
2-4. おそらくアブラハムが長子イサクをいけにえにささげるという考えを持ったとき 大錯乱に落ち入り迷いに迷った挙句に得た結論。《人は他人(ひと)をもおのれをもころさない》。理屈抜きと言うべきか。公理と言うべきか。これが 人間の自由だと言うべきか。
ちなみにモーセはこのアブラハムの心なる《非思考の庭(信仰)》に火花を散らしたヒラメキの中身を《なんぢ ころすなかれ》と言いかえたのである。倫理規範としたのだ。このオシエなる形態とシンジルかたちとは別である。
2-5. ソクラテスの場合は けっきょく自分の弟子にあたる人間ふたりがアテネの町に害を及ぼしてしまった。人びとはその教師ぶりをうたがってとがめた。ソクラテスは――先ほどのマウドゥガリヤーヤナの場合ではないでしょうが―― このような自分の仲間としての弟子たちにしろ一般の市民たちにしろその咎めを受け容れ死刑のさばきにも甘んじた。のではないか?
おそらく《善く生きる》にしろ《生きる》にしろ アテネの町の人びとにおいてさらにさらに熟慮を持ち得た〔のにそれを打ち切った〕のではないだろうか?
3.
● 《われわれの持つ 否われわれだけが持つばかりではない あらゆる弱化
するもの 老化するものに対して 残酷で仮借ない態度を取ること》
☆ これは 《あらゆる弱化するもの 老化するもの》というのは 《歳を取ることにおいていわゆる自然に反する考えや振る舞いをおこなうことによってシガラミを増し加えるかのごとく現われて来る老弱化のそのこと》であると採ればよいかも知れない。
つまり《者》つまりその老化する人間に対して《残酷で仮借ない態度を取る》のではなく そうではなく 要するに考えと行動について自然(ないし人間の自由)に反するようなマチガイに対して容赦なくこれを捨てるということ。そのマ(間)の違いをおのれの内面において捉えこれを自然本性への違反として(ないし人間の自由への違反として)みづから批判しこれを内的に棄てるということ。であればよいかも知れない。
《生きる》ないし《善く生きる》のささやかな議論でしたが 《2》は課題として述べて立ち止まり思惟をなお残しております。そのおあとがよろしいようで。
~~~~~~~~~~~~~~~








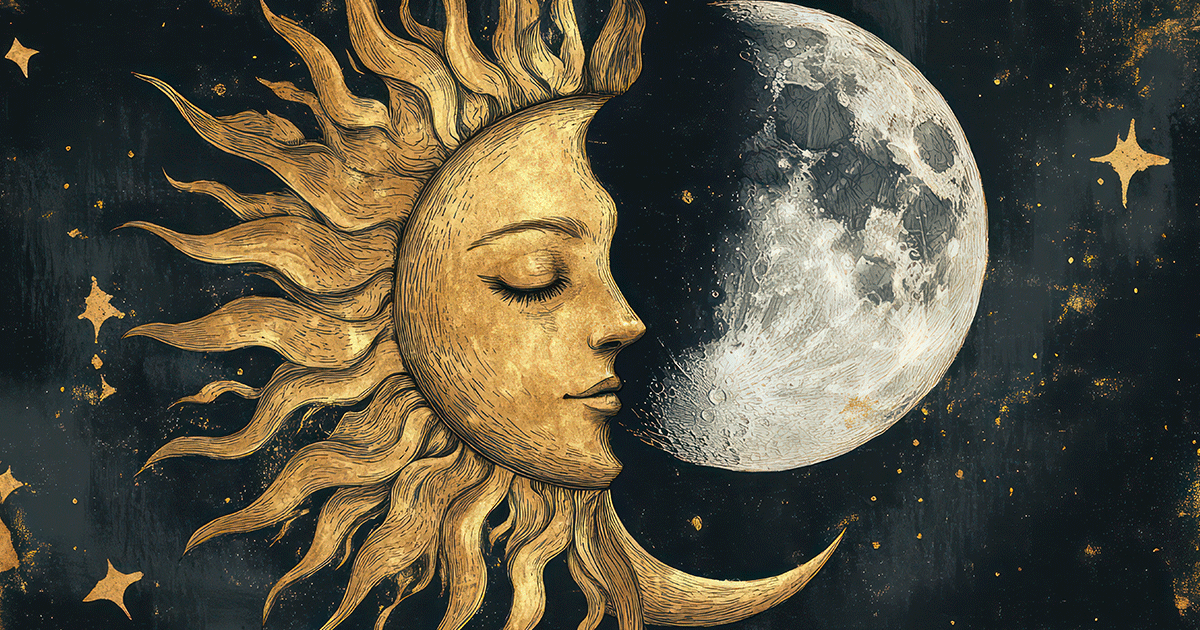












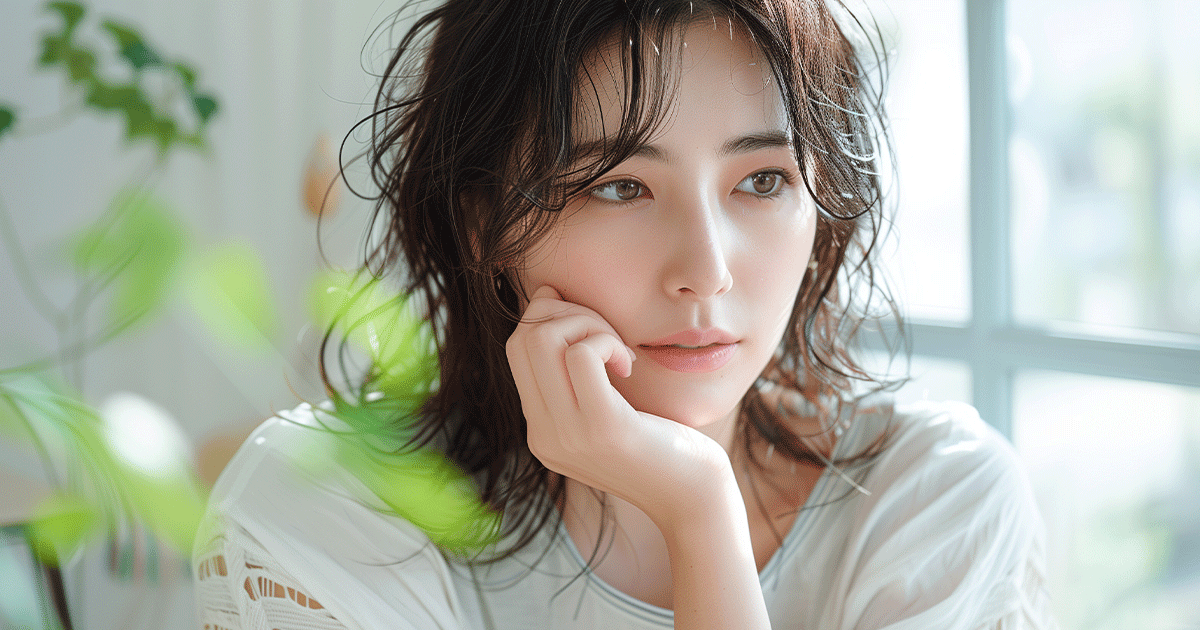

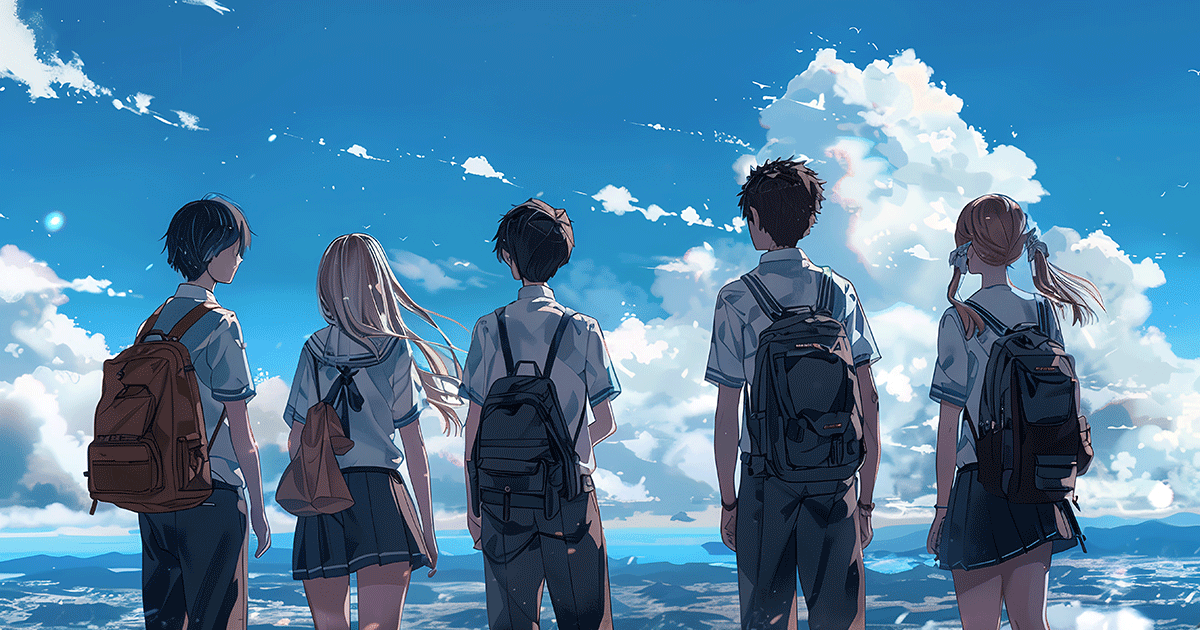








お礼
なるほど、神の死と結びつける解釈ですね? わざわざありがとうございました。