<<その通りだと思いますが、maggaさんの回答としてはちょっと物足りなかったです。>>
なにやら過分な評価をえているようですねw
物足りないとのことなので、思索に役立つかもしれないので、もう少し体についての考察を書いてみようと思います。
『病気』という視点から始めてみますね。
『病気』とは「肉体的・精神的働きに、不快・苦痛・悩みなどを感じて通常の生活を営みにくくするもの・そのような状態」のことと思います。
そのうちの『肉体の病気』についてみてみましょう。
肉体に生まれる「不快」や「苦痛」は「感覚」の中に分類できると思います。ではどのようなときに「不快」や「苦痛」の感覚を感じるのか考察してみます。
すると
「同じような感覚が続く」
「強い感覚」
になると「不快・苦痛」を感じるのではないかという結論に達しました。(もう一つ、経験や肉体の性質などによってでしょうか個人差のある「好き嫌い」原初的な快・不快があるように感じますが、この分類が肉体に当たるものか精神に当たるものか分別できるほどの観察能力を兼ね備えてないのでここでは無視しますね。)
「同じような感覚が続く」と「強い感覚」になるとも思います。
『止まる』状態でいると同じような感覚を得て強い感覚に感じ「不快・苦痛」が強くなると思います。
苦痛になると、動きますね。他の感覚に移しますね。するとさっきまで感じていた苦痛が減った分「楽になった」「楽を得た」と一般的には言うと思います。
しかし、その次ぎの感覚も感じ続けていると不快苦痛が強くなっていきますね。移った感覚が「楽」であるわけではないと思います。苦痛・不快の少なくなった分を「楽」と呼んでいるだけで、「苦痛・不快」から「苦痛・不快」への引越しで、感覚は「苦」であるといえると思います。
そして生まれた生命には老いて死ぬという性質も発見できると思います。
老いとは「肉体の生理的働き」が異常をきたし「動き」が弱り、「不快・苦痛」を感じ、「通常の生活を営みにくくする」ことであり、死はそれらのはてに営みを終えること。といえると思います。
ということは「老い」という性質自体が「病気」でしょうw
そして肉体は常に必要なものを取り入れ不必要なものを外に出していますね。食を必要として汚物を出し続けていますね。
汚物とは「身体に有害もしくは不必要なもの」です。
汚物は常に悪臭を放ちそれらを、洗ったり何なりしなければ悪臭はより強いものとなってしまい、仕舞には体の維持(老いにはかないませんが)も難しくなりますからますから、我々は体の垢・糞尿・などなど(全て汚物ですよね)を出して、流し落としてなんとか維持していることと思います。
●★●★●★●★●★●★●★●★●★
まとめると
『肉体とは、悪臭を放つ徐々に老いて死をむかえ壊れる定めの汚物の生産工場で、常に苦痛・不快を避けるために、「苦」から「苦」へと引っ越し「動く」もので、病気そのものである』
といえると思います。
そこから見出せる生命の希求は。
幸福でありたい
悩み苦しみは嫌だ避けたい
努力は実ってほしい
今なすべきことがすぐにひらめいてほしい
という希求かと思います。
生命のネットワークの中で、「心を堕落させず。向上すさせる。」には、この生命の希求を自分に・周囲に・全生命に認めること。自他の希求を守ること。肉体や感覚の事実を認めること。
が必須になると思います。
このような認めることの邪魔になる「自分勝手な価値判断・尺度」にどう対処するかだと思います。
「精神的な悩み苦痛」は、自他の希求を認めず、事実を受け入れないで、「自分勝手な価値判断・尺度」によって「『こうあるべき』理想の自分・世界(他者・物質もふくむ)」をつくりだして、現実との軋轢に「自分いじめ・他人いじめ」して苦しむものと思いますので…
「自分勝手な価値判断・尺度」は精神的苦しみの根っこかと思います。
パーリ語の仏典では「パパンチャ」と呼ばれるものと思います。スマナサーラ長老は「捏造・データの捏造」と呼んでいたと記憶しています。
●★●★●★●★●★●★●★●★●★
生命の希求を認め守るための心の育成である
「慈悲喜捨の修習」
生命のネットワーク内で自他を守る
「十善の実行」
十善を善、十悪を悪と知り、邪見を無くし正しい見解を得て、善の根である感情・悪の根である感情を知り、善根を育み・悪根を滅するため
「八正道の実践」
その道の多く修習することが期待できる支援策
「七支の前兆」
このような道が・修習が、精神的な悩み苦しみを滅したい人にとって、必要になると思います。
参考になれば幸いです。
幸福であれノシ






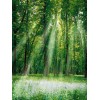































お礼
釈尊は人の楽しむ姿を見て、それさえも‘苦’であると見たようですね。 人間の、喜怒哀楽に安らぎの世界を見出せず、出世(世間から脱出)して、涅槃の心を求めました。 そして悟れたからこそ、楽しむ姿も、苦であると思えたのでしょう。 その苦に満ちた世間で生きなければならない、我々に、その苦を軽減するには、八正道の実践が有効であると、教えてくれました。 magga さんの今回の回答に接して、このようなことを思いだしました。 回答ありがとうございました。