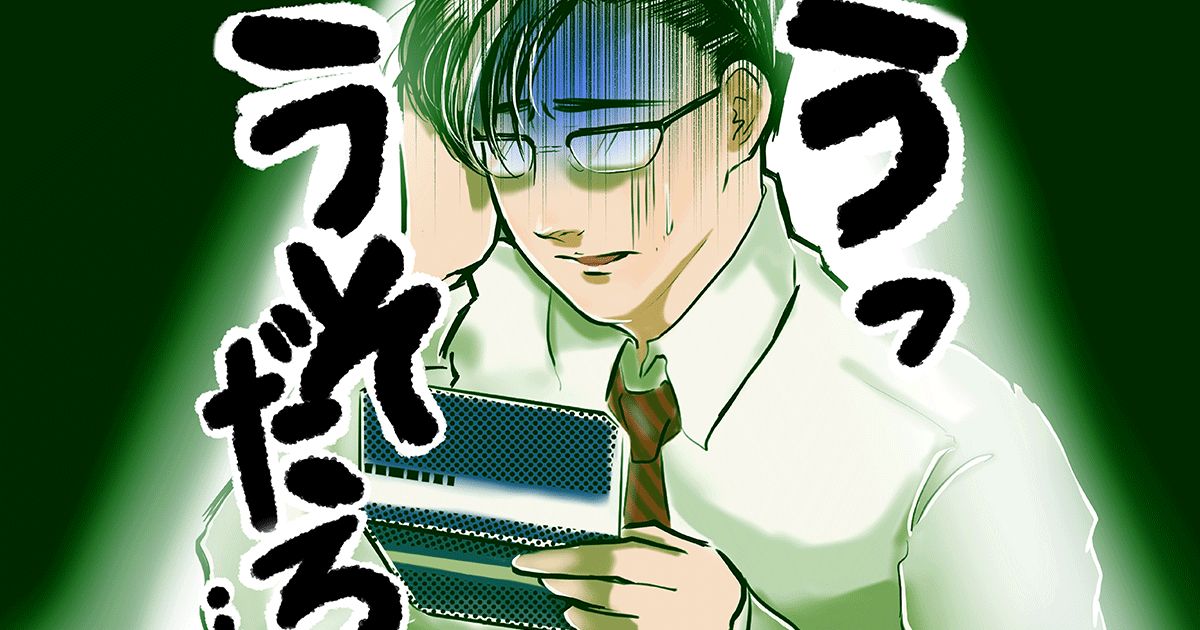いくら以上稼げば夫の扶養手当をもらうよりも得なのか
来月から正社員で月給16万円で働く予定です。
夫の扶養からは外れてしまいます。
夫の会社は、扶養手当が年間で約586,500円つくことになります。
夫の会社の規定で、妻の収入が100万以下でないと扶養手当はつかないので、
私が年間100万円以内で働くのと、年間約159万円で働くのは変わらないということになります。
上記のような理由で、月給16万なら年収192万円になるし、損はしないだろうと安易に考えていたのですが、
税金のことをしっかりと細かく計算に入れていませんでした…。
税金が引かれ、年間の手取り額が159万以下になってしまったら働き損ということになってしまいます。
実は新しく働く職場は小さい事業所なので、社会保険がつきません。(雇用保険のみあります)
働きながら国民健康保険や国民年金を自分で支払うことになります。
そうなると、税金でかなり持っていかれるのではないかと戦々恐々としております。
そこで、以下の点を質問させてください。
(1)月給16万円の場合、税金で持っていかれる金額はどのくらいなのでしょうか。
(※国民年金と国民健康保険を自分で支払った場合を想定して)
税金額は自治体によって違うとは聞きますが、
おおよその額や、給与に対して何割ほどが税金で引かれるのかだけでもわかると有難いです。
(2)上記の夫の家族手当を考慮すると、私は年間に総支給いくらで働けば損をしないのでしょうか。
ギリギリのラインは一体いくらなのか把握したいです。
税金等について全くの無知で大変お恥ずかしいのですが、
ご回答よろしくお願いします。