税理士試験挫折者ではありますが、零細企業の人事担当で、さらに会計事務所の在宅職員である者です。
税理士業界にいる間は、日商簿記1級<税理士試験簿記論かもしれません。
ただ、目指した経験のある者からすれば、日商簿記1級の範囲と難易度から考えると、
日商簿記1級<税理士試験簿記論+財務諸表論だと思います。
簿記論だけでは、比較が難しいと思います。せめて、試験範囲をある程度そろえてからでないと、比較できないように思うのです。
一般企業などに行けば、税理士試験の評価は難しいと思います。税理士試験5科目合格であれば、とても優秀だと思われると思いますが、科目合格を評価しきれないことでしょう。
わかりやすい日商簿記1級を評価すると思いますし、逆に科目合格するような人であれば、独立の考えをもって学習を続けるだろうというイメージが出てくることもあるでしょうね。
簿記論合格は税理士試験の一科目の合格にすぎませんが、日商簿記1級はそれだけで資格試験として評価されるものだと思います。
税理士試験は5科目合格して初めて正当な評価がなされるものにすぎません。
また、日商簿記1級は、税理士試験の受験資格にもなっていますし、大学などでも評価される資格としても有名です。そう考えると、日商簿記1級を取得されてからのほうが順当だと思いますね。
ちなみに、私は専門学校在学中に目指したのですが、受験資格として日商簿記1級や全経簿記上級を合格後に簿記論を受験しました。合格できる人のほうが少なかった記憶があります。もしも、2級から目指して挫折したら、ただの2級取得者です。商業高校の生徒と同じになってしまいます。
さらにいえることは、日商簿記1級の学習を省略した人で簿記論の合格者を私は知りませんし、日商簿記1級を挫折し、他の受験資格で税理士試験に挑んで簿記論に合格できた人も知りません。
飛び級のようなイメージで資格を目指される考えもあるのはわかりますが、一般的な難易度の段階を踏まないで合格したとしても、実務で役に立ちません。ただのテクニックでの合格にすぎなくなります。
知っている税理士の中には、ちょっと複雑な仕訳もできない、税法も基礎も分かっていないような税理士もいました。たぶん何かしらの近道をしたのでしょうね。近道が成功すれば社会的評価も得られますし、その後の学習さえできれば、困ることもないでしょう。しかし、税理士試験は長くかかる人が多いもので、さらに専念せずに合格できるほどの試験でもないことから、その間の社会からは置いて行かれることにもなります。テクニックのみで合格してしまうと、社会に出てから苦労します。段階を経て理解度を深めたうえでのテクニックでの合格者は、何年たっても理解度はさほど下がらないものでしょう。
私は日商簿記2級合格後、全経簿記上級に合格しました。
日商3級合格後、夜間の専門学校にて数か月学習して2級に合格しました。専門学校に入学して上級を目指しましたが半年で合格(入学前の2月ごろから学習し7月に合格)となりました。
下位級をしっかりとした合格をしていれば、2級が数か月、1級でも半年程度の試験でしょう。
社会的評価や保険という意味でも、段階を踏むことがよいことだと思いますし、簿記検定最上位級の合格と税理士試験の会計科目二つの合格で、ある意味会計のプロだと思います。




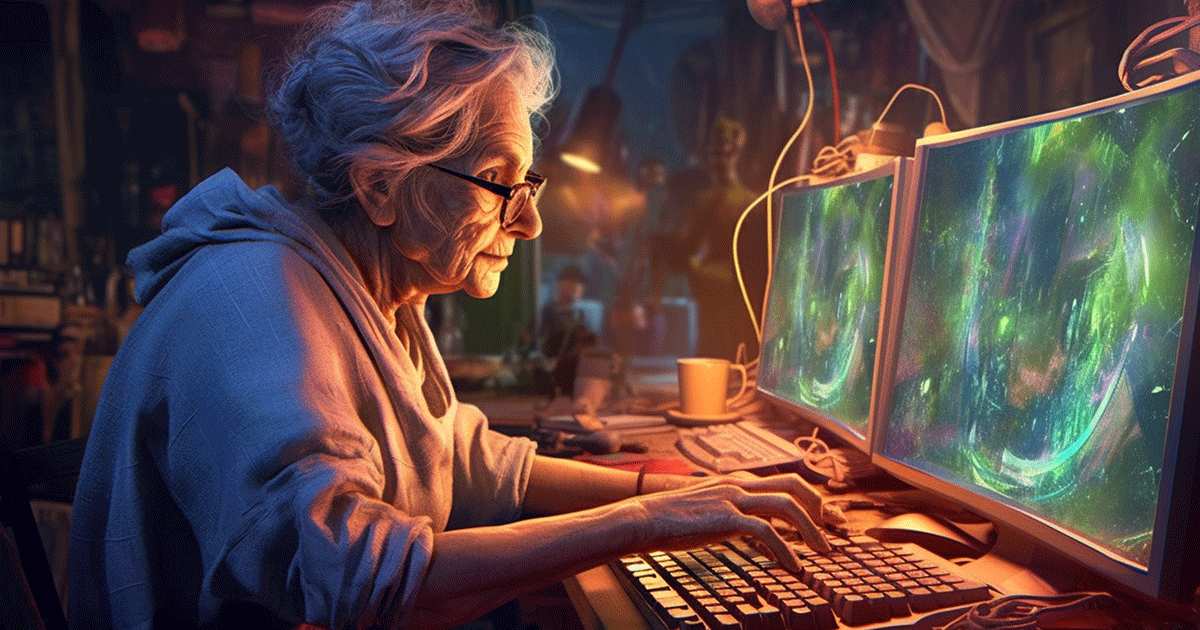

















お礼
回答ありがとうございます。 確かに簿記論は税理士になるための1科目で、 簿記1級と比べるには質の違うものだったかもしれません。 少し時間的な余裕があるため、 忙しくなったときのことを考えて、簿記論をやっておくのもいいかな、、と考えていました。 簿記のような話は私にとって、全くの専門外の内容です。(調べたところ税理士試験の受験資格はあったのですが、、) 税理士試験の受験資格に簿記1級があることを考えれば 簿記1級の内容をきちんと学ぶのが妥当かとも思いました。 すぐに受けることはないかもしれませんが、 簿記論を視野に入れつつ(その先も考えて) まずは1級を目指そうと思います。 ありがとうございました!