- 締切済み
軽減税率の種目の分類はなぜ細かいのか
消費税が10%になるに伴い、軽減税率が導入される。 しかし、なぜ8%と10%の区分けが複雑なんでしょうか。 なぜ、わざわざ複雑にしなければならないのでしょうか。 (お店で食べれば贅沢、持ち帰れば贅沢ではないというような説明ではなく) なにかの法律の縛りがあって細かくなってしまうのですか。 報道番組、ワイドショーを見ていてもそういう説明は聞いたことありません。 ネットでその辺のことを説明いているサイトはありますか。 ネットにないにしても、複雑にせざる得ない理由をご存知の方いらっしゃいますか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4
- NAYAMINAKUNARE
- ベストアンサー率14% (307/2063)
回答No.3
- NAYAMINAKUNARE
- ベストアンサー率14% (307/2063)
回答No.2
- okvaio
- ベストアンサー率26% (2018/7727)
回答No.1










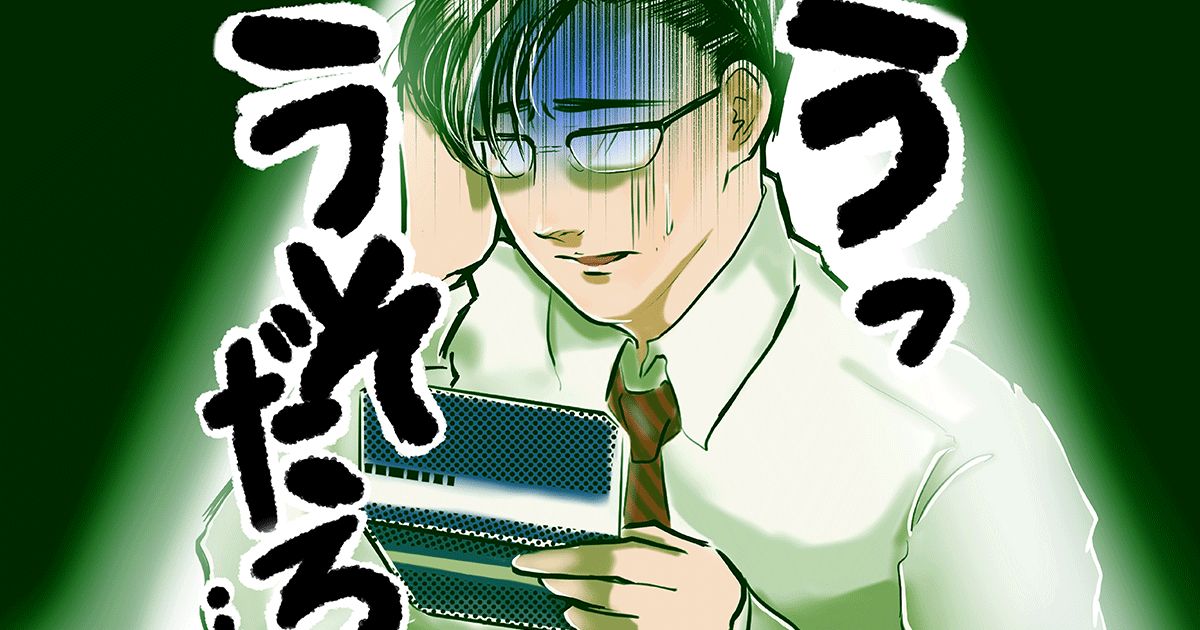















お礼
ありがとうございます。 複雑にしちゃったわけですね。 たった2%の増だけど、1000円のものを買うのに1100円払うのは気持ち的に痛いです。 イートイン、イートアウトで違うのはやり過ぎでしょ。公明党が言ったからって役人は考えろよといいたくなります。 よく行くある大手スーパーは専用カードを提示すると3%引いてくれます。(酒類は除く) ただでさえ他より安いのに3%引きは大きいです。まとめ買いは必ずこのスーパーを使います。 ガソリンを1リッター使う距離でちょっと遠いけど、それでもお得です。 10になったら必ずこのスーパーに行くしかないかな。