※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会計処理に関する素朴な疑問(減損、遡及適用など))
経理に関する疑問と誤解
このQ&Aのポイント
経理についての素朴な疑問や誤解を解決するために、遡及適用や減損会計、減価償却法などの重要な用語や概念について詳しく説明します。
遡及適用については、会計上の記録を修正するだけであり、会社への直接的な損害はないことを理解してください。
減損会計では、当期の損失が不安視される一方で、減価償却費の軽減なども考慮すべきです。また、減損の影響はキャッシュフローには直接的な影響を与えません。
経理になって10カ月ぐらいが経ちました。
現在は連結会計を担当しています。
なんとなく仕事の全体像や用語などは理解が出来るようになってきました。
一方でどうも経理の人達が「おおごとだ!」という感じで騒ぐことに対して、
どうしても「そんなにおおごとかな?」と思ってしまいます。
ことの重大さについて今一理解出来ていないというか?
たとえば下記のようなものです。
(1)遡及適用について遡及になったら大変だ!というトーンで良く打ち合わせなどするのですが、
単に財務諸表を作り直すのが大変だ!というだけの話でしょうか?
それとも会社として何か損害が出るのでしょうか?
(2)減損会計についても減損になったら大変だ!という感じなのですが、
確かに当期に大きな損失が出るのが嫌なのは理解できますが、
裏を返せば翌期以降の減価償却費の負担は減るわけですから、
トータルでも何も変わらないような気がするのですが。
別にキャッシュが出て行ってしまうわけでもないですし。
他に何か大きな弊害が出るのでしょうか?
(3)減価償却を定率法でやっているのは税法にひきづられているから、
IFRS導入になったら定額法でやらなければいけないから大変!
という話が出てるのですが、そもそも何故定率法でやると税務メリットが出るのですか?
また、税金計算は別途定率法でやってもらうとして会計上は定額法でやっては駄目なのでしょうか?
単に二つやるのは大変だから、どっちか1つということなら定率法でやっている、というだけの話でしょうか?
(4)耐用年数を長くしてしまったために、償却が終わる前に使えなくなってしまい、
固定資産除却損が出てしまうのは問題。みたいな話をセミナーで聞いたのですが、
これは何故ですか?ちゃんと償却してれば原価に費用が計上されるので、
営業利益にHITするけれど、
除却損にしてしまうと営業外費用だから営業利益にはその影響が出ないからずるい!
みたいなことでしょうか?
何だか経理慣れした方からすればバカみたいな質問&的外れな質問かと思いますが、
ご教示いただければ幸いです。








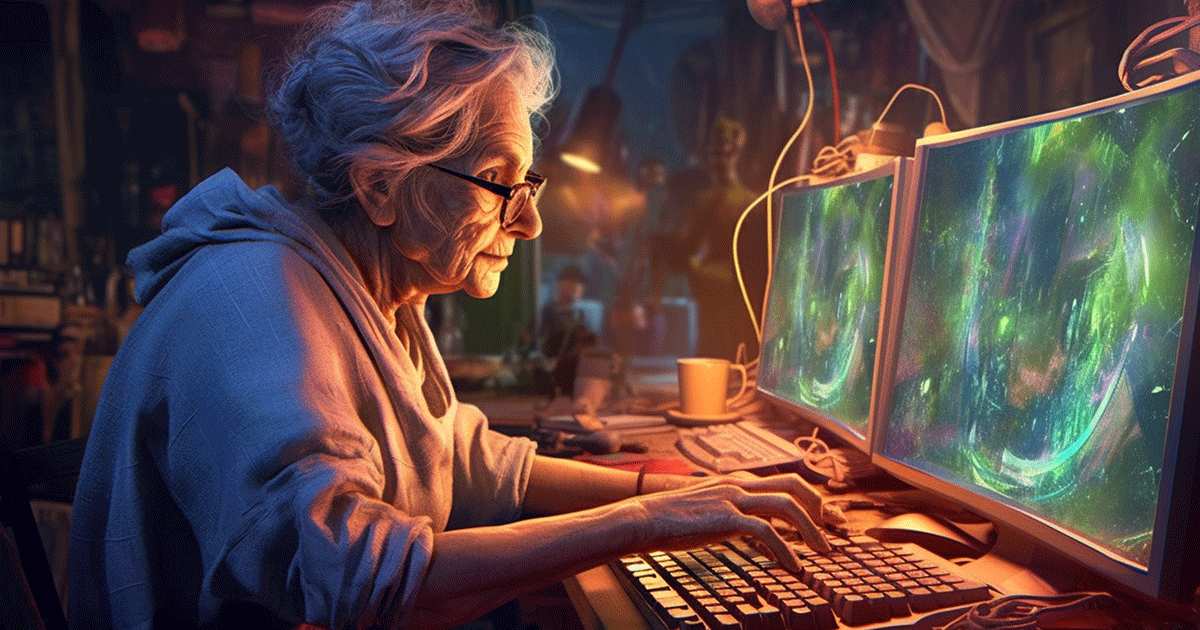
















お礼
ご回答ありがとうございました。 皆さん一生懸命にご回答いただいて大変感謝しています。 1番に解答いただけましたのでベストアンサーにさせていただきました。 (1)聞いてるだけで、ぞっとしてきました。とても大変なんですね。 (2)確かに減損処理をする=無駄な投資をしちゃいました、やらかしました、と株主に言っているようなものですよね。 (3)減損損失は一切税務上の損金算入が出来ないということ、知りませんでした。勉強になりました。 (4)なるほど。「特別損失」に落ちるのと「営業外費用」に落ちるのとではやはり違いますか?どうもその辺がぱっぱらぱーでして・・・極端にいえばキャッシュフロー上変わんないんだからいいんじゃない?という気がしてしまい。投資家は特損なら見逃してくれるけど、営業外に費用がはいっちゃうと、この会社ダメだね、って思っちゃうもんなんでしょうか?それってどうしてでしょうか?