- ベストアンサー
夏目漱石『こころ』はエゴイズムを描いたのか
似た質問がありますが、少し違う視点から質問しますので皆様、盆休みの間によろしくお願いします。 よく『こころ』はエゴイズムを描いた小説とされますが、何度読んでみてもどうもしっくり来ないのです。 先生のせいでKが自殺することになったのは確かです。けれど、先生はエゴをふりまくタイプではないし、もちろん自覚的なエゴイストではありません。 うまく表現できませんが、先生は何だか流されてそうなってしまった人といった印象を受けるので、普通イメージするような「エゴ」「エゴイズム」ということではくくれないような気がするのですが。 作者がエゴイズムを描いたとすると、どう解釈すればいいのでしょうか。また、他の解釈があれば教えて下さい。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- ghostbuster
- ベストアンサー率81% (422/520)
回答No.4
- neil_2112
- ベストアンサー率73% (196/268)
回答No.3
- neue_reich
- ベストアンサー率21% (138/647)
回答No.1







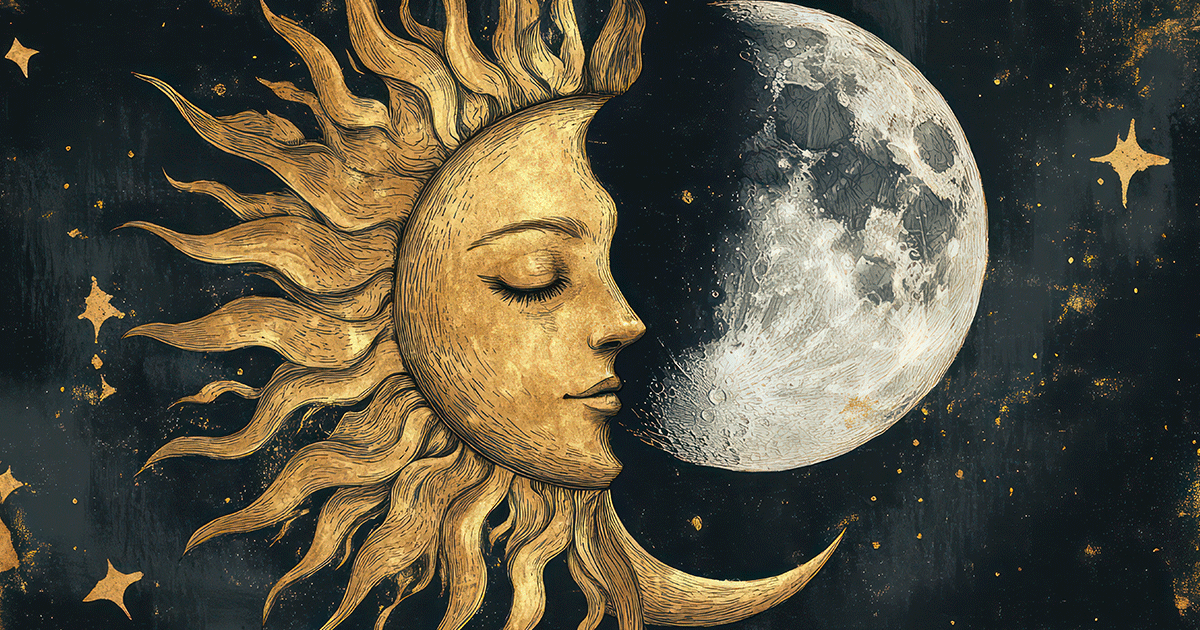









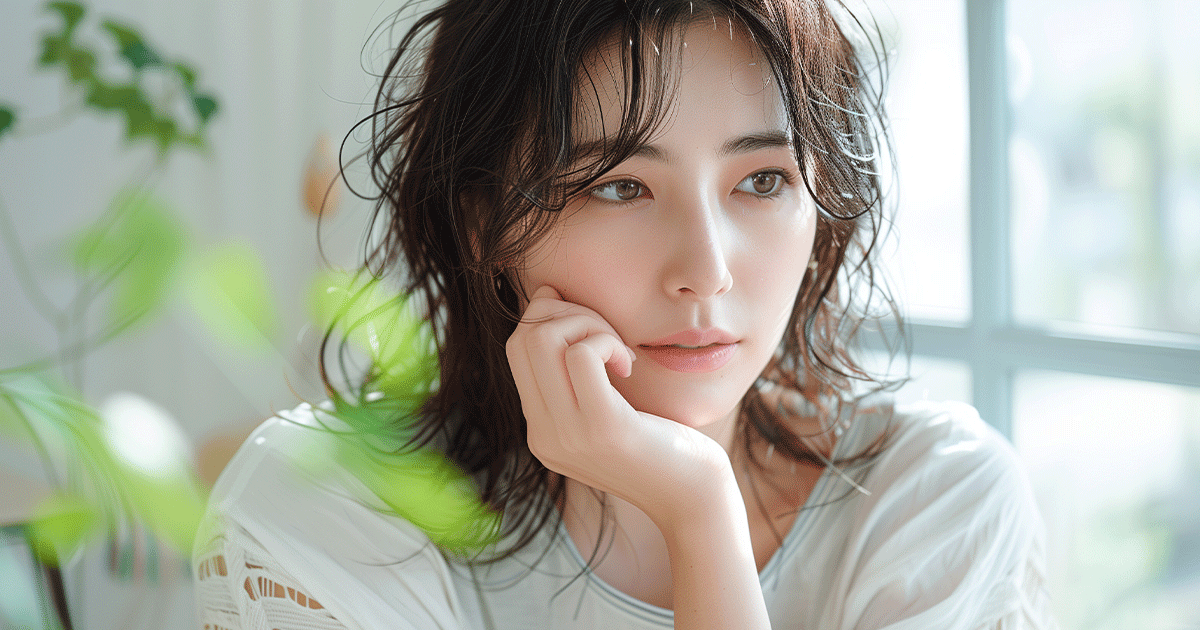

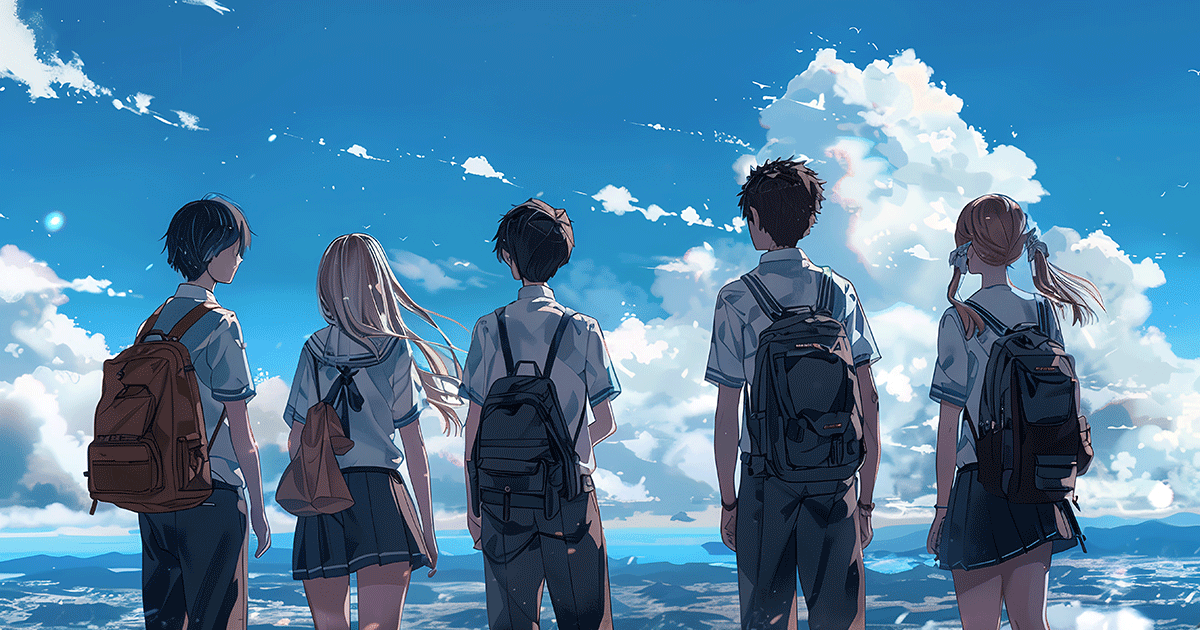








お礼
どうもご回答ありがとうございました。 幅広い視点のお答えでとても参考になりました。残念ながら『門』はまだ未読ですけどもご回答を参考に是非読んでみたいと思います。 >漱石は人間の心の奥深くに巣くうエゴイズムを暴こうとしました。それを白日の下に晒していけば、人々は反省し、自然で自由な世界へいくことができる。それが、後期の“則天去私”の心境とされています 教えて頂いたこのポイントを自分のこころにとどめておこうと思います。