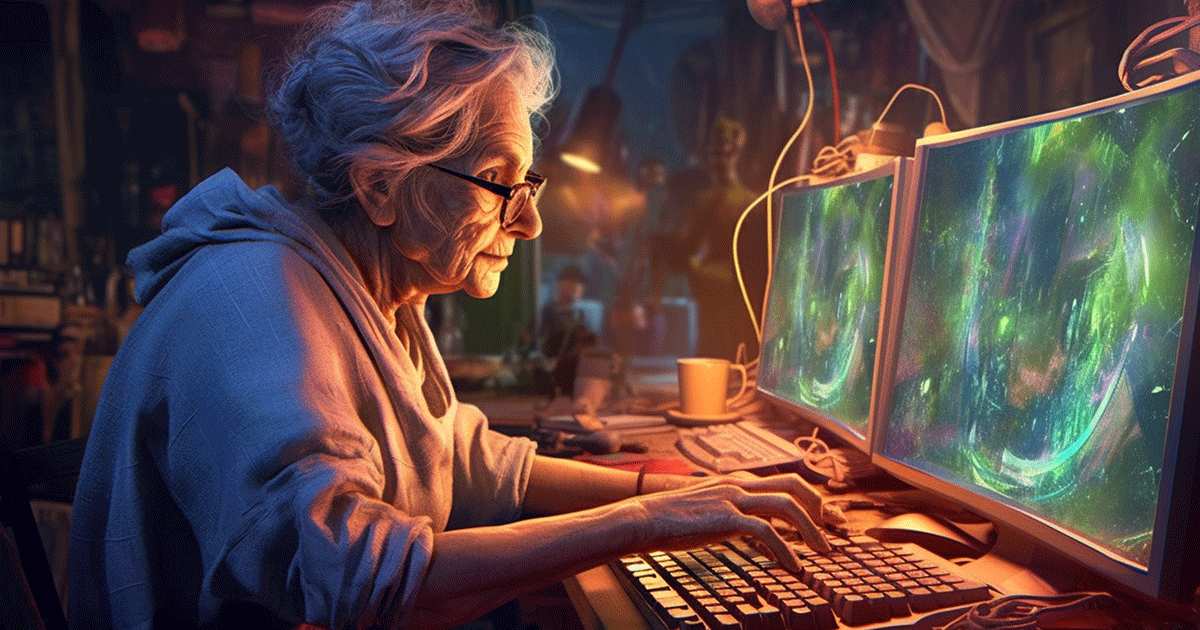破産等の法的手続きをおこなっている場合でない限り、督促は最終的に回収できるにせよ、できないにせよ行う必要があります。これは会計処理上、経費で落とす際に必要となるためです。ただこの場合の督促は法的措置というよりは、請求書を送付し、回収不能であることを立証するためのものということになります。
もちろん回収可能性があるのであれば督促から、法的手続きを含めて行うことは重要かと思いますが、もちろん手間・資金をかけて回収を模索しても結果回収できないことも充分に考えられるので、回収可能性と費用を天秤にかけて・・ということとなろうかと思います。
先方が破産・民事再生など行っている場合は担当する弁護士から通知が届くと思われるので、それにしたがって債権の届出を行うのみとなります。
会計処理で言えば、未回収の収入は未収として計上する必要があります。その上で今後の状況によって回収不能となった分を損失として処理していくこととなります。
税務上認められる処理を前提にしますと
・債務者が破産等の申し立てを行っている状態
→その時点で50%の貸倒引当金を計上、破産配当もしくは破産廃止の決定の時点で貸倒損失として処理
・破産等の申し立てを行っておらず、連絡不能等の場合
→最終取引から1年経過時点で、1円を残して貸倒損失として計上。この場合、請求書等を送付し戻ってきてしまうなど、回収不能であることを証明する必要があります。