「2007年版の建築物・・・基準書」に記載のある耐震壁に関するこの規定は,開口を含む耐力壁全体の耐力は,開口の形状及び位置によって低減する必要があるというものです。ここで,壁筋を切断していない,且つ,十分に補強された,本体耐力壁の耐力に影響を与えない程度の小開口は,耐力壁の耐力低減の必要はない事を規定しています。「開口と見做さない・・・」ではなく,「開口として十分な補強がされていれば・・・」という条件が与えられています。
よって,小開口といえども,基本的には,RC規準及び配筋指針による開口補強が必要です。耐力壁の小開口の補強は,配筋指針に記載されていませんが,スラブの単独小開口及び連続している場合の規定がありますので,参考になると思います。ただし,配筋指針によって開口補強を配筋すると,相当な間隔が必要となる場合があります。例えば,開口補強筋の定着を35dとすれば,D10であっても,L=70×2+35d=490(mm)程度必要となります。
また,規準はありませんが,経験的に,小開口と近接した窓等の大開口を包絡線等を用いて一体として本体耐力壁の検討を行い,開口全体としての開口補強設計が行われているとすれば,小開口と窓等の間隔は,詳細な検討を行わなくても,設備貫通孔と同等と扱ってもかまわないと思います。
なお,ここでは「・・基準書」による判断についてのみ記載しました。開口を有する耐震壁は,腰壁,たれ壁,袖壁のモデル化等に絡んで,難しい問題を含んでいるので,単純な回答は難しいです。「RC規準」或いは「2007年版・・・解説書による判断」で割り切るのが最も簡単です。





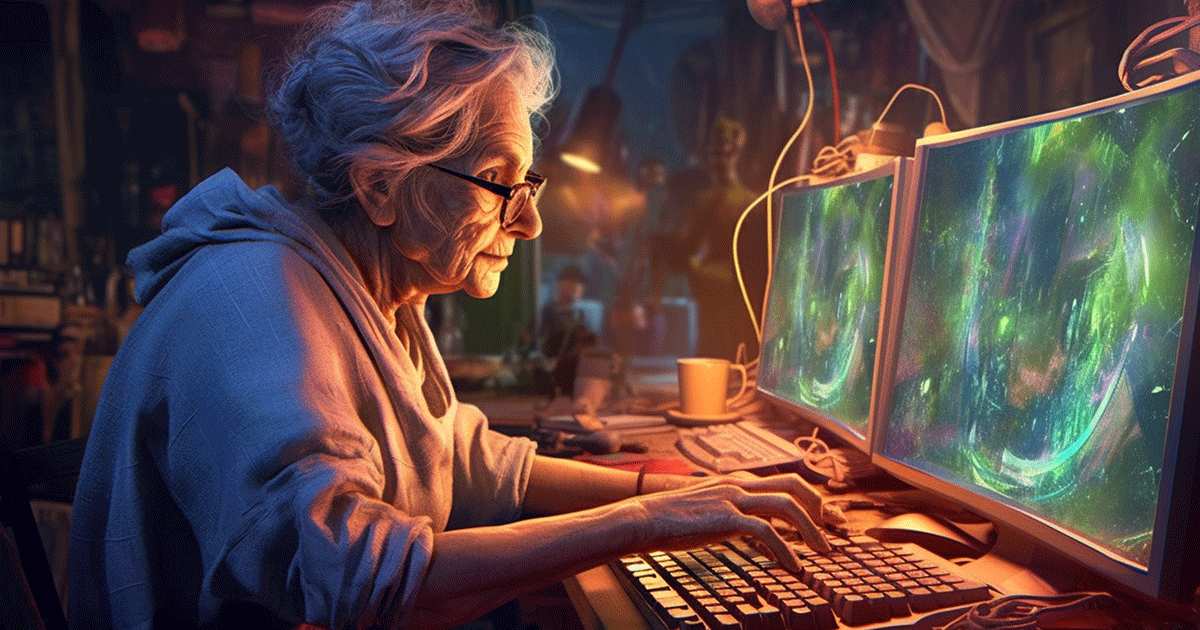






















お礼
解答ありがとうございます。 十分な補強というのが判断が難しいですね。 配筋指針に従うと少し過剰過ぎる気がしますが・・・ 床開口と同じで壁筋を切断せずにおさまるならそれでよしとすると言うことで良いのでしょうか? 窓との開口と包絡させて設計が成り立つというのが安全側で理想だと思いますが、 万一窓開口がぎりぎりの設計だった時急に配管を通すなんてことになった場合、どうするのだろうとちょっと疑問に思ったので質問してみました。 あとは設計者の判断ということですね。