- ベストアンサー
消費税の端数の差額
建設業の事務をしています。 材料を仕入れた場合、注文したすべてのものの合計に税金をかけるのではなく、個々に税金を計算してあると差額が出るので、会計ソフトに手作業で税金を入力して集計したのですが、決算時に税理士さんにそのことを伝えたのですが、面倒らしく「合計したのでやっとくから」といわれました。少しならいいですが、沢山あると結構な金額を損している気がするのですが・・・。 どうしたらいいのでしょうか?
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (7)
- lemon_heart
- ベストアンサー率69% (9/13)
回答No.8
- lemon_heart
- ベストアンサー率69% (9/13)
回答No.6
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.5
- seaway
- ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.4
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3
- ngsvx
- ベストアンサー率49% (157/315)
回答No.2

noname#6341
回答No.1






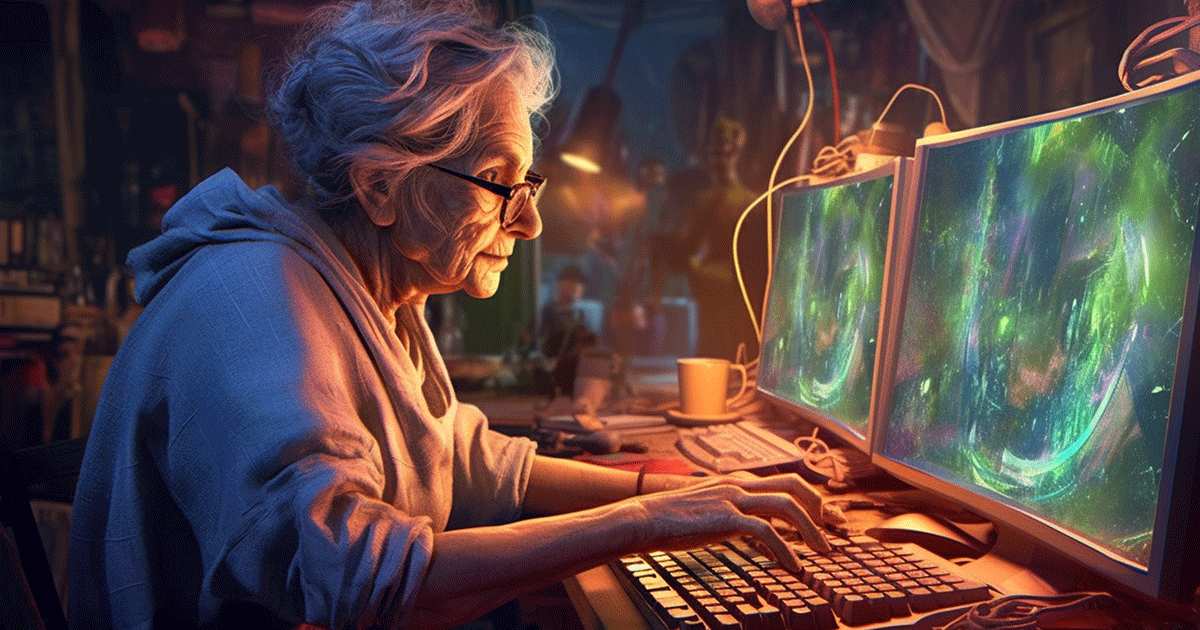



















お礼
何度も回答ありがとうございます。 詳しく説明していただき感謝しています。