- ベストアンサー
自分の身を守るのはいけないことでしょうか
私が、私や私が所属する集合体を守ろうとする、あるいは利益をもたらそうとすることは当然のことでしょう。 ならば、、 彼が、彼や彼の所属する集合体を守ろうとする、あるいは利益をもたらそうとすることも当然のことのはずです。 しかし、この当然のことをしているだけのはずが、互いに排他の関係に陥ることがしばしばあります。 互いの利益がぶつかり合う関係というのは日常茶飯事的に立ち上がってくる問題です。 「排他性」は相手を悩ませるともに、自分自身の精神性にも好ましくない影響を与えます。 しかし、生きようとすると排他の関係にならざるを得ない。 「いや、案外みんな仲良くやってるんじゃないの」という見解もあるかと思いますが、 それは通常の場合、少数者、あるいは弱者に対する排他の上に成立している仲良さであるように私は感じます。 ここで言う「私」や「彼」は個人はもちろんですが、家族、学校、地域、会社、国家、宗教などの代名詞でもあります。 排他性は、イジメ、虐待、商品偽装、収賄、殺人、戦争、テロなどなど、あらゆる場面で発揮されています。 一見なにごともなく過ごしているように見える私たちも実は、この排他性によって互いに影響を受け合い、 また、それが私たちの精神形成にも影響を与えているはずです。 どう考えても「良い影響」であるとは思われません。 「生きようとすると排他の関係になる」から「排他を発揮しなくとも生きることができる」へと転換するためには、どのような哲学が必要と思われますか?
- みんなの回答 (81)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (80)

noname#91067
回答No.61
- pokoperopo
- ベストアンサー率28% (104/359)
回答No.60
- cyototu
- ベストアンサー率28% (393/1368)
回答No.59
- cyototu
- ベストアンサー率28% (393/1368)
回答No.58

noname#82286
回答No.57

noname#155689
回答No.56
- pokoperopo
- ベストアンサー率28% (104/359)
回答No.55

noname#155689
回答No.54
- pokoperopo
- ベストアンサー率28% (104/359)
回答No.53

noname#91067
回答No.52

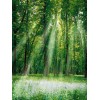






























お礼
(つづき) >信じることーあるいは信念と、勇気をうまく結びつけることで、無理なく心の偏りから抜け出るイメージをーー現在鋭意努力中、ということで。 :この場合の信念に対する変化も怖れないようになりたいものですが、難しいかもしれませんね。 信念は自信にも結びつくわけですが、自信を持ちながらも変革を怖れない、ということになるでしょうか。 信念によって何を求めているのか、ということも検証課題として浮かび上がってくるような気もしてきました。 >実際行動を起こす、というより、まず現実認識ー自分の本音を自覚することにしてます。 気取って言えば、敵を知り、己を知れば百戦危うからず、みたいなことで。自分と戦うくらいばからしいこともないので。 :このへんはクールですね。 行動によってしか得られない反応なり真実もあるかもしれませんけどね。 >人生の一定期間一週間とかを目的のために使うか、人生全体か、過去も未来も全部使いたいか、などのスパンによって、こちら側の人格が変化し、発想、感性が変化する、と考えてます。 無意識レベルの集中が強い人、と言ってます。 :方法論だったわけですか。 非常にわかりやすくて、有効な考え方ですね。 大変参考になりました。 その【目的】が何か、ということになるのでしょうね。 >その集中は、意志による物ではなく、自分と自分を取り巻く環境の組み合わせによって発生する、無意識レベルの人生に対するーー主観的な時間と空間を使用することに対してのー高い自然な集中状態、と考えてます。 :う~む・・・(-_-;)。 なるほど。 瞑想か何かされていらっしゃるような気もしてきました。 >こんなんでいいでしょうか? かみ砕けてます? :おかげさまで、おっしゃることの意図が一応理解できたように思います。 懇切丁寧に解説していただきありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 >排他的かどうかについては、それらの概念に対して自覚があるかどうか、あるいは無意識によりどころにしてるかどうか? が、本質的な違いじゃないか、と考えてます。 自覚的であるなら、それによりどころを求めてるのでなく、精神的な自律と主体性がともない、いろんな概念は、社会がうまく回るために必要な小道具、という位置づけになります(理想論としてです) :なるほど。 「>無意識によりどころにしてるかどうか?」 ここが分かれ目ですか。 なかなかしっくりとくるご見解です。 依存しているという事実に気付いているかどうか、ということですね。 気付いていれば、全面的依存に流れて自己を見失ったり、依存対象を失うまいとして無闇に排他に走る可能性も少なくなる。 このように解釈しました。 少し違うのかな・・・。 具体的手法としては、 >勇気を出す、主体性を発揮する、というのは、習慣づけ、という方向しか浮かばないですが。 癖です。 :たしかに習慣として身につくことは重要でしょうね。 習慣づけのためのモチベーションがネックになってきます。 >固定観念に寄っかかって手抜きしていた現実をちょっとずつかみ砕いていく、 :これもうまい表現ですね。 寄っかかることの不都合に対する気付きや、噛み砕いていくことによって新たな地平が見えてくるのだ、と確信させてくれるような契機なり、言辞が求められるようです。 >それは、大きく言うと変化を恐れない、みたいなことです。 :大いに同感です。