周囲の土地の状況によって違います。
東京の都心などは「土地の高度利用地域」という指定になっています。建築技術は年々進歩しているので「何階建てまで」という規制はしにくいからです。
かといって、どんなに高くてもよい、というのも問題です。
日本の建物の規制は「建蔽率・容積率」で規制されています。建蔽率は建物を建てようとする土地の広さの何割まで建てていいか(100%なら全部・50%なら残り半分は庭などで地面を残す)と、土地の広さの何%まで立ててよいかの容積率(100%なら地面分全部、50%なら半分)で決めれています。
ですから建蔽率100%容積率100%なら、土地いっぱい使った平屋が作れます。建蔽率50%容積率100%なら土地は半分しか使えないけど面積は100%なので、2階建てにすれば地面は半分しか使わずに100%の面積の家を建てることができます。
これが駅前などになると建蔽率90%容積率450%などになり、事実上5階建てまでは建てられる、ということになります。
さらにこれに商業地なのか、住宅地なのかなどで建てられる階数などに規制があります。
で、高層ビルの建っている地域は容積率がとても大きいということになります。サンシャイン60などは容積率が何千倍もあるわけです。ではこの容積率をどこからもってきているか、ということになります。
答えを言うと、周辺の容積率を満たしていないビルの上部空間をもらって容積率をかさ上げしている、ということになります。
最近東京駅周辺で高層ビルの立替が進んでいるのは、赤レンガの東京駅の上部空間の容積率をもらって周辺に建てているからです。
これを特例容積率適用地区というのですが、高層ビルの立替と赤レンガ駅舎の復元が同時に進んでいるのは、東京駅は駅舎の上部空間を売ったお金で復元工事を行い、周辺のビルは買った容積率で建物を建て替えているからです。
六本木ヒルズもあべのハルカスも同じように特例容積率で建てています。
また、これとは別に日本では地震対策が必要になります。私はシンガポールのサンズが建設途中のときに見に行ってきましたが、日本ではありえないほど華奢な鉄骨を使っていました。単に自重を支えるだけなら、それほどのものではなくていいようです。
しかし日本では、耐震建築にお金が非常にかかります。たとえば世界一高い建物であるブルジュハリ
ファの総建築費は1400億円ぐらいと言われています。日本の六本木ヒルズは2000億円ぐらいです。
もちろん人件費や土地代も違いますが、高さ238mの六本木ヒルズとその3倍近い600mの建物を比べたときに世界一高いビルの建築費用のほうが安いのはやはり、耐震構造そのものにけっこうなお金がかかっているからでしょう。
日本でも600mクラスの高層ビルをつくる技術はあるといわれます。再開発すれば建てる場所も確保できるでしょう。でも採算にあう建物としたら、せいぜい500mクラスまでがいいところなのではないでしょうか。
またアメリカでも新しいWTCビルが500mぐらい、他のビルも500m届かないぐらい、階数にして100階程度ビルがほとんどです。なかなかこれ以上のビルが建たないのは採算性などの問題も大きいのだと思います。
高層ビルは上下の移動にエレベーターを使わざるをえないため、高くなればなるほど、利用が混んでしまうという欠点もあります。
作るつもりなら1000m級の計画がありますし、技術的にも日本で可能だそうです。でも採算性などいろいろな問題で、やはり600mクラスまでが今のところの限界ではないでしょうか。日本なら250mを超えるのは大変だと思います。








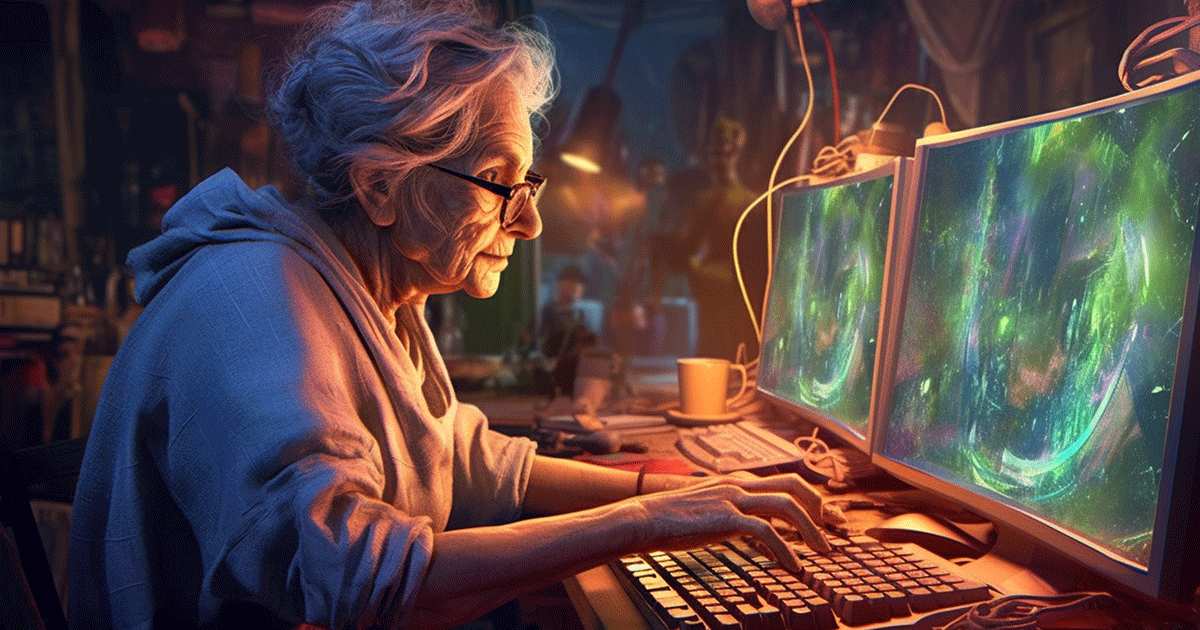



![その他([技術者向] コンピューター) イメージ](https://gazo.okwave.jp/okwave/spn/images/related_qa/c205_3_thumbnail_img_sm.png)























お礼
ありがとうございました。 参考にさせて戴きます。