契約は、口頭では不確実であるため、文書を交わします。
契約書・領収書を交わす際には、その取引の裏に経済的
利益があるだろう。そこにそれ相応の担税力(税金を納
める能力)を求めています。
社会的にも、文書を交わさないわけにはいかないし、
取引をしている以上利益もでているのだから、一部を
税として課せられるのも仕方ないといったところでしょ
うか。
消費税は、財・サービスの消費に目をつけた税ですが、
印紙税は、文書で交わす取引の裏にある利益に目をつけ
た流通税です。
世界では、ヨーロッパで17世紀からできた税で、
日本では、明治に成立した税です。
成立当初、印紙を貼っていないと裁判で証拠として採用
しない、貼付していない者を通報すると報酬がもらえた
等現在よりも印紙税の役割は大きかったようです。
(現在では、質問に書かれているように、印紙を貼って
いないからといって文書の効力を否定するものではあり
ません)
質問者さんが書かれているように消費税や、その他様々
な税の整備がされた現在では、確かに印紙税の根拠は薄
くなってきていると思います。歴史的な慣習の部分もあ
るのでしょう。
また、インターネット取引の場合、文書を残さないため
画面上で決済をしている限りでは印紙を貼る必要があり
ません。このような取引が増えると公平性を欠いてしま
うため、将来的には見直す必要がでてくる税なんだろ
うなと個人的には思います。
長くなりましたが、こんなとこでしょうか。













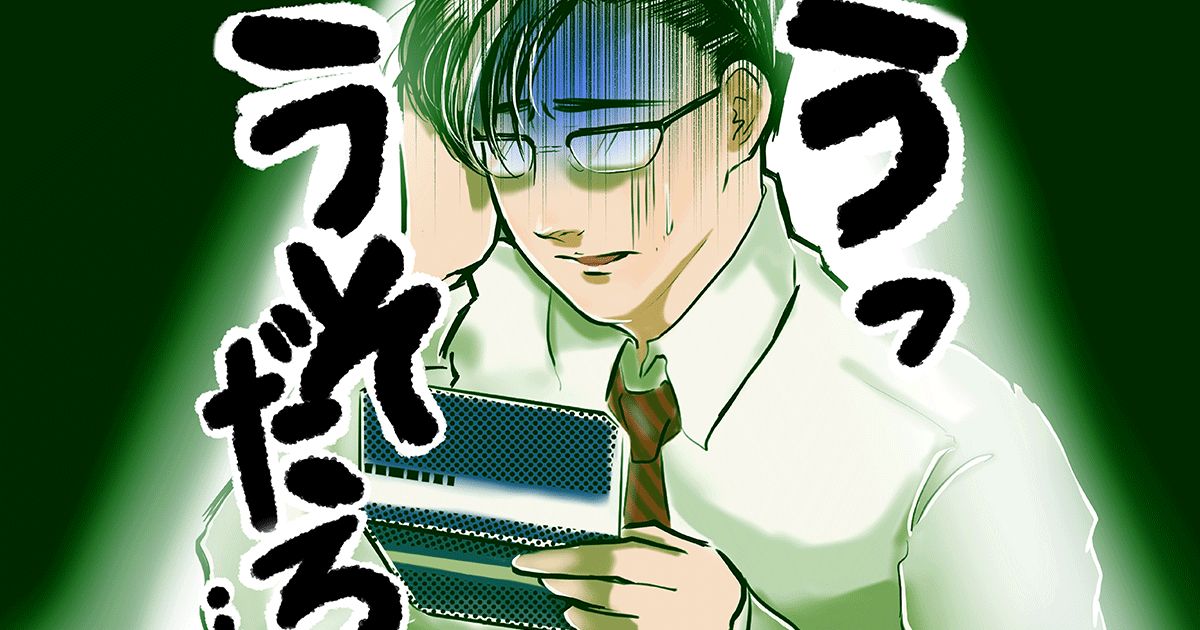
















お礼
回答ありがとうございます。なるほど。確かにインターネット取引では印紙が必要ないですね。経済発展に伴って目を付けられた (^^; 税で、さらなる社会変化に伴ってなくなっていくか、逆に取引の大半がネットになれば、ネット印紙税となってしぶとく生き残っていくかも・・・なんて思ってしまいました。