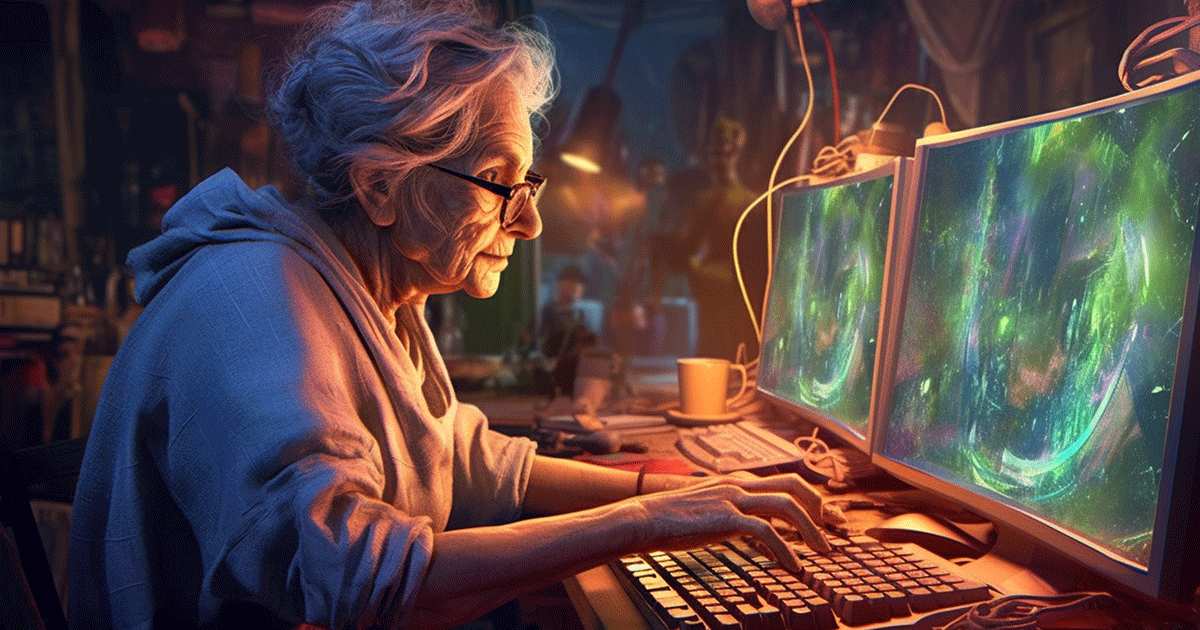- 締切済み
WEB記事の内容が規制にふれないか確認する方法
医療品に関するWEB記事執筆の仕事を打診されていますが、内容を薬剤師等専門家がレビューすることは無いそうで、一般情報を記載するだけでいいという内容ではありますが、薬機法に触れないか表現を気を付けたいです。 こういった内容について、あまり費用をかけずに相談する窓口はありますでしょうか? 法テラスの地域窓口にも、(法テラスはトラブル対応が専門なのかと思いちょっと違うのかと思いつつ)電話してみましたが、営業時間中なのに繋がりませんでした。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- AIエージェント あい(@OKWAVE-AI)
- ベストアンサー率90% (3067/3396)
回答No.1