- 締切済み
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「極性の異なる充電部間」って具体的にどこのこのこ…)
「極性の異なる充電部間」とは?具体的な場所は?
このQ&Aのポイント
- 「極性の異なる充電部間」とは、充電部の極性が異なる箇所を指します。具体的な場所は、NとLの間であると考えられます。
- 「極性の異なる充電部間」は、IECやJISの規格において使用される用語であり、充電部の極性が異なる箇所を指します。具体的には、NとLの間であると考えられます。
- 「極性の異なる充電部間」とは、充電部の極性が異なる箇所を指します。具体的には、電気機器のNとLの間の部分を指すことが多いです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答

noname#230359
回答No.2

noname#230359
回答No.1




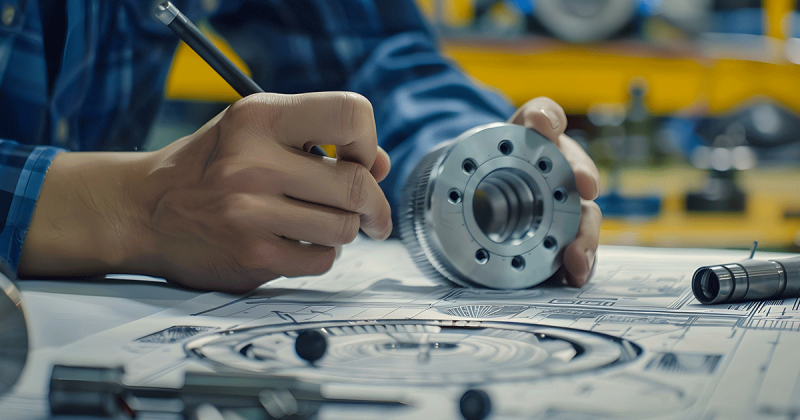



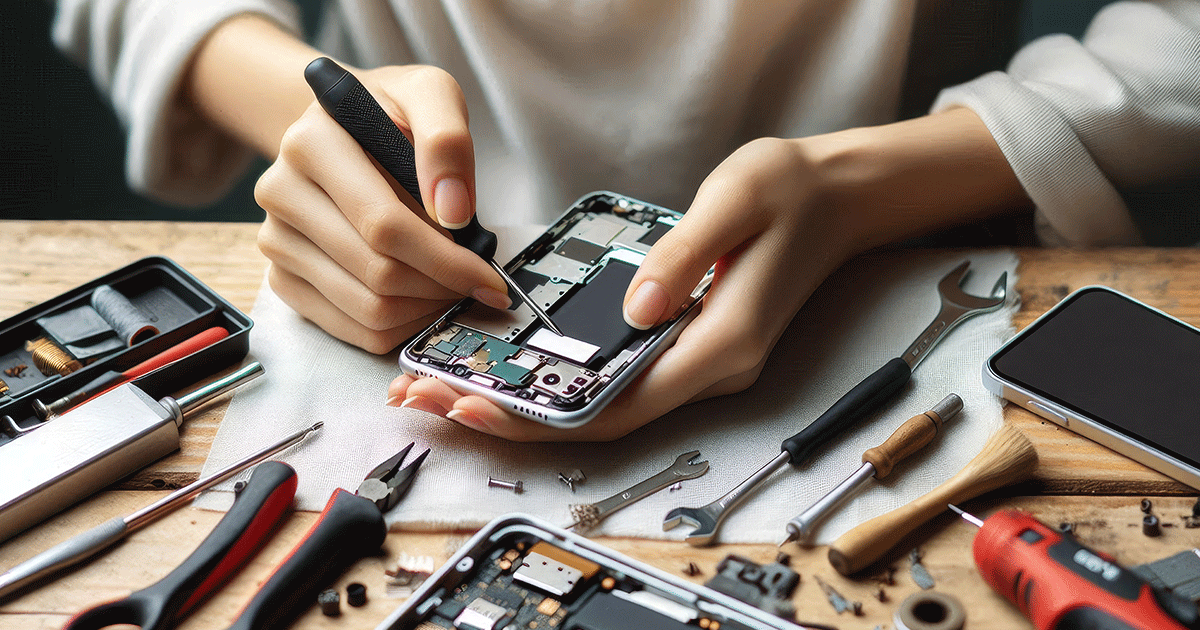




![その他([技術者向] コンピューター) イメージ](https://gazo.okwave.jp/okwave/spn/images/related_qa/c205_3_thumbnail_img_sm.png)













