- 締切済み
電磁気学と力学(とくに流体)の相違点について
電磁気学と力学(流体含む)についてお尋ねします。 両者には原理的な部分で大変類似性があると思います。実際の現場は大変なちがいになると思いますが。原理の方ですが、相違点があるとしたらどのようなところでしょうか。両者に読み替えができるということですが。 電流 ⇔ 流量 電圧 ⇔ 圧力 など。 私のこれまでの経験では、以下のようなことがありますが。 1.電磁気にはベクトルポテンシャルがあるが、流体力学にはあまり出てこない。 2.流体力学の流速は千差万別で、流速がどのように分布するかが大きな興味ですが、電子では流速の空間分布にあまり関心がない。(そんな気がするというぐらいですが) 3.電界・電荷に対応した概念が流体力学にない? このような違いも実は、読み替え(対応物)がある(例えば名称としてはないが)ということになるのではないでしょうか。 電磁流体力学という分野がありますから、相互乗り入れできるという意味で類似と相違があるということなのかなと思います。 突き詰めると、統一理論になるのかもしれませんが、そこまで大げさには考えていませんが。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答






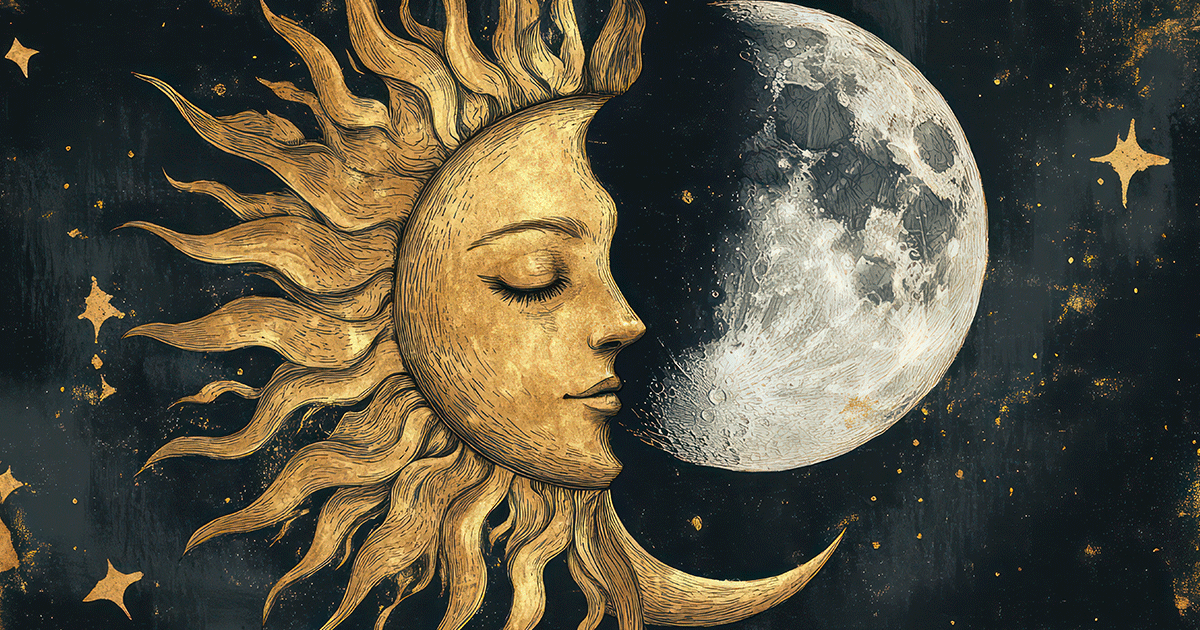






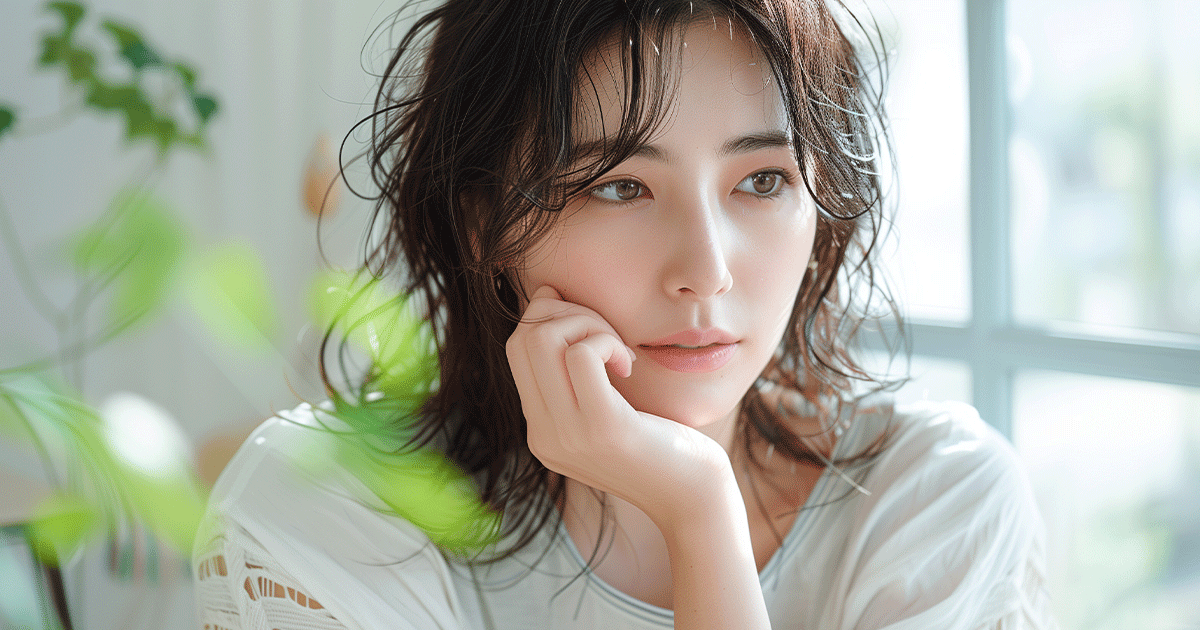

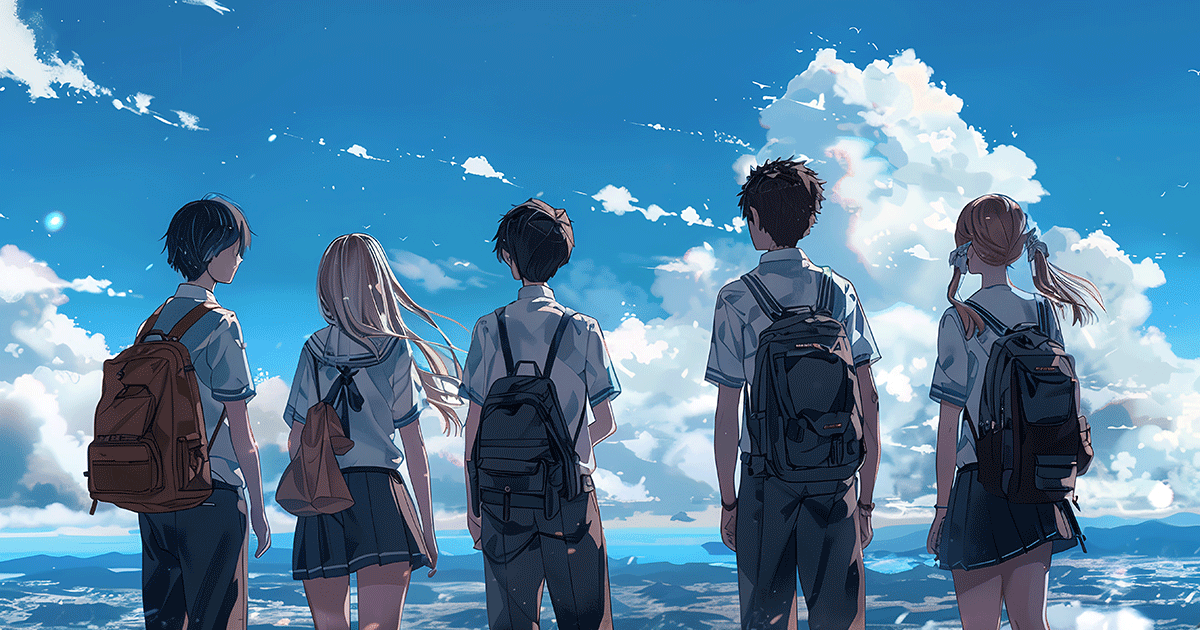








お礼
広範な考察が展開されていて大変ありがたいと思います。両方の成り立ちを極微の世界から論じる場合や、式が出来上がったあとで、計算する(式があって計算だけするのであれば理論を知る必要がないと極言できると思いますが。知っていたほうがベターでしょうが)という視点からの考察も展開されているようです。 目線をずっと低くして、以下のようなことがあります。 1クーロンの電荷を電界に逆らって移動して1Jのエネルギーを与えた場合、その電荷には1Vの電位差が与えられた。1kgの水に塊を重力に逆らって1Jのエネルギーを与えると1/9.8[m]高いところに移動している(その高さの分、斜面を登っている標高)ということになります。 まるで、電位と標高が同じもののように見えるのですが、電位は電磁気学の内部だけれども、標高は流体とは異なるということになります。 そっくりだ!と思うと、そっくりでなく、全然違う思うと、似ている!となるわけです。 ランダウリフシッツよりも、ファインマンさんあたりを引っ張りだすのかな?などと思うのですが。