「試験のため」の勉強は批判されることも多いですが。1級レベルになればそれが当然求められるということは了承していただける前提で書きます。まず、応用問題が解けない理由はいくつか考えられますが、
自分では基礎はできていると思っているが実はそうではないため、少々の変化に対応できていない場合:
この場合、例えばテキストの基本問題ができているつもりでも、実はどちらかというと単に答えや解法を覚えているだけで、実践になるとそれを思い出せなかったり、そもそも論点の本質が理解できていないため、少しひねられると対応できないことが原因と考えられます。したがって、時間があるのであれば、一つ一つの論点をじっくりつぶすべきです。具体的には簿記初心者レベルの人に処理とその理由を簡単に説明できるレベルまで理解すれば完璧です。
次に基礎は理解しているが練習不足。応用問題や総合問題に対する慣れが不足している場合:
上記のステップはクリアしていても総合問題などはやはり慣れが必要であることは間違いありません。具体的には問題を解く順番、時間配分や数値の集計の仕方などが挙げられます。これはもはや量をこなすべし、というのが率直なアドバイスだと思います。
簿記の場合は問題を読んだら体が反応するというレベルが理想です。つまり問題を解いている時に問題文を読む時間を除いて、鉛筆の筆記音か電卓を打つ音がしない瞬間(=考えてる時間)がないようになるまで体に覚えこませる必要があります。
1級は難しい試験ではありますが比較的時間には余裕があるのでそこまでなる必要はないかもしれませんが、こうすることによって見直しの時間や初めて見るような問題にじっくり取組むための時間を確保でき、結果としてアセリからのミスなども減らせます。
以上、個人的なアドバイスですが、「そんなこと分かってるよ」と思われかもしれません。しかし、私の勉強していたころの経験や周りの状況を考えるとほぼ上記2点のいずれかに引っかかっていました。頻出論点(問題)に関しては「大体できる」ではなく、1級を目指す場合は大げさに言えば「極める」必要があります。まずは基礎問題を体に覚えこませて、応用問題等の数をこなしてみてください。






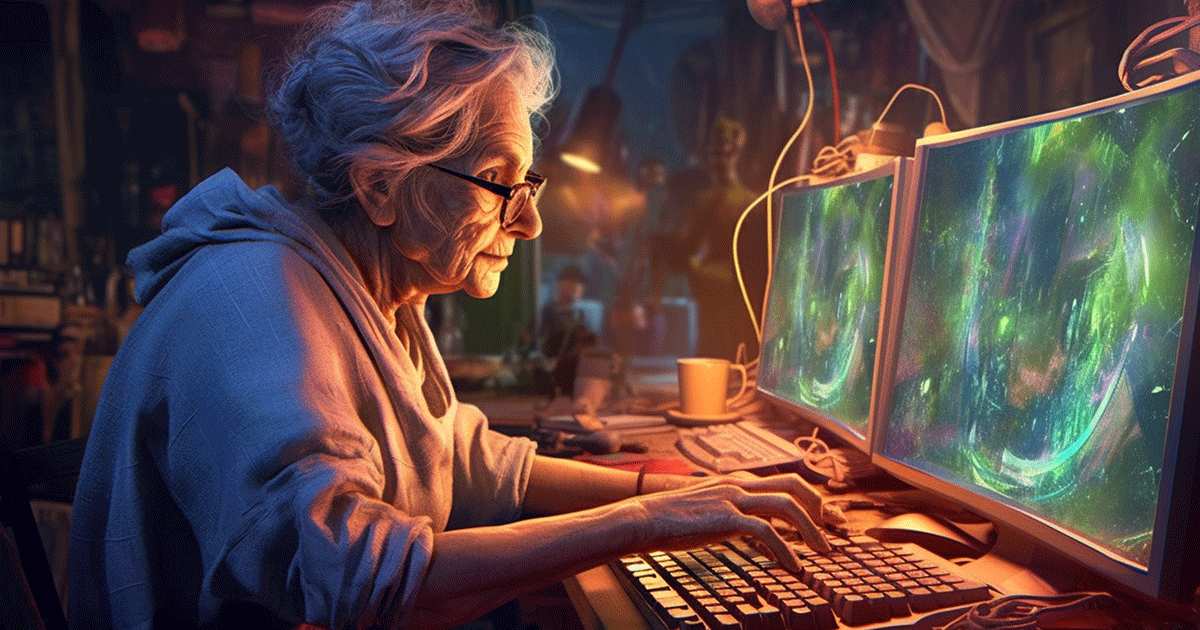


















お礼
事細かなアドバイスありがとうございました。 論点を理解して分からない問題も答えを見ながら出来るまで がんばろうと思います。 出来るから「極める」の方向で!!