経験者と書きましたが、実のところ金融系のシステムは未経験ですので、あくまで推測です。
報道等で聞いている限りでは、今回の統合は、元々の三行のシステムがバラバラだったが、
それを一つに統合することもできないので、元の各システムを維持したままリレー
コンピュータで連携させるようにしたということです。互いに異なったシステムを連動
させるというのは、オープン系のシステムならば普通に行われていることで、それ自体が
間違っているとは思いません。
ここで、リレーコンピュータの役割は何だろうと考えてみると、とっさに思いつくだけで
次のような機能が考えられます。
(1)データの送り先を判断するルーティング機能
(2)データを一時的に保存するバッファリング機能
(3)データを通信方法の異なるシステムへ送るためのプロトコル変換機能
(4)データを構造の異なるシステムで扱えるようにするためのコンバージョン機能
他にもあるかもしれませんが、とりあえずこれだけの機能として考えます。
四つの機能のうち、最も複雑なのがコンバージョン機能です。金融システムで使われている
メインフレームという種類のコンピュータでは、各メーカーが独自の仕様でシステムを
作ってしまい、メーカーが異なると全然動かないようになっていたのです。(そのように
して、メーカーはお客が逃げないようにしたのです。パソコンなどは、逆にオープンにする
ことで、新しいお客を獲得しやすくしました。)このため、一つのシステムのデータを別の
システムへ送るために、データの形式を変えなくてはならなくなります。一口に言えば
簡単ですが、実際には大変です。例えていうと、一つのシステムでは「水」と「湯」という
別の形式で扱われているものが、別のシステムでは「Water」という一つの形式で扱われると
いったようなことが頻繁に起こります。(あくまで例えです。)
こうしたレベルの設計がきちんとできていないとシステムを連動させることはできません。
が、個人的には、今回起きたトラブルはこうしたレベルの問題ではなかっただろうと思います
。というのは、もしそうした問題が残っていたとすれば、二週間やそこらで復旧するとは
思えないからです。
次に複雑なのはプロトコル変換機能です。例えばインターネットならば、TCP/IPという
標準化されたプロトコル(通信の約束ごと)がありますから、Webページがどんな機械に
置かれていようと、またユーザがどんな機械で閲覧していようと、関係なしにデータを送る
ことができます。ところが、上に書いたように、各行のシステムが異なりますから、
通信方法も異なります。ストレートに送受信できれば問題はありませんが(そんなレベルで
問題があればお話になりませんが)、もし送信が正常に行われなかったらどうするか、
システム全体で矛盾が生じないよう、細かく決めておく必要があります。このレベルで
問題が発生した可能性は小さくないと思います。
ルーティング機能は、プロトコル変換機能とも関係するものですが、このレベルで問題が
起きたとは思いません。
もう一つ問題が起きた可能性があると思っているのは、バッファリング機能です。処理量
が予想を上回ったとコメントされているからです。
・・・と推測した上での私の評は「お粗末」です。データ収集不足とテスト不足以外の
何ものでもありません。バブル崩壊からこの方、ダウンサイジングやアウトソーシング
といった様々な波がシステム部門を襲ったはずで、あるいは要員が不足していたのかも
しれませんが、もっときちんとできたはずだと思います。













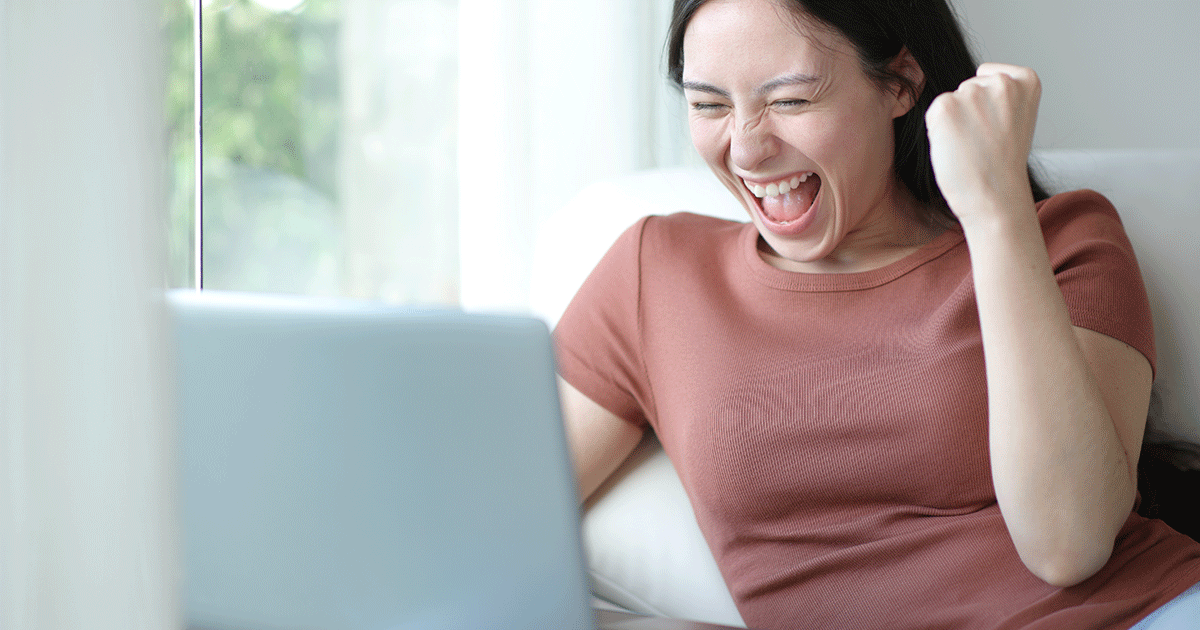














お礼
返信ありがとうございました。 今回のトラブルはなんとなく「Y2K」で指摘されていた ことがそのまま出ているような気がします。 「Y2K」の時はエンジニアの方々も初めての経験であり 「危機感」があったと思うのです。 それで、当初言われていたトラブルが発生しなかった と思っています。 やはり甘く考えていたのかもしれませんね。