生産緑地法第10条の解釈について。
野菜を中心とした畑作をしていた父と、高校を卒業後父の後を継ぎ、「茶葉」生産に切り替えてきた、子がいます。後継者のできた父はその頃から農業経営から離れ、農協の役員活動などを行い、その農業経営は、実質子供が行っていました。(ただし、農業所得の申告は昔ながらの「家督相続」や「家」の代表がする。という風習のもと、父でしています・・)
そんな状況の中、平成4年、生産緑地法の改正があり、父と子は同意の上、生産緑地指定を所有の畑にしました。その後、父は、高齢になり、体の具合も悪くなり、畑作業はもとより、外出もしなくなり、平成12年に亡くなりました。
ここで、悩んだことですが、生産緑地法第10条に、
(生産緑地の買取りの申出)規定があり、その内容は「生産緑地(・・・・・)の所有者は、・・・告示の日から起算して30年を経過したとき、又は当該告示後に当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(・・・)が死亡し、若しくは農林漁業に従事することを不可能にさせる故障・・・を有するに至つたときは、市町村長に対し、・・・、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。・・・・・・書面を添付しなければならない。」
と、なっています。今回の事例のように、父は、所有者ではあるが、主たる従事者ではない場合、(後継者である主たる従事者もいる状況である)買い取りの申し出は、法律上できるのであろうか?






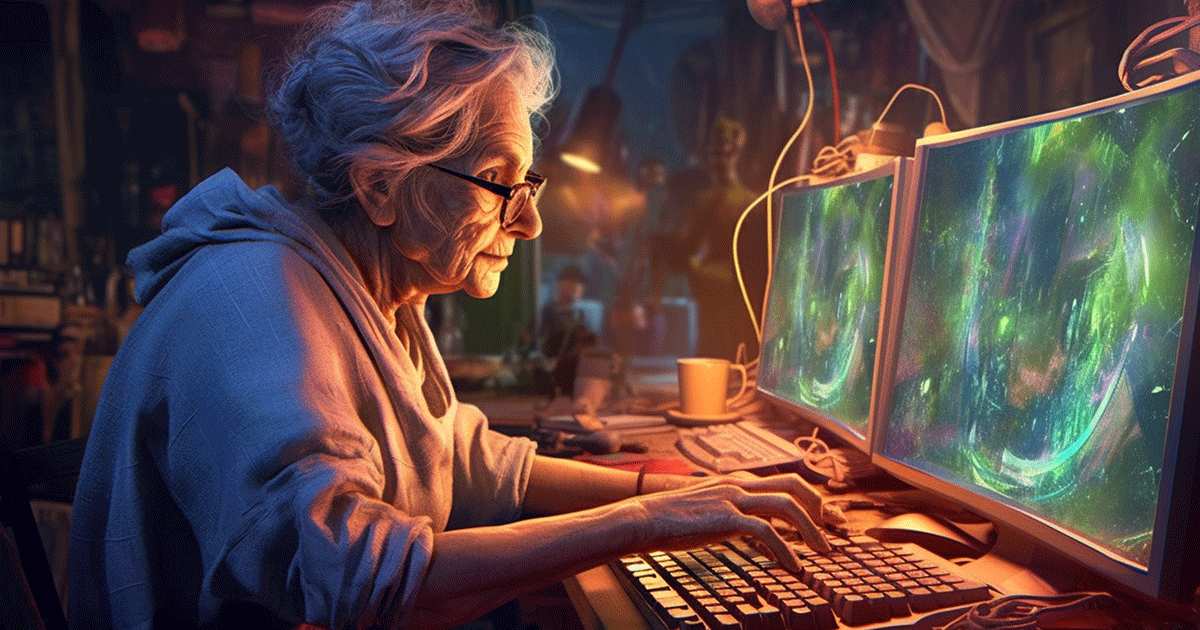






















お礼
「普通の土地と同じようになる」という言葉でよくわかりました。どうもありがとうございました。