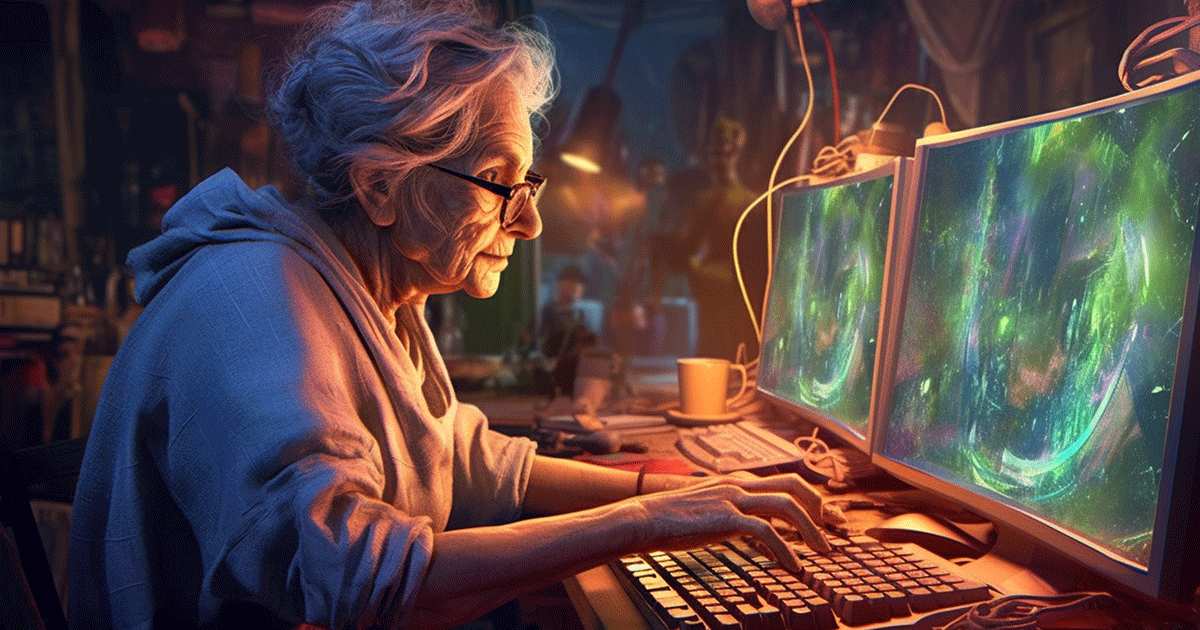- 締切済み
簿記の参考書について・・・
よくわかるだの、すっきりするとかいう本が出ていますが理屈ありきでそれこそ分かりにくいです。 それこそ、しーくりくりしーみたいな語呂合わせ公式みたいな解説や説明がないのはどうしてですか? NETや専門学校の先生の講義では出てきますが参考書テキスト本には出てないですよね?どうしてですか。 理屈で覚えるものはあるでしょうが結局無理にでも覚えないことには・・・。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2
- tomson1991
- ベストアンサー率70% (914/1304)
回答No.1