法人で雇用し、法人の業務をさせるのですよね。
そうすると、法人として税務署へ届出が必要となります。
給与支払事務所の開設に関する届です。すでにあなたの役員報酬を支払うために届け出ていれば必要ないでしょう。
雇用保険単独での加入はできないと思います。労災保険と雇用保険をセットで労働保険と呼びます。どちらも役員は基本的に入れませんので、あなただけであれば何も手続きをしていないことでしょう。
法人の管轄の労働基準監督署で、労働保険としての手続き、労災保険の手続きを行いましょう。子の際には、4/1から3/31を計算期間とする労働保険料(労災&雇用保険)を1年分前払いすることになると思います。雇用保険の手続きで労働保険の番号などが必要となるので、順番に注意しましょう。
労働基準監督署での手続きが終わったら、管轄の職業安定所での手続きが必要となります。雇用保険の事業所としての手続きと従業員の雇用の手続きが必要となるでしょう。
厳密な話をすると、株式会社として法人組織なわけですから、社会保険にも加入義務が生じます。加入義務を果たさない経営者もいるようですが、今後の法改正などで厳しくなる見込みもありますので、あわてることのないようにしっかりと手続きを行いましょう。
ちなみに、労災保険料は雇用する会社が全額負担となります。それも前払いです。給与変動分は翌年に清算することとなります。雇用保険料は折半で負担となりますが、従業員負担分を含めて1年分前払いとなります。社会保険料(健康保険・厚生年金保険)については折半ですが、通常給与天引き後の納付のタイミングとなるため、給与天引きにより従業員から預かった分とその同額以上(児童手当拠出金など)を合算しての納付となります。小さい会社の多くは、これらの会社負担が厳しく、いい加減なところも多いようです。
これらの会社負担を含めて給与などを算定する必要があります。
さらによく知っている間柄であっても、お金が絡めば争いにもなります。雇用する側の方が法律では弱く、従業員を守る法律が多いのです。就業規則などの諸規則を決めてその人に見せ理解させること、雇用の条件面を労働条件通知や雇用契約書などで明確にする必要もあるでしょう。
私の知人の会社では、従業員の情報量(WEBなど)が多くなってきたことから、解雇すれば解雇予告手当金の請求を受けたり、不当解雇と訴えられたり、見込み残業などをサービス残業として給与未払いだとか言われたり、争いになることも多いようです。
あとは、従業員の住民税の特別徴収(天引き)についていい加減な情報が多いですが、原則給与支払者の義務となっています。そのための手続きも必要となります。
これらの手続きは最初だけすればよいのではなく、所得税の年末調整・社会保険の年度単位の扶養の確認・労働保険の申告・社会保険の最低基礎届や月額変更届・住民税などのための法定調書関係手続きなどといろいろあります。これらは税理士の分野だけでなく社会保険労務士の分野も含まれるため、顧問税理士がいてもいい加減な取り扱いをしている会社も多いようですね。
すべての窓口でいろいろな資料をもらい熟読し、わからないことは窓口相談をしたり、専門家を活用しましょう。







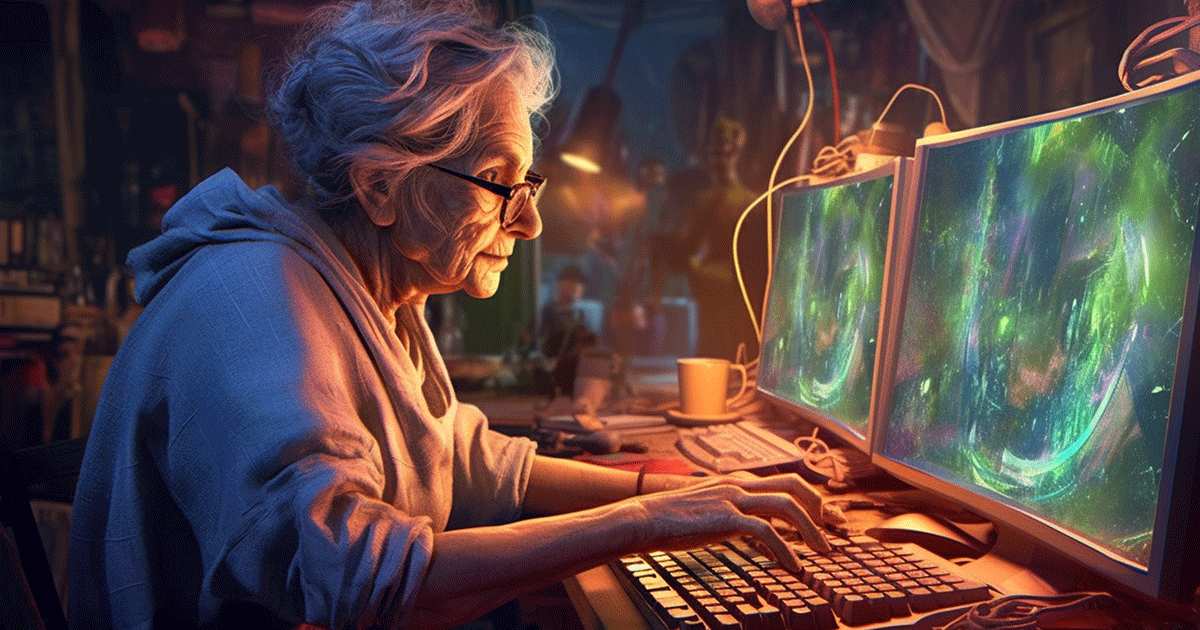



















補足
回答ありがとうございます。 今度雇う人は、信頼できる先輩ですのでもめる点は問題ないと思います。 順調に業務が増えてきているのでフリーと言うよりは、会社として大きくしていくステップとしての増員になりますので、一部ではなく私と同じように出来る人がほしいのです。 ただ、先輩としては後々家を購入したいそうで、基本的に正社員にならないとローン自体が出来ないので正社員になりたいそうです。 なので住宅ローンが通るような正社員にするにはどのような手続きが必要かを聞きたかったのです。 例えば、正社員として登録するなら何処かに届出をする必要があるとか。など お願いします。