年金受給開始後の受給額の変化
年金受給開始時の支給額も大事ですが、受給開始後の年金額の変化も大事な事です。が、話題にならないので詰めて質問します。下記の資料を見つけました。
https://www.nenkin.go.jp/mobile/faq/jukyu/kyotsu/gakukaitei/201805-8.html
基礎年金について
1)基礎年金は全て「780,900円(平成16年度額)」に年次の物価、賃金、マクロ経済の3スライド倍率を掛け算して算出しているようです。仮にこの先「780,900円」が変更された場合、既裁定者の年金額は影響を受けるのでしょうか?
2)1)で60歳以降に受給しながら厚生年金に加入している場合、1年ごとに受給額が見直されて(1年ごとに加入年数が伸びる分だけ)受給額が増えていきますが、「受給&加入」中に「780,900円」が大幅に減額された場合」、年金支給額の計算方法はどうなるのでしょうか?
1年ごとに全加入期間分丸ごと裁定となるのか、加入年数が伸びた分だけ裁定になるのか、どちらですか?
3)前年度改定率、物価、賃金、マクロ経済の3スライド倍率の4つを平成16年度から現在まで一覧で見られるサイトはありますか?
厚生年金(報酬比例分)について
4)物価、賃金、マクロ経済の3スライド倍率は無く、平均標準報酬額※の現在価値換算を変更するだけのようです。この倍率(再評価率)は過去数十年分わかるといいのですが、どこか公開されていますか?
5)マクロ経済スライドというのはとても話題になったのですが、これを適用するのは基礎年金だけですか?
6)「5.481」という掛け率が変更された場合、既裁定者の年金額は影響を受けるのですか?
7)「受給&加入」中に「5.481」という掛け率が変更された場合、年金支給額の計算方法はどうなるのでしょうか?
1年ごとに全加入期間分丸ごと裁定となるのか、加入年数が伸びた分だけ裁定になるのか、どちらですか?










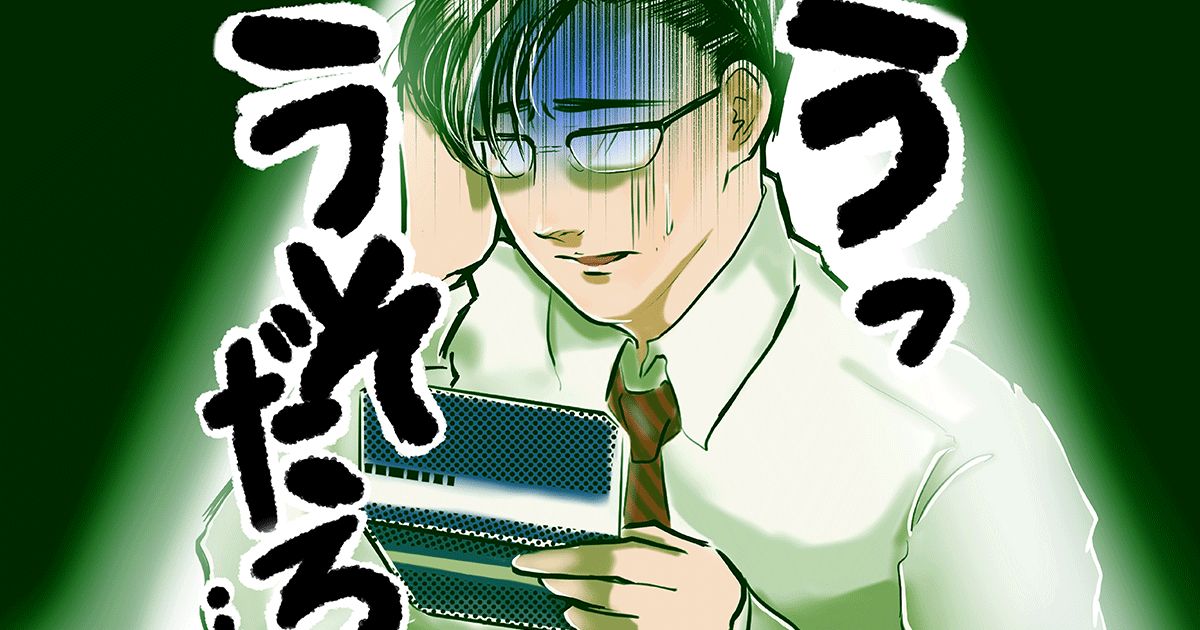
















お礼
長期出張で昨日帰宅しました。 お礼が遅れて申し訳ありません。 具体的な説明でよく理解できました。 このような仕組みになっていることを、知るべきだったのでしょうが、どれだけの方がご存知なのでしょうか。 私は単に、同じ会社で、そんなに処遇も違わないのに、何故年金にこれほど差があるのかという素朴な疑問でした。 義父は現在34万ほどもらっていると聞いています。80歳までは更に企業年金がありましたので、ゆとりのある生活でした。今でも、毎週、同僚と連れ立ってゴルフにも行っており、私もそばで見ていて、それに近い生活かと思っていたら、金額の低さにびっくりしたものです。 保険方式ではなく、世代間の助け合いという考え方はいいと思いますが、受給世代のなかでこれほど格差が有ることに政治家は問題意識を感じないのか不思議です。 世代間の助け合いという概念のなかに、自己責任を除く体系に社会的な公平が一番優先すると思っていましたが、現実は個人の財産権の保証が重要視されるんですね。 皆で苦しい難局を乗り越えようというときに、原資はひとつでそれを分け合おうというなら我慢もできますが、このような不公平に気づいたら納得しないと思えます。 先般の後期高齢者医療については「かわいそうなおじいさん達」というイメージでマスコミも伝え、結局つぶしてしまいましたが、このような恵まれた世代であるなら、かかる費用は堂々といただいたらいいと思いますが。 ちょっと脱線してしまいました。 よく説明いただきありがとうございました。