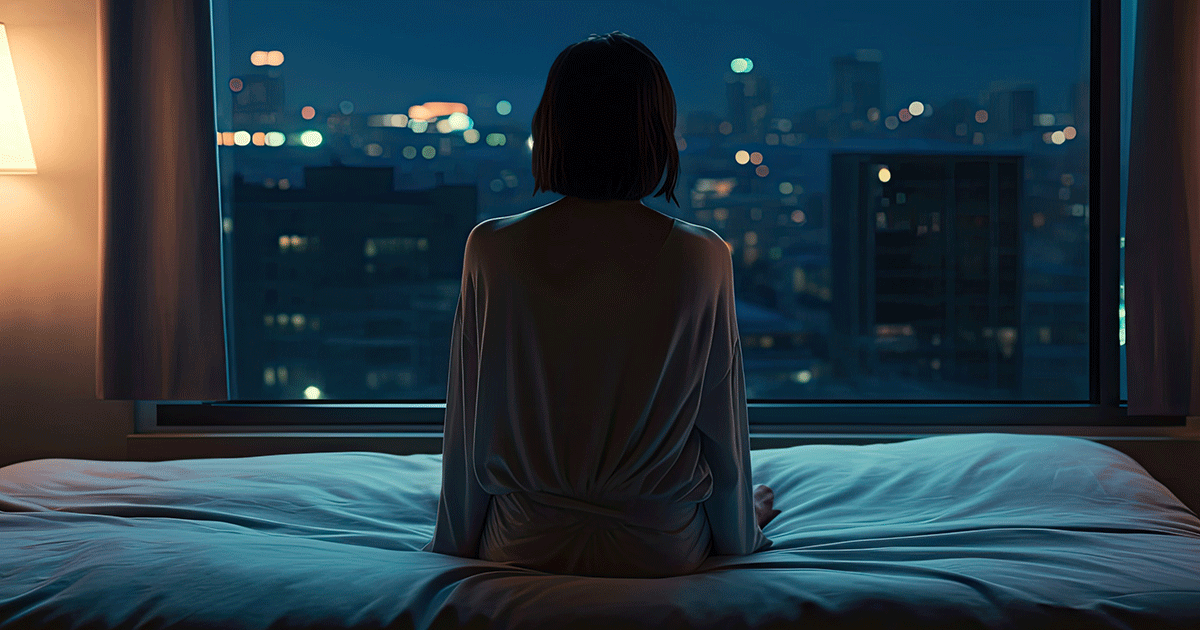質問1.
脳(中枢神経系)には、大脳、小脳、中脳、橋、延髄、脊髄という部分があります。このうち、中脳、橋、延髄を脳幹といい、呼吸、循環などの生命に直結する機能の司令塔となっています。脳幹の機能が失われると、生命維持に欠かせない呼吸が止まってしまい、生命活動がとまってしますということになります。
ところが、人工呼吸器(レスピレータ)によって、脳幹機能がなくなり、自発呼吸が停止した人に、人工的に呼吸させることができるようになりました。
人工呼吸器で呼吸を維持すれば、脳幹機能が廃絶していても、心臓は動き続け、その結果呼吸と循環は一定期間維持していける状態が生まれました。これが脳死です。
厚生省脳死判定基準は「前提条件」、「除外例」および「判定基準(判定のための諸検査)」で構成されます。
「前提条件」と「除外例」
脳死診断を行う患者の前提条件は、
1.器質的に脳が障害されている
2.深昏睡・無呼吸である
3.脳障害の原因が確実に診断されている
4.適切な治療を行っても回復不能である
の4点ですが、6歳未満の小児、薬物中毒、32℃以下の低体温、代謝・内分泌疾患患者さんのケースは脳死の診断から除外します。。
「判定基準(判定のための諸検査)」
「前提条件」を完全に満たし、「除外例」を除外した上で、以下の諸検査を行います。
1.痛み刺激にも反応しない深昏睡。
2.脳幹の機能を反映する自発呼吸が、完全に停止しているかどうか。これを調べるためには、人工呼吸器をはずして、自発呼吸が出てくるかどうかを確認します。
3.瞳孔が固定していること。以前は瞳孔が「散大・固定」と表現したが、現在では、瞳孔が直径4mm以上で、特に散大がなくても、固定して光に対して反応しないということが必須条件となっている。
4.すべての脳幹の反応が消失している。
5.脳波が平坦である。植物状態では、正常とは異なりますが、脳波の波形は見られます。一方、脳死(全脳死)では波形はまったく見られなくなります。感度を最大に上げて測定しても波は平坦になります。脳死の判定では、最低30分間脳波をとります。
質問2.
脳死は生命活動を司る脳が機能不可能になったということです。心臓の筋細胞と脳神経細胞は一度死んでしまうと、再生されません。深い昏睡から覚醒したということは聞きますが、それはあくまでも「深い昏睡」であって、一見「脳死」と混同されがちですが、きちんと脳幹は機能しているので、「脳死」ではありません。
質問3.
約半数の脳死者は2~3日で心停止に至ります。また、通常は1週間でほぼ70~80%が心停止に至ります。しかし、脳死が死であるという意味は、一定期間後に心臓が止まるからではありません。脳幹を含む全脳の血流が止まってしまい、脳自身が融解して壊死するからです。「人間は考える葦である」という言葉のとおり、人間の生命活動の中心は心臓ではなく、脳です。
「脳死」と「心臓死」の定義をはっきり理解しておくことが必要と思われます。
回答らしい回答ではありませんが、お役に立てればと思います。