私は書籍の編集者です。
詰め打ちは、普通、その文字列に緊迫感を出すために用いられます。
だから書籍の場合、装丁や扉、見出しによく使いますが、本文には余り使いません(よほどデザイン的な本なら使います)。
以前一緒に仕事をした装丁家の方は文字のつめ打ちについてこういってました。
「文字にはひとつひとつ重心がある。それを整えるようにつめてゆくんだ」って。
たとえば「あ」は真ん中にありそうですよね。「つ」なんて結構迷いません? 「し」や「く」なんかフォントによって違ってきそうですよね。「●」を持ち上げる(ベースラインシフトといいますが)のも、同じことでしょうね。
それからもう一つ、読みやすいように字間を調整する方法に、雑誌でよく使いますが、ある文字群の両端をそろえる、というのがあります(ジャスティファイといいます)。お手近にある雑誌をよーくご覧ください、字間が微妙に違っているのがありません? それがそうです。そして、ごくごくたまーに字間がものすごく空いている箇所も見つかるかもしれない。これは機械的にジャスティファイをして、その後点検しなかったため。
結局、文字を詰めるという問題は、綺麗で見やすい紙面をどう作るかという大問題の一部なんですね。もし、あなたが首都圏にお住まいの方なら、江戸川橋にある、印刷博物館に行ってみるといいですよ。昔から、綺麗な本を作るために、人が何をしてきたかがわかります。
あんまり文章が長くなるので、この位にしますが、この世界もはまると深いので、どうかご注意を。でも、面白いですよ~。







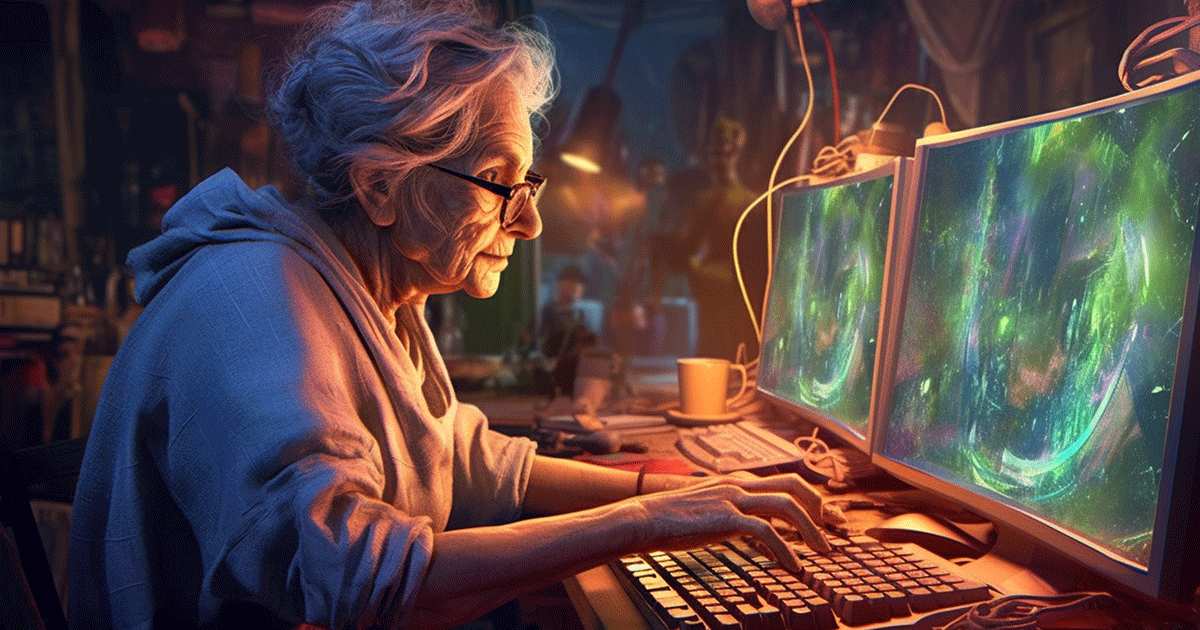


























お礼
それそれ!!そういう話を待ってました♪ キヤノンの話、はじめて知りました。なるほど・・・。^^ デザイナーさんたちは、 綺麗な絵を作るだけじゃなくって、そんなにもいろいろなことを 考えてデザインしてるんだなぁ・・・って感動しました。 ご回答ありがとうございました。