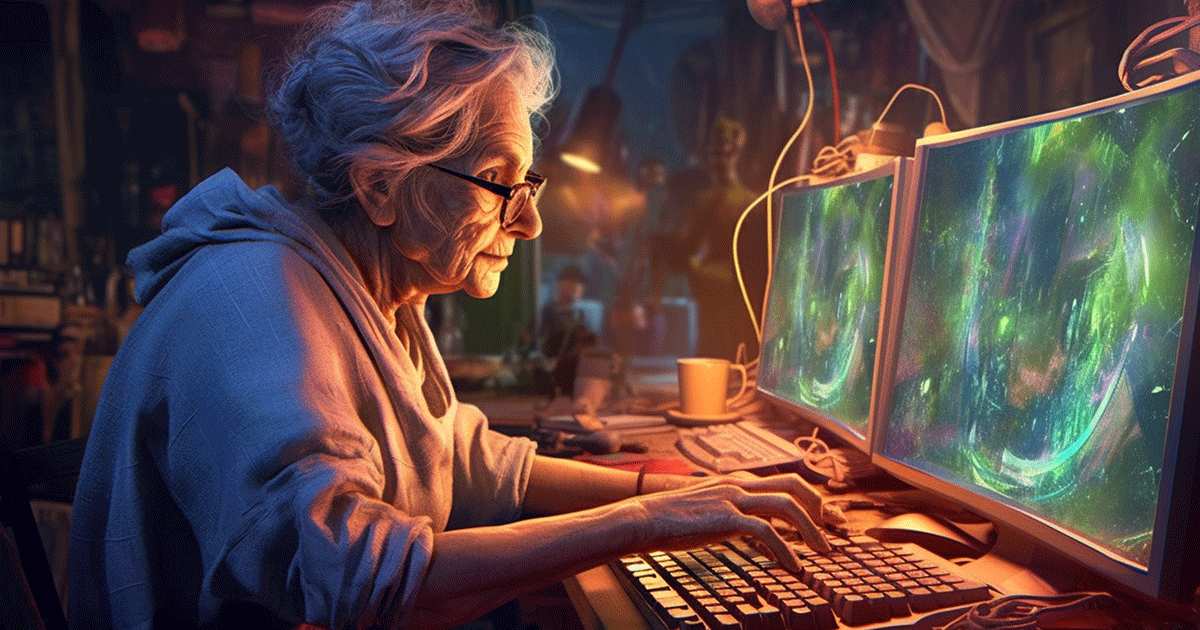※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大変恐縮です。もう一度お教え下さい)
再就職先での離職票発行と雇用保険加入条件について
このQ&Aのポイント
再就職先での離職票発行について、原則離職後10日以内に行われますが、自治体により緩和措置として離職後12日過ぎたらハローワークにゆけば離職票の仮受付が可能です。一部の条件を満たせば、最短1か月後前後に給付金を受け取ることができます。
再就職先での雇用保険加入条件について、雇用保険は社会保険の一部であり、現職で社会保険に加入している場合でも、雇い止め後の再就職先が社会保険加入条件を満たしていなくても雇用保険に加入することが可能です。高齢者失業給付金の受給条件についても再度説明します。
高齢者失業給付金の受給条件について再度確認し、雇い止め後の再就職先における雇用保険加入条件を知りたいと思っています。
syakurekappa1様
ご回答本当に感謝いたします。昨日総務の方にご回答者様のご意見を参考に再度
問い合わせました。
1、離職票
月末締めでの給与計算も元に発行となるので、離職後10日以内に行うが原則いつとは約束できない、が、自治体により緩和措置として離職後12日過ぎたらハローワークにゆけば、離職票はその場に無くても仮受付ができ7日待機ご指定認定日ご数日での支給対象になる場合があるので、総務では10日以内に意をくんで早期に出すよう努力するが、一応ハローワークにも確認をしておいて欲しいと言われました。
私としては、現段階から求職活動はしてますが今まで15万前後の月収がゼロになり
6月は会社から5月分給与で生活は可能ですが、高齢者失業一時金を6月以降加入する国民健康保険に充て、H31年度の市町村民税が別途かかってくる分を遣り繰りするため、一時金は何としてももらいたいと考えてます。6月に入り全ての書類が準備され(或いは一部残しでも申し込み)ハローワークで申し込み完了しても最低給付金を受け取るには最短1か月後前後と聞きます。6月中に何とかハローワークから給付金を頂くにはやはり離職後会社に頼み込むしか方法は無いでしょうか?
2、追加質問ですが雇用保険に関してお教えください。
私は68歳ですが、75歳ぐらいまではパートで生活希望してます。
離職後再就職先にて、雇用保険に加入されていただく条件は如何様でしょうか?
例えば、雇用保険は社会保険の一部と聞きます。私は現職では労働条件から社会保険加入と言われ(健康保険、厚生年金他加入)支払い継続してきました。今回の雇い止めで失業保険も受けられる条件になってます。仮に今後再就職先が現職のように社会保険加入条件に満たない職場であっても、雇用保険には加入できますか?
仮に雇い止めになった場合を想定すると、高齢者失業給付金は非常に助かる制度なので、雇用保険加入条件を今一度お教え下さい。
以上 再び伺う事お許しください。