脂肪はとりすぎると肥満や生活習慣病の原因となりますが、炭水化物、タンパク質と並んで人間にとってなくてはならない重要な栄養素です。
脂質の役割としては、
1)エネルギーの貯蓄体になる
2)生体膜の材料になる
3)ホルモン、抗酸化物質、色素、成長因子、ビタミンなどの材料となる
等があげられます。
脂質が不足すると
1)細胞壁や血管壁がもろくなり、脳出血などの原因となる
2)脂溶性ビタミン(A,D,E,K)の欠乏とそれによる障害の発生
3)発育障害
などがおこります。
肉などに含まれる飽和脂肪酸は体の中で糖質から合成できますが、多価不飽和脂肪酸の内n-6系脂肪酸(リノール酸)とn-3系脂肪酸(αリノレン酸、DHA、EPA)は体の中で合成できないので、植物からとらなければなりません(必須脂肪酸)。
脂肪の摂取の目安は、成人の場合は全摂取エネルギーの20~25%です。脂肪は
飽和脂肪酸:一価不飽和脂肪酸:多価不飽和脂肪酸=2:3:2
n-3系脂肪酸:n-6系脂肪酸=1:2
でとるのが望ましいとされます。
現在の日本人の平均では、飽和脂肪酸やリノール酸が過剰で、n-3系脂肪酸が不足しています。飽和脂肪酸やリノール酸をとりすぎると、動脈硬化やアレルギーの原因となります。n-3系の脂肪酸や一価不飽和脂肪酸(オレイン酸)を積極的にとることが健康維持に有効です。








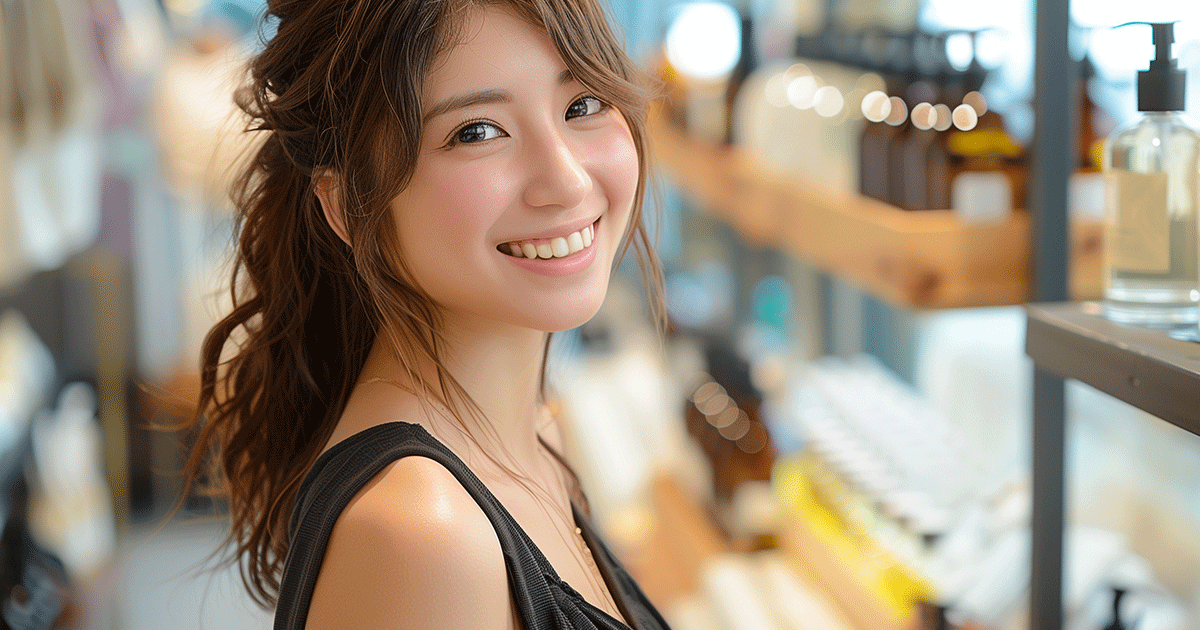















お礼
詳しい説明ありがとうございます。 脂肪を摂取することの重要性がわかり、以前よりも食事を楽しめるような気がしてきました。