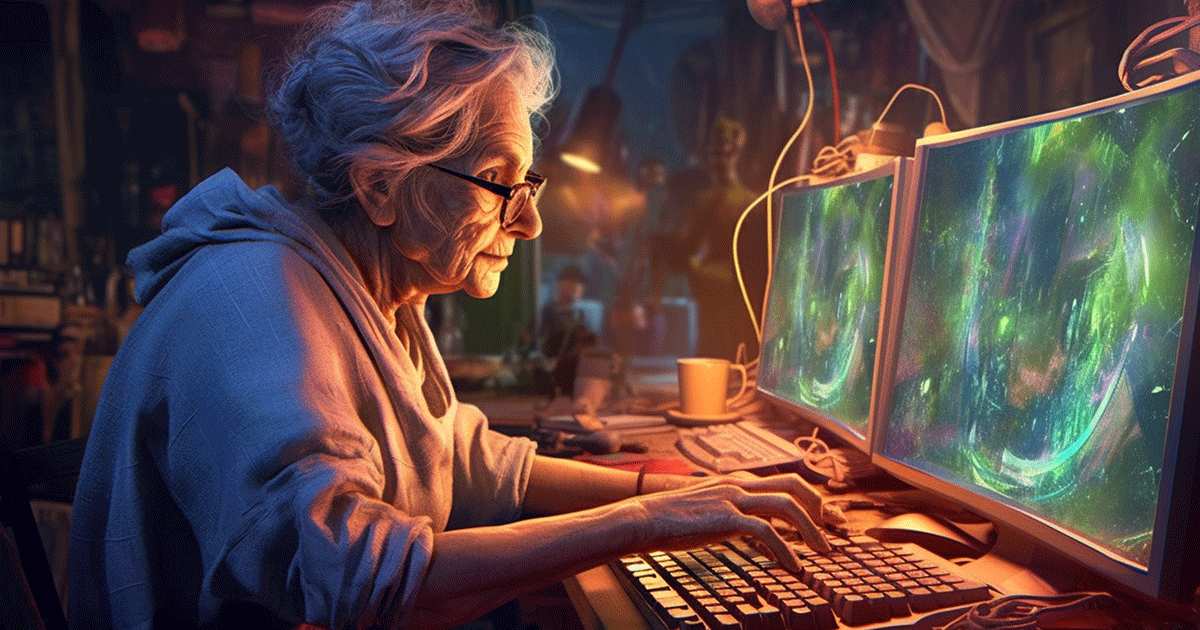表面処理がある部品の勘合部の製図方法について
メッキやアルマイト等、表面処理がある部品図の製図?(設計?)について困っています。
問題にしているのは、
例えば、軸受けやオイルシール等のハウジングの勘合部分です。
(ハウジング以外にも勘合部分です)
図面は最終形態を表すと思っているので、図面に寸法と公差と入れ、メッキを指示してあればその通りに出来上がっていると思っていました。
例えば、穴:φ10に公差±0.1、メッキを指示した図面の場合。
部品完成後は当然メッキが施されており、寸法もφ10±0.1になっていると思っていました。
しかし、当社の部品は出来上がりが違っており、
メッキ前の加工したものはφ10±0.1ですが、その後メッキを施し
φ10±0.1から外れています。
現場からは「メッキを施した時に膜圧で穴が小さくなるから、図面には公差を大きめにつけろ、そうすればメッキを施して欲しい寸法になる」と言われます。言っていることはわかりますが・・・
私は、冒頭にも言いましたが、
図面は最終形態と思っているので、現場の方の言うように、メッキ膜圧を考慮した寸法公差にして、メッキを施すと理想の寸法に仕上がるようでは、その図面と完成したのが違い、図面通りにできていないことになると思います。
それで、そのやり方が納得できず、いつも現場の方に怒られています。
私も、自分の持論(図面は最終形状を表すもの)を現場の方に説明しますが、わかってもらえません・・・。
メッキ膜圧を、メッキ屋さんから聞いて、
その膜圧を考慮した寸法公差で加工してもらい、その後メッキを施せば
図面通りに完成すると思うのですが、なぜかそういうことはしないです。
メッキ屋さんに聞く事が面倒くさいのか、現場の持論が譲れないのか、
理由はわかりませんが、対策しないです。
(私は、改善したいのでここで質問しました)
そこで皆さんの会社では、どうしているのかお聞きしたいです。
どのように、図面を描いていますか?
勿論、重要ではない部分は何も指示しなくても言いと思いますが、
勘合部分などの重要な部分はどのようにしていますでしょうか?
例えば、軸受けやオイルシールのハウジングや、モータを取り付ける部分など。
例えばですが、図面に“メッキ前寸法***”“メッキ後寸法***”などと入れるのもありでしょうか。ただ、その辺が製図法から有りなところか、ハッキリわかりません。
他社ではどのように図面で指示しているのか知りたいです。
教えていただけませんでしょうか?
宜しくお願い致します。