- ベストアンサー
24年以降生まれでも経過的加算が付くのかしら
昭和24年4月2日以後生まれの男性は、定額部分は支給されません。 この大卒サラリーマン殿は、60歳までで厚生年金に446月加入することとなる見込みで、その後も継続して勤め、65歳で退職する予定です。 60歳~65歳の間も給与ベースが高いことにより、年金は全額カットの見込みです。 ところで、この男性が65歳で年金をもらい始めるとき、経過的加算部分は付くのでしょうか。過去スレをいろいろ見てみたのですが、どうもスッキリした例に遭遇できませんでした。 (1)この人には元々「定額部分」がない(制度上60~65歳の間に支給されることはない)ので、定額部分と老齢基礎との差額たる「経過的加算」などあるわけがない。 のか、 (2)経過的加算とは、昭和24年4月2日以後生まれの男性であっても、65歳時点で、例の「定額部分」とやらの計算式を用いて「定額部分に相当する金額」を計算し、それと老齢基礎との差額をいうのであって、誰にでも経過的加算の可能性はある。定額部分の受給権があったかどうか、また何歳で受給権が発生したのかは関係ない。あくまで65歳時点であの計算式を使って万人に対して計算するのだ。 というのか、 どちらでしょうか。私の記憶では、「(1)だ」という趣旨の回答が以前あったような気がするのですが・・・。 法律の条文をつぶさに当たれば明確なんでしょうけど素人には到底不可能です。それにつけても、今回、さんざんネットサーフィンしましたが、(1)なのか(2)なのかを明確に判別できるような上手(じょうず)な書き手って、なかなかいないもんですなぁ。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答








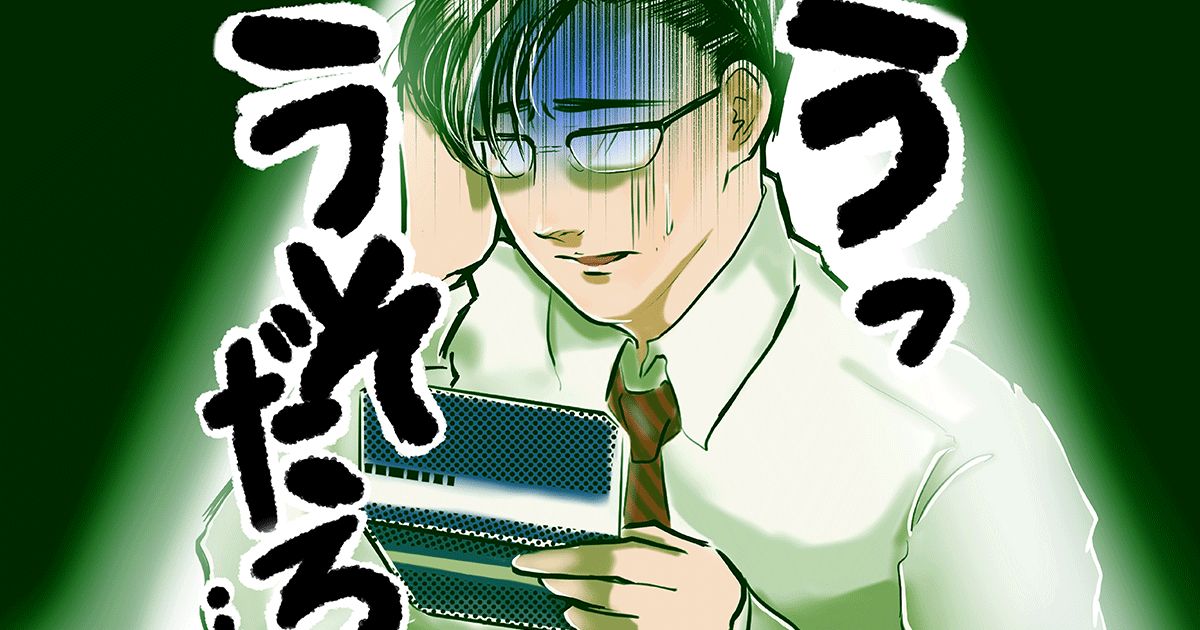
















お礼
貴重なご意見、ありがとうございます。 藤四郎の分際で言わせていただくなら、「受給年齢を勝手に65歳まで引き延ばしたんだから、"基礎"部分は当然にして20~65歳までの加入期間でカウントすべし。経過的加算でなく恒久的加算にすべし。"救済"ではなく"当然の権利"とすべし」、と言いたいですなぁ。 まぁ冗談はさておき、少なくとも65歳程度まで働くのが近年の大方の実態とすれば、大卒者で20歳から入社までの2~3年間のあいだ国民年金を支払わなかったというのも「正解」だったのかしら・・・。例えば昭和21年生まれの人なんかはH17改正で上限が一気に480月になりましたもんねぇ。「経過的加算様々」です。今、発見しました。間違っているかしら。