「後遺傷害保険」とありますが、労災の「障害補償給付」の件としてコメントします。
傷害補償給付の請求は、様式第10号(通称・10号用紙)で請求します。表面に事業主の証明、裏面に主治医の診断書となっており、表面下側に請求人、つまり被災者の署名押印をする欄があります。提出先は所轄労働基準監督署です。
次に手指の機能障害の場合、可動域制限がどの程度かを計測します。要はどの程度動きにくくなったかを健側(被災していない側の手指)と、患側(被災した側の手指)で比較する訳です。で、この計測に際して、「自動」と「他動」があります。
自動とは自分の意思で曲げること。他動とは他の力で曲がること。労災の認定は、原則的に自動計測ですから、仮に主治医が他動で計測して診断書を書いた場合でも、所轄監督署の障害認定の際の面接で、『この診断書の計測結果は他動であった。』旨を述べればいいだけです。
なお、主治医側にすると、他動であってもある程度曲がることはとても大切なことです。今後、リハビリや日常生活を経て、被災前の状態に戻る可能性があるからです。障害が残存せずに元通りに直したい!というのが、マジメな医師の考え方。ましてや大切な拇指ですから、医師も相当、気を掛けているように思います。
追記ながら、指の曲がりがよくなっても、痛みが残存すれば、神経症状として第12級(頑固な常時性のある疼痛)、第14級の補償対象となる可能性もあります。















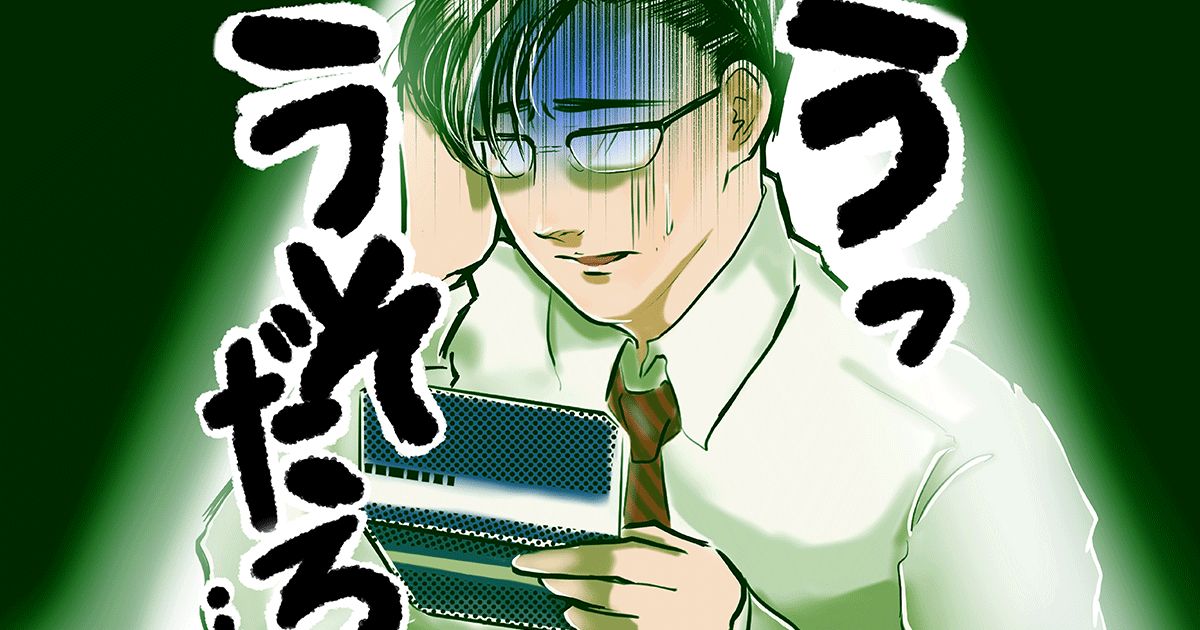


















お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。踏み込んだ回答に感謝します。