日本の商法取引関係の法律には、商品やサービスのやり取りを伴う通貨の交換の際、拒否できる金種の種類と量がはっきりと定義されています。
特に「日本銀行法」より紙幣(日本銀行券)には無限の法定通貨としての機能が明記されており、上記のような取引において紙幣の受取を断ることはできません。
ただし補助貨幣である硬貨については「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第7条」において補助通貨は額面の20倍まで法定通貨としての機能を認めていますので、それを超える額面の場合は拒否できることになります。
以上の前提を踏まえたうえで各問いに答えます。
Q1:両替とは、商品金額70円の場合
両替とみなされるのは500円以上の紙幣や硬貨になりますか?
商品の授受を伴いその商品が70円であった場合、紙幣の受取とつり銭(両替)はいかなる場合も拒否できません。硬貨の場合は単一額面で20枚を超えない場合も拒否できず、したがってほぼどのような場合もでも両替を拒否することはできません。
Q2:両替が就業規則に書いてないから、と拒否しても、客とは法的に問題ないのでしょうか?
問題があります。
質問者様の仕事が商品授受に伴う金銭の授受(決済)がある場合、それは仕事の一部ですから仕事として規定されている行為を行い、その行為に伴う日本銀行券は法定通貨ですので両替(つり銭)を拒否することはできません。
ただし、単なる両替は決済ではありませんので、拒否しても法的には問題ありません。
Q3:両替は、どちらの責任(義務)ですか?
両替は通貨で支払いを受けるほうの責任(義務)です。日本銀行法によれば、商品の授受に必要な金銭の支払い(決済)にどのような日本銀行券を使うことも認められていますので、つり銭は用意しておく必要があります。
最初に商品70円とありますので両替とはつり銭の用意、たとえば500円で70円の商品を購入した場合に70円の商品と430円の両替した通貨を支払うことと解釈しました。
間違っている場合は、ご容赦ください。







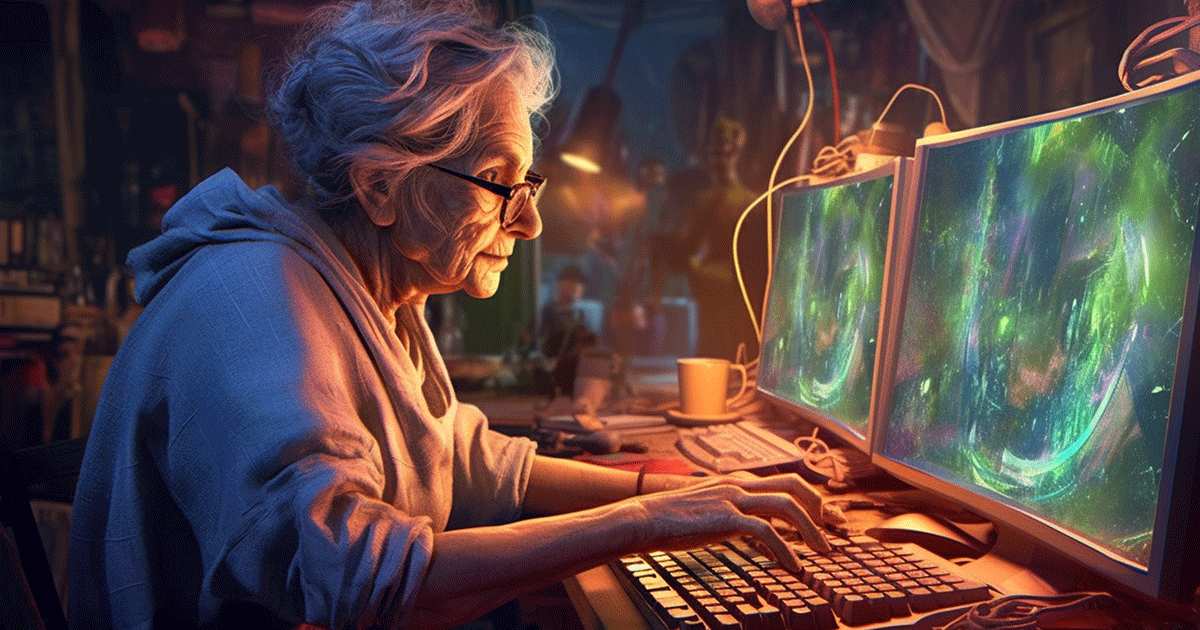

























お礼
回答ありがとうございました 予測して通りの回答の内容と思っています でも 限度(限界(自販機の釣銭切れ))があると思います その対処はないのでしょうか たとえば ただいまから釣銭切れになりました、と表示させると、万札での買い物を拒否できたりしませんか?