筋に貯蔵されているアデノシン三リン酸(ATP)とクレアチンリン酸(CP)をエネルギー源とする「ホスファゲン機構」と、もうひとつ、筋に貯蔵されているグリコーゲンや血中のグルコースといった炭水化物を分解して前述のATPを産生するのを「解糖系」機構と言って、このふたつを、所謂、無酸素系と一般的には称します。言い換えれば、これらは、酸素の関与無しに行なわれるエネルギー機構ということになります。
そして、一方、「酸化(有酸素性)機構」は、酸素供給が充分(必要最小限)に行なわれている状態に可能なもので、炭水化物、脂質を利用してその機構としての機能を発揮します。
つまり、充分な酸素供給が不要と言いましょうか、それが不十分でも可能な運動強度で行なわれるものを無酸素系と称しているわけでして、6(~30)秒がホスファゲン機構の限界点、6秒~2(3)分が解糖系、2(3)分以上を酸化系とする、というのがその時間的な目安です。陸上競技で良く喩えられますが、100Mをホスファゲン機構、400Mを解糖系、800Mを酸化系と言っています。尤も、100Mでも、10秒近くかかるわけですので、全体をホスファゲン機構でまかなうことは出来ずに、オリンピックレベルのランナーでも、その最高速(トップスピード)は80M地点の前後でして、それ以降減速して、ゴールに飛び込んでいます。
いずれにしましても、有酸素性運動とは、酸化機構のことでしょうから、2~3分以上続けられるものは、全て有酸素性運動というのが科学的には正しいのだと思います。そうしますと、様々なものが有酸素性運動に成り得るわけで、筋トレと一般的に言われているスクワット、シットアップ(クランチ)、プッシュアップでも、これを100回以上出来てしまえば、立派な有酸素性運動なんですね。逆に、筋量過少な人にとっては三分間のランニングもキツく、これが出来ないということならば、もう、その人にとってはランニング(ジョギング)は有酸素性運動ではなく、筋トレ(体重の3~5倍の荷重が片足に掛かる)そのものであって、無酸素系(解糖系)ということになりましょうね。
人それぞれ、筋量や心肺機能が違えば、同じひとつのエクササイズであっても、それが有酸素性なのか、あるいは無酸素性なのか、必然的に変わってくるということなのでしょうね。










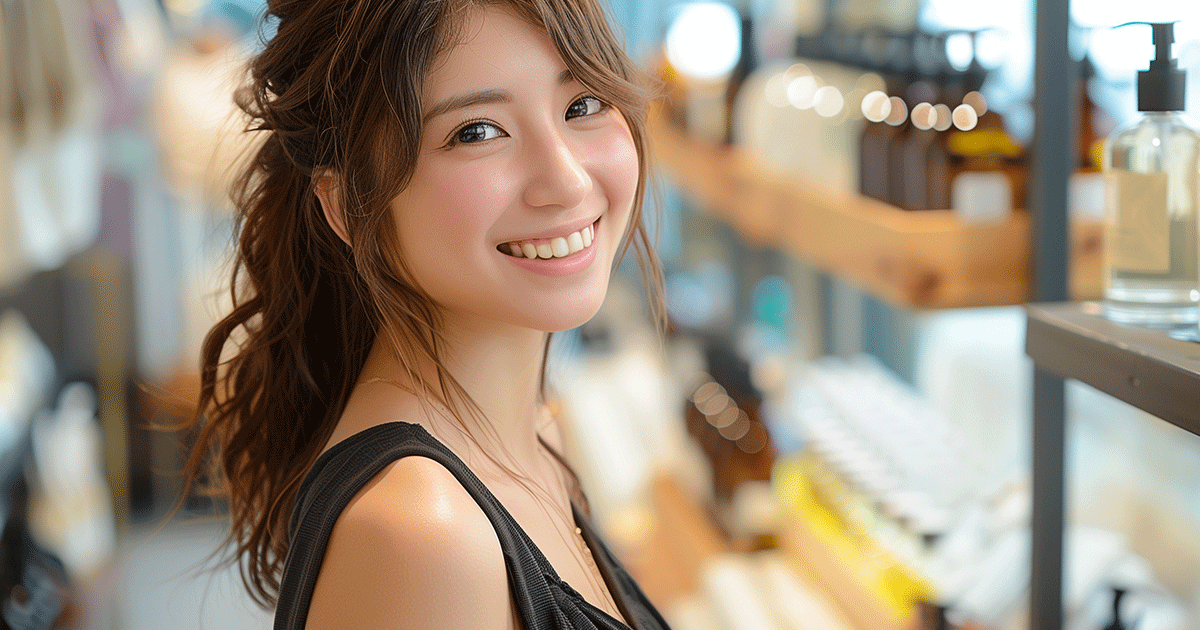















お礼
回答ありがとうございました。 詳しく説明していただきよくわかりました。 長文ありがとうございました。