元々は鳶職人「トビショクニン」と読みます。
このスタイルは太ももの所が尺五寸廻り。45センチの太さですので、ぶかぶかです。
最近の工事現場の仮設の足場は安全第一で女性の方でも安心して階段叉はエレベーターで上に上っていけます。
しかし昭和の初期。仮設の足場は杉丸太で組み上げていました。階段などはありません。その為、高さ1.7メールの高さにある飛び付きと言う丸太に片足を乗せ上げて体をねじ上げて1段目に上らないと上に上がっていけません。。
この仮設の足場を組み立てる専門職人さんが鳶職
つまり、高所作業専門の人です。
夏場汗だくで、スボンが肌にまとわりつけば、飛び付きと言う作業「最近は禁止です」の時、失敗して
落ちる事があります。
その為、鳶職のズボンは現代でもその頃の名残で
ぶかぶかでする
現代では、いろいろの服装があるようですね。
鉄骨造の鉄骨建方「現場組み立て」の作業の一番最初は鳶職人さんがされます。落下防止ネットの取り付けとか。
やはり。足をその辺の鉄骨等に絡まして作業されますので、肌にまとわりつくと、作業がしにくいと思います。最近は化繊ですし・・
ファッションでは無い様です。
25年ぐらい前、鳶職人の親方に会って雑談していた時。
当時70歳ぐらいでしたが。
鳶の制服は。
(1) 地下足袋、締め付けは強く
(2) フンドシは前締めの代端無し「あると引っかかって危険」
(3) かぶりのヤッケ・ボタン式の作業服は「前開きは丸太の番線締めの端に引っかかり危険」
(4) スボンは地下足袋の口に締め合わせて、太ももは
倍寸「自分の太さの倍」
(5) ベルトは2本「1本目は鳶道具を紐で吊して落とさないよう/2本目は命綱「最近は安全帯と言います」の引っかけ用」
(6) 落ちたら、死にます。仕事に命をかけている
証として
「根性の印」は「キモ玉とか入れ墨の事です」
花を入れない、桜とか菊は散るので落下。
縁起が悪いで緑の榊が多いそうです
(7) 気質の職「カタギノ人間」ですので、腕と前あき だけ。背中は汚さないそうです。
と言う様な事を聞きましたが
多分戦前の感覚だと当時私は思いました。
時代錯誤でスミマセン。
質問がチョット懐かしかったので。







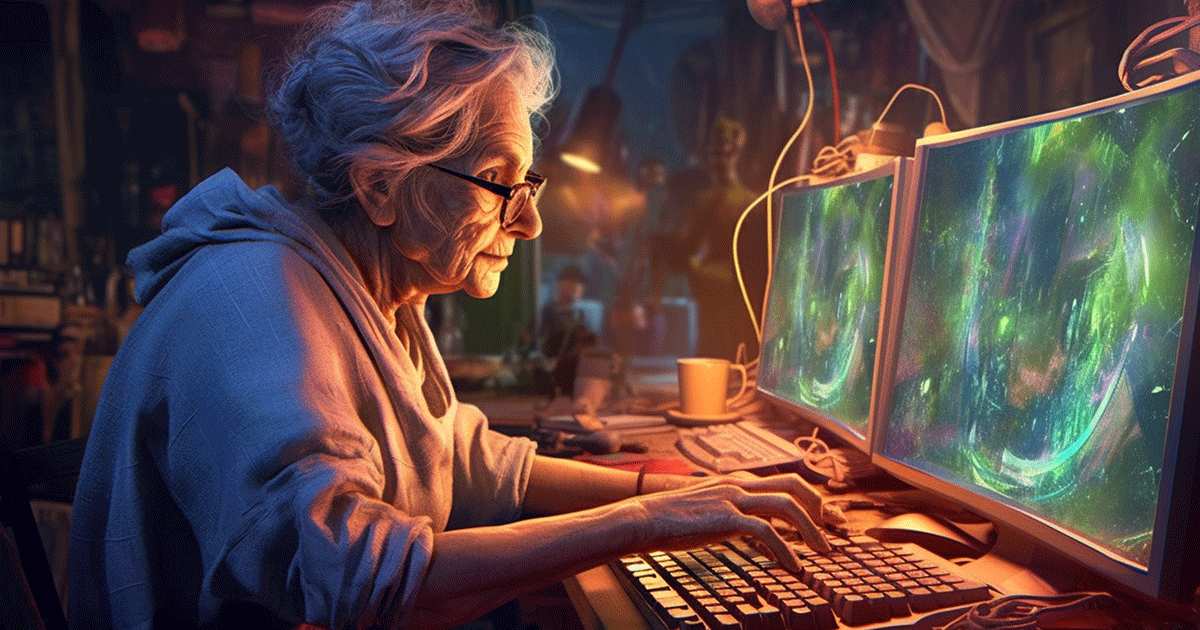
























お礼
ご回答ありがとうございます。 当時の経験者の貴重なお話をありがとうございます。 傍目には奇妙な格好もきちんとした理由があるのですね。普通のズボンだと確かに汗をかくと肌にまとわりついて動きにくいです。ヤの人でないのに刺青をするというのも初めて聞きましたよ。