- 締切済み
不正検知システムの業務フローについて
不正検知システムのおおまかな業務フローについて質問です。 (1)ECサイト ⇒ (2)決済代行 ⇒ (3)カード会社 上記のような会社関係があったとします。 (2)が不正検知システムを運用しており (1)に対する不正を検知した場合、どのようなフローで処理されるのでしょうか。 以下1~5のフローだと思うのですが、相違ないでしょうか。 1.(2)が不正検知システムにより不正(または不正の疑い)を検知。 2.(2)は(1)に検知結果を連絡。 3.(1)は(2)から受け取った結果の中から、不正だと判断した取引を(3)に確認依頼を出す。 4.(3)は本人に電話して確認し、その結果を(1)に通達する。 5.(1)は商品の発送を取り消す
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答




![その他([技術者向] コンピューター) イメージ](https://gazo.okwave.jp/okwave/spn/images/related_qa/c205_1_thumbnail_img_sm.png)

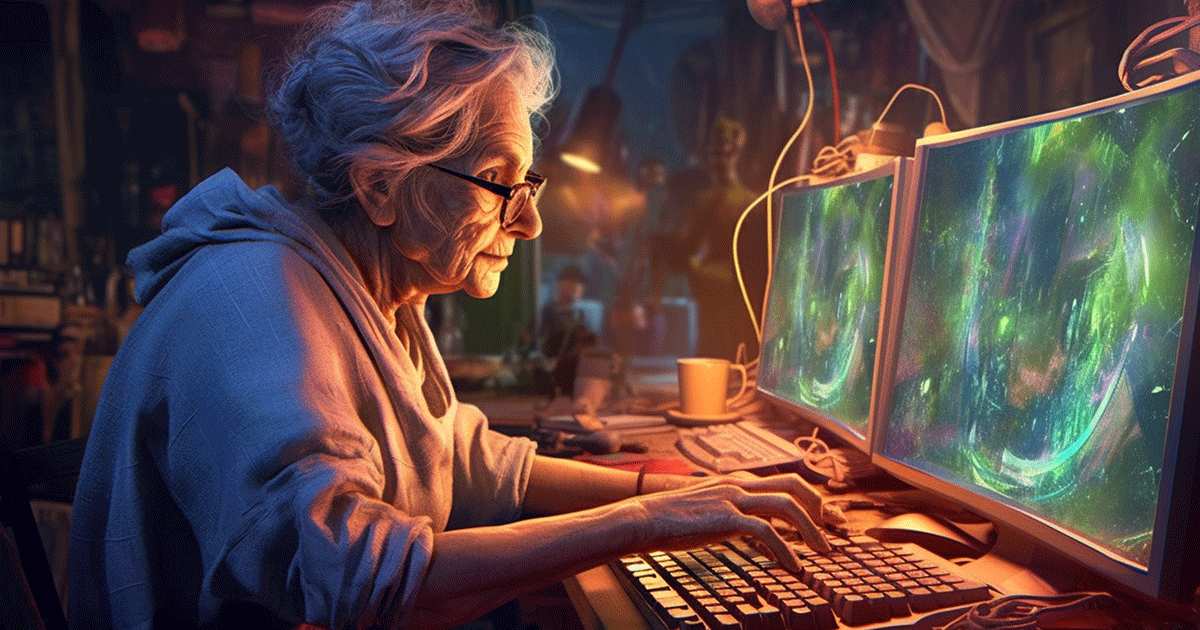



























補足
回答いただき、ありがとうございます。 だいぶ私からの情報が不足しておりました。 申し訳ありません。 ECサイトは amazonや楽天市場のようなショッピングモールではなく 独立系ECサイトを想定しておりました。 不正検知システムについては 決済のオーソリ通過後から、商品発送までの間に 取引内容を再度確認し、クレジットカードの不正利用(なりすまし)などを 検知するシステムで、EC業界では一般的に普及しているシステムになります。 (不正検知システムは、似たような呼び方が他にもいくつかあります) 決済代行会社は その名の通りですが、決済処理を代行している企業になります。 業界上位には以下のような企業があります。 ・ソフトバンクペイメント・サービス ・GMOペイメントゲートウェイ ・ウェルネット ・ベリトランス ・ペイジェント ちなみに 不正検知システムについては以下のようは製品があります。 ・O-PLUX(かっこ株式会社) ・FraundFinder(かっこ株式会社) ・eDefenders(イーディフェンダーズ(株)) >電子取引なんて毎日何千あるかわからないんですよ。 >それを不正検知システムなんかで監視する人間がいるわけありません。 クレジット不正利用によるチャージバックを回避するために 昔は人間が商品発送前に取引内容を確認しておりましたが 近年は何千ある取引システムによって検知するようになりました。 質問内容ですが この不正検知システムを利用するようになってから 決済を取り消すまでの不正検知業務フローは どうなったのかご存知でしたら教えて頂きたいです。