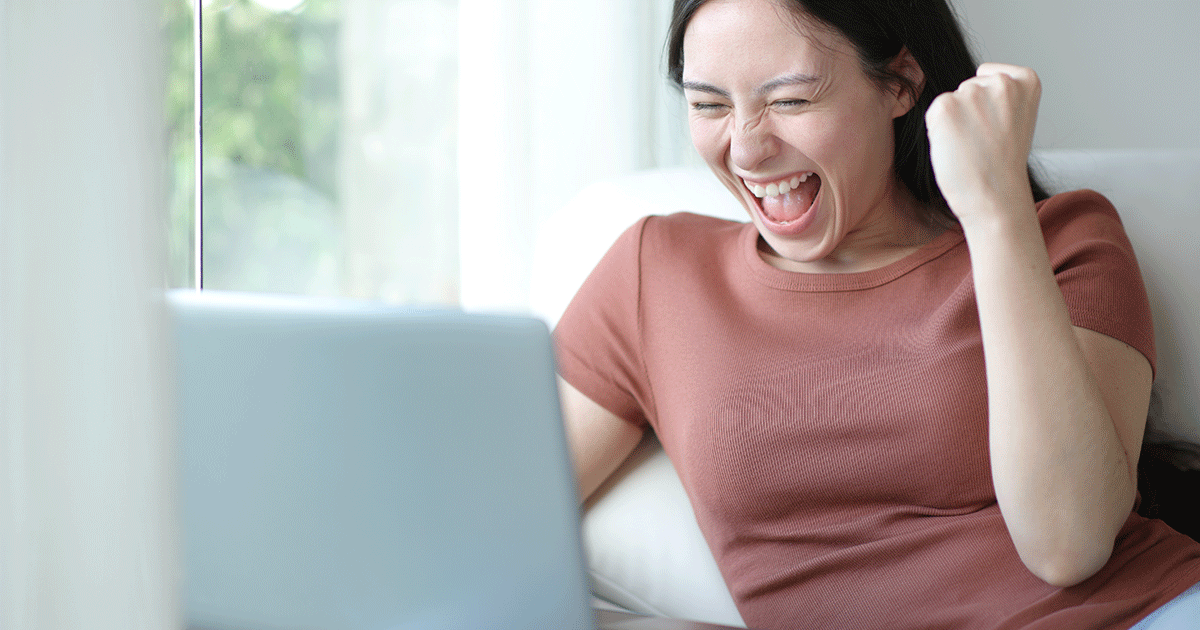私たち個人がインターネットにつなぐ場合、一部の例外を除いて、次のようにつながっています。
おうちのPC
|
モデム(ADSLでもアナログでも)
|
~電話回線~
|
NTTなどのキャリア
|
プロバイダのモデム
|
各種サーバー
|
~ネットワーク専用線~
|
他のネットワーク
また、サーバーには、
・メールサーバー(POP&SMTP)
・WEBサーバー(HTTP)
・ファイルサーバー(FTP)
・その他(NEWSサーバーなど)
があります。
そして、インターネットというのは「ネットワークとはネットワークをつないだもの」です。
さて、以上を踏まえて。
まず、「プロバイダ」ですが、2つの基本機能があります。
1)接続
PCからの通信信号を電話回線という原則アナログの信号を載せることを前提とした「電線」の上にモデムという機械をつかって、デジタル信号を効率よく運べるようにしてあげます。それがプロバイダのモデムにはいって、信号がデジタル信号として、プロバイダの持っているサーバーに運ばれます。
その後、PCが発した要求にしたがって、サーバーが処理を始めます。
2)ID
それが「メールを読んでね」だったら、メールサーバーが動き出して、メールをサーバーからPCに、さっきと逆に同じルートで送ってきます。
メールの場合は、個人を特定するためにメールアドレスがありますが、この「メールアドレス」とは外側から見たときの呼び方(正確には@よりも左は)であり、ただしくは「接続ID」ということができます。
さて、メールの場合、個人がサーバー上で特定できないと機能的に困りますからIDがありますが、WEB閲覧には、個人を特定する機能上の必要はありません。
そこで、「接続」があれば、WEBにはIDは必要ないということがいえます。
たとえば、ネットワーク対応マンションに住んでいると、インターネットへの接続は済んでいますから、メールアドレスを他にもっていれば(たとえばフリーの)、このマンション内でしか接続しないのならば、プロバイダ契約は不要、ということになります。
次に「レンタルサーバー」です。
通常、プロバイダは上記の「接続」「ID(メールアドレス)」の提供だけではなく、オプションサービスとして
・WEBスペース
・レンタルディスクスペース
などの提供もしています。
これらは言葉を変えると、
・HTTPサーバーの「領域の一部」を提供
・ファイルサーバ-の「領域の一部」を提供
ということができます。
レンタルサーバーは、これにくらべて「領域の一部」が大きくなっている、ということなのです。
場合によっては一部ではなく、サーバーマシン一台分を貸してくれることもありますし、2台、3台、ということもあります。
また、メールサーバーを貸しているところもありえますね。
以上、正確に、かつ、分かりやすく書こうとしたら、これだけの分量になってしまいました。
推敲に推敲をかさねて、もう少し要約すればいいのでしょうが、このまま書くことにしました。