最初に定義として述べておきますが、限月はラージは四半期限月だけの3月限、6月限、9月限、12月限、翌3月限の5限月制となっています。
ところがmini では、3月、6月、9月、12月(四半期限月)のうち直近2つの限月に加え、四半期限月以外の直近3限月(マンスリー限月)の取引を今年春に開始したので、5限月制となりました。
ここで期近、期先を実際の限月で表現すると、'11.9.21現在の期近は12月限、期先は(翌)3月限です。
但しこれはラージについての限月です。
miniは冒頭で記したマンスリー限月が導入されたため、'11.9.21現在設定されている限月は10月限、11月限、12月限、(翌)1月限、(翌)3月限の5限月です。
ということでminiについての期近は10月限、期先は11月限ということになります。
(マンスリー限月導入前はラージとminiの期近、期先は一致していました。)
さてここからminiの出来高についてですが、上記5限月の'11.9.20夜場(営業日としては'11.9.21になります)の出来高は10月限=19,431枚(70,230枚)、11月限=343枚(8,245枚)、12月限=128,311枚(472,280枚)、(翌)1月限=112枚(2,013枚)、(翌)3月限=1,246枚(3,752枚)となっています。
なお、()内は現在決済されずにホールドされている玉(建玉)の枚数です。
ご覧のようにminiでは期近でもなく期先でもなく12月限の出来高、建玉がダントツに多くなっています。
miniの12月限は期近でも期先でもないのですが、ラージでは期近限月で最も多く売買されている限月です。
従って
(1)ラージ期近に対応するmini限月は月によって期近でないこともある。
(2)現時点では期近ラージの価格にほぼ等しいminiの限月は期近ではなく12月限。。
よってminiの売買時に信頼できる参考価格を有しているminiの限月は期近でも期先でもなく12月限ということになる。
(3)また12月限の最終売買日までは3ヶ月近くあるが期近は1ヶ月、期先は2ヶ月と短く将来の変動を見越して建てておくには最終売買日までの期間が長い方が(予測が狂って保有せざるを得ない場合)有利といえそう。
(4)出来高が少ないと値が飛びやすくなるので取引上不利になる危険性がある。
ざっくりといえば上記(1)の理由に起因する(2)、(3)及び(4)により、miniの期近限月とラージの期近限月が一致する月はmini期近限月の出来高増加、それ以外は減少(といってもラージ期近限月に対応する限月が増加している)と出来高が大きく変動するのではないでしょうか。







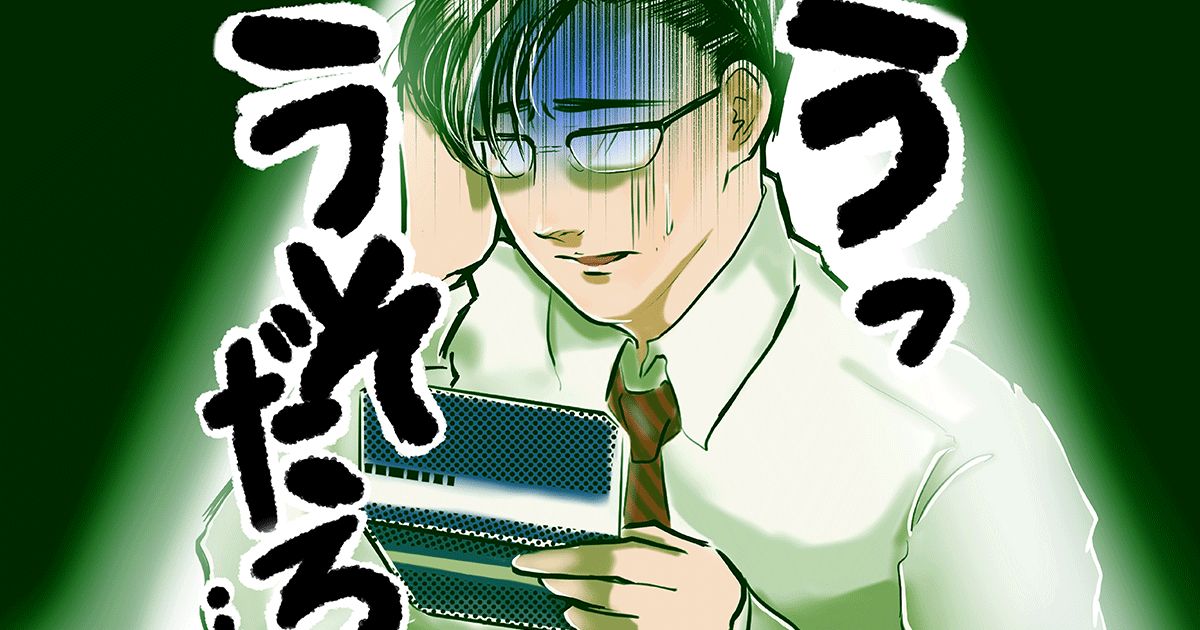














お礼
回答ありがとうございます。 私も他の限月を見て、出来高が違うのはラージの限月との関係があるのではないかと思っていました。しかし、これほど極端に違わなくてもいいのではないかと考えたのですが、出来高が多い方が、なにかと有利(便利)だということで、出来高の多い物に参加者が増えるということで、ますます出来高が多くなり、反面、少ないのは少なくなるということなんでしょうね。 データ処理のソフトを考えていましたので、回答を参考にさせていただきます。