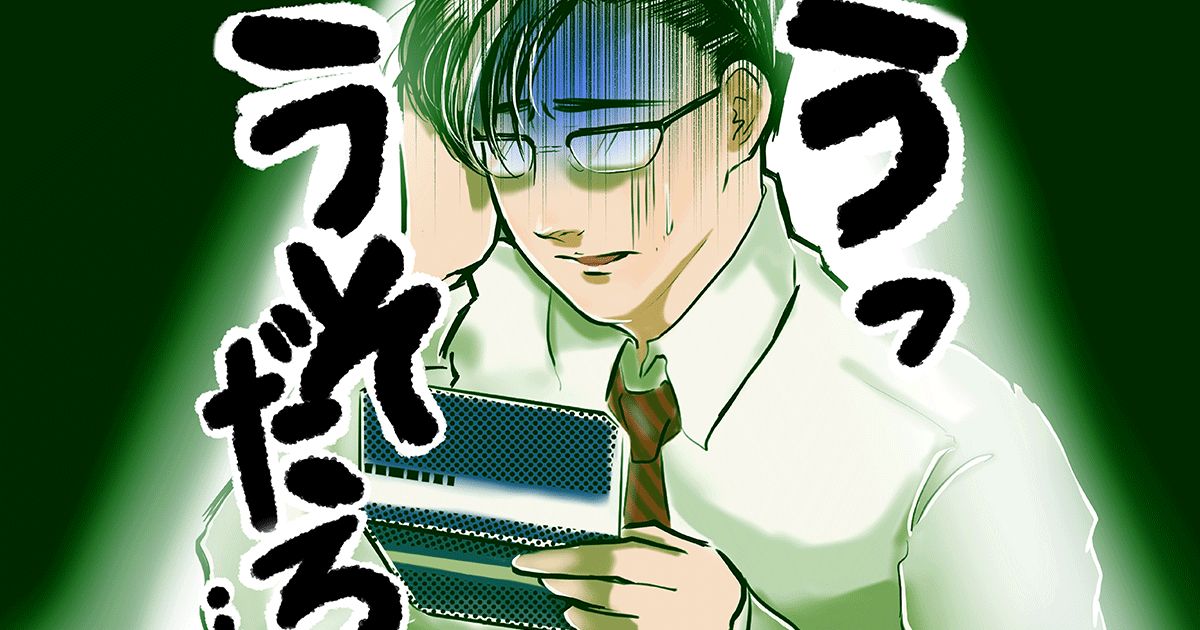金融数学の理解の仕方が今ひとつわかりません。
学校時代、数学がものすごく苦手でした。唯一まともにできたのは、三角形の合同証明くらいでした。
それに対して、語学や社会科学系は、社会の事象が具体的にイメージされるので頭が動くのです。どこかの中央銀行が金利を上げるというと、その中央銀行から流れ出る水道管のバルブが閉まり水が少なくなるから水の値段が高くなる、そして当該国内では水が貴重品になるので使わなくなり物価が安定するという感じで理解するのです。
いま、社会科学と数学の接点とも言うべき投資の世界に入るべく、数学を再び勉強しています。投資についてはドルコストでの毎月定額投資・分配金再投資、また金融商品の売買を行っていて年利8%くらいなのですが、より深く勉強したいと思い金融数学を勉強しています。
最近やっと、利息の複利計算や、その逆の一定利率を期間内に実現するためには一年間でどのくらいの収益が必要かといった、分数乗の考え方を理解することができました。超低レベルですが、この勉強が金融をより理解できるよすがとなると思うと、うれしくなります。
MBAをとったりするレベルではなく、ただ日常の投資効率を上げるための道楽のようなものなのですが、あえてそういう数学をマスターするにはどうすれば良いか、教えていただければうれしいです。