補足を読みましたが、前提とする論拠が質問者さんと私とでは全く違うんじゃないかなと思います。
BCPなんて確率的には低いことでも、予測していないと大事になるので予測のラインを高めにしておきましょうというだけの話でしょう。
下は社長が倒れるから上は全面核戦争までのトラブルを考えたとき、今までは政情不安定な国でクーデーターが起きる程度までを範囲内としてFAQを作っていたのを、もう少し上のライン、日本のような政情安定な国でもテロの可能性を考えるラインに持ち上げましょうということです。
例えば災害時の連絡を携帯電話で取るという前提にしているのは確かに計画倒れでかえって混乱するだけかもしれませんが、それなら携帯電話も通じないという前提での連絡の取り方を定めておけばよいだけですし。ある工場のラインが一時的にしか止まらないという前提で、一時的に他のラインに移すという計画しかないのなら、全損して復旧不可能な場合は他の工場のラインに振分けつつ新たなラインを作成するところまでを計画に入れておけばよいだけで、予測不可能な災害というレベルはそれこそ予測するだけ馬鹿らしいような全面核戦争や巨大隕石の落下というレベルの話ではないかと思うわけです。
国際競争力という観点で見た場合、要はトラブル発生時に迅速に復旧するだけの計画が無いとこと、あるところどちらが信頼されるか、また同じあるところでもその計画内容の質が良いところと低いところのどちらか信頼されるのかというだけの話で、予測範囲の狭いBCPという前提なら仰る通り国際競争力にも結びつきませんし、危機管理があるとも当然言えないとなるでしょうね。













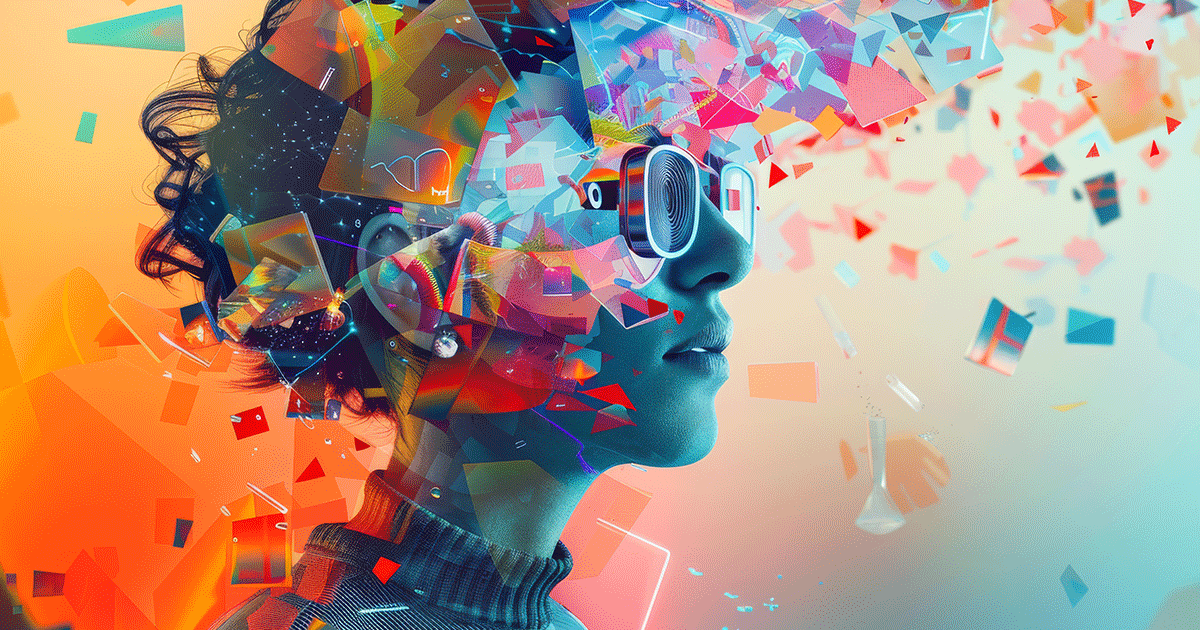




















補足
ありがとうございます。 おっしゃることは理解しました。BCPは危機管理事前想定および対策のレベルアップだというのは,極めて明快ですが,今,なぜこんな話が最先端の話題になるのでしょう。ITセキュリティがらみなら,話はかんたんでしょうが,国がそこに地震想定などををもちだすからややこしいのかも。 もちろん,9.11以降の世界的な危機管理体制強化がメインの理由かと思いますが,実際には個別企業は結構コストのかかる話ですし,何か裏の仕掛けがあるんじゃないかとも感じます。例えば,国際コンサル会社の次の営業戦略とか…。そういうことがわたしの中ですっきりしないのですが,何か情報をお持ちでしょうか? 後段の国際競争力については,株価収益率とかさまざまな企業価値指標があるわけで,BCPの存在などは,他がまったく同一条件だったときの小さな観点でしょうか。これも,どの程度の競争力指標なのかがはっきりしないのがもどかしいです。 自分の頭が整理できていません。いろいろ,飛んでしまってすみません。