1番様のご回答は正しいのですが、もう少し説明したいと勝手に思ってしまいました。
> 1.国民年金受給者は遺族年金がないと聞いていますが、その
> 理由はなぜなのでしょうか?
ご質問文では、誰が死んだのかが不明ですね。
[受給権者が死んだのか?受給権者の親族が死んだのか?]
それに、遺族と死亡した人との関係も不明確。
a 『国民年金の受給権者が死亡した場合』
この場合、国民年金第37条第1項第3号に該当し、保険料納付要件を具備していれば『支給要件』はクリア。
そして、同法第37条の2により、受給権を有する遺族は「子」または「子の有る妻」です。ここに出てくる「子」とは、同条第1項第2号により『18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって[国民年金法に定める]障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない者』となっております。「子の有る妻」とは、上記の「子」に該当する子供と生計を同じくしている者です。
ですので、国民年金の受給権者が死亡しても、条件に合っていれば遺族給付は行われます。
b 『死亡した者が国民年金の被保険者又は老齢基礎年金の受給者であり、残された遺族が国民年金の受給権者の場合』
この場合、国民年金第37条第1項第1号~第3号のいずれかに該当し、保険料納付要件を具備していれば『支給要件』はクリア。
しかし、受給権の有る遺族は上記aで書いたように「子」または「子の有る妻」なので、遺族がそれ以外の者のだけであれば、遺族基礎年金は支給されない。
又、遺族が妻であり、その受給する年金が遺族基礎年金であれば、妻は65歳以上なので子供は「子」の条件に該当しない事がありえる[妻が47歳以降に出産した子供か、特別養子制度で実子にした子供?]。
C 『死亡した者が厚生年金の被保険者又は老齢厚生年金の受給者であり、残された遺族が国民年金の受給権者の場合』
この場合、遺族基礎年に関してはbに書いた内容と同じ。
遺族厚生年金に関しては、
・妻は年齢や子供の有無に関係なく受給権者となる
・子供は「子」の条件に該当し、母親(死亡した者の妻)が受給権者では無い場合には受給できる。
・夫が遺族の場合には、妻死亡時の夫の年齢が55歳以上であれば受給権者になれるが、上位の受給権者が居た場合には受給権は消滅する。
・父母、孫、祖父母も受給権者になれるが、夫々、年齢条件と上位の受給権者の存在の有無で結果が変わる。
と言う事で、お聞きになられたことは間違いです。
> 2.遺族年金は全額非課税のようですが、その理由はなぜなので
> しょうか?
例えば、現在の遺族基礎年金。
これは、旧国民年金法(昭和61年3月31日まで適用)の「母子年金」「準母子年金」「遺児年金」を引き継いだ物です。夫に先立たれ母子・準母子家庭や孤児となった者の生活支える為の給付であり、当時の女性は社会進出が難しかった事もあり、非課税が相当と考えられた。
遺族厚生年金も同様ですね。










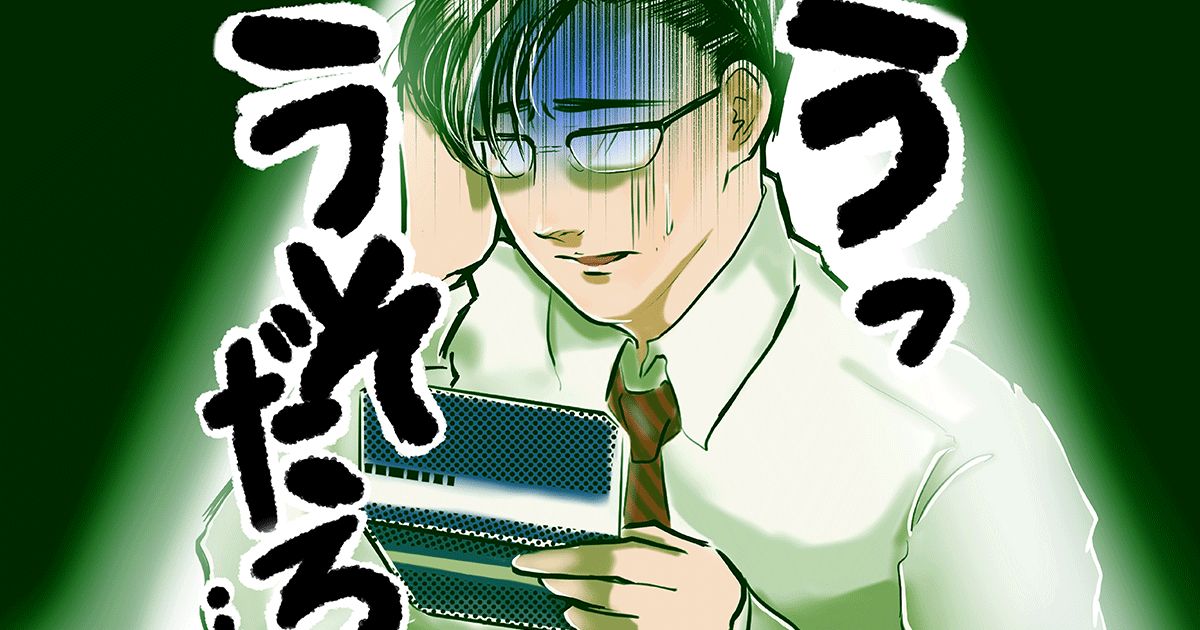

















お礼
詳細にわたる回答ありがとうございました。一定の要件を満たせば 遺族年金は支給されるケースがあることを理解いたしました。 認識を改めます。