>追加の質問なのですが、局方品があるのに局法品でないものを使う理由はあるのでしょうか?
>また、政府で定められたものと、定められていないものはどんな違いがあるのですか?
添加物は薬効の無い部分であり、薬効を妨げず安全が確認されている薬品ならば何であろうと添加物として使うことになんら問題は無いので、メーカーが(コスト含め)使いたい薬品を使っているのが現状です。
局方品という名称は政府の定義を1つでも外れると名称を付けられません。
本来、薬局方は基本的に医薬品を記載しているため、薬効の無い添加物は記載されません。
添加物で局方品がある物は、ほとんどが古い時代には医薬品として使われていたために記載されたにすぎないものが多いです。
特に製法や試験法などで古典的で非効率な定義がなされている場合は効率的な製造をされて安価な物が定義から外れてしまうこともままあります。
また、近代になって開発された添加物などは薬局方に基本的に記載されていません。
コストだけでなく、例えば服用回数を減らすために薬を徐々に放出するために加える添加物や、胃ではなく腸で溶かすための添加物なども大部分が局方品ではないでしょう。
結論としては、局方品であるか無いかの違いは、その薬品が政府の発行した本に載っている定義に当てはまるか、そうでないか。だけです。どちらが良いも悪いもありません。
あ、もちろん薬効を発揮する主薬は局方品のものが定義から外れちゃダメですよ。





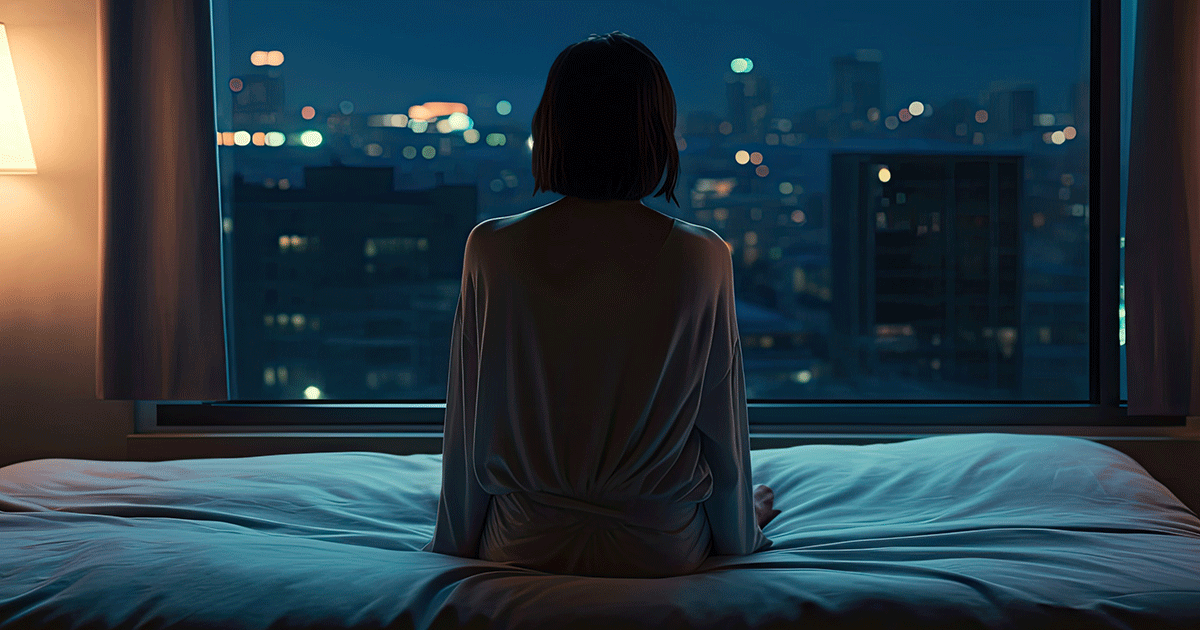























お礼
とても良くわかりました。ご丁寧にありがとうございました。