声は糸電話と同じですよ。声が、コップの裏の薄紙を振動させて、その振動が糸を伝わって、向こうの薄紙を振動させ、コップで拡声されて聞こえます。
でも、糸だとそう長くは離せませんので、弱い電気を流した銅線に変えます。ラジオとスピーカーがビニルに皮膜された金属の線で繋がって音が伝わるのと同じです。でもラジオをスピーカを繋ぐ線の様に細いと遠く話した場合音がすぐ小さくなってしまいますので、線(銅線)を太くします。それでも小さくなってしまう場合は途中に増幅装置をかまします。昔の電話の海底ケーブルに数km毎についているもっこりしたものがそうです。ただ、増幅すると、雑音もいっしょに増幅されますから、増幅を重ねると音が悪くなります。昔の国際電話が、音が悪かったのはこのためです。
で、20年くらい前から、伝送路のディジタル化が始まります。金属線を伝わるアナログの音声信号をデジタルに変えて遠くまで運んでからまたアナログに戻します。スタジオで録音したCDを自宅で再生するのと同じです。元の音はアナログですが、デジタル化された後は、劣化や減衰(音が小さくなること)なしに自宅まで運ばれ、CDプレーヤーでアナログの音に戻されます。そのデジタル化された信号はさらに多重化され伝送効率が上がります。1回の宅急便でCDを24個一度に送るようなものです。
デジタル伝送路は光ケーブル(髪の毛1本の太さで、圧縮なしで24通話を同時に伝送が基本)が主ですが、架設にコストがかかる場合はマイクロ波も使います。
最寄の電話局同士はディジタル網で階層的に繋がっています。那覇市の局から沖縄の地方局、西日本統括局、東日本統括局、北海道地方局、札幌中央区の局って感じです。
もうひとつ、「電話したい人が居るってことを知らせる信号のやり取り」が通話の前にあります。発信局では、掛けたいと受話器を取った電話の電話番号が解りますから、その電話でダイヤルされた電話番号に対応する電話機まで1つの通話路を作りつつ、電話が来たよって信号も伝えます。これが北海道の電話機にまで伝わると電話が鳴り、受話器を上げることで通話路がひとつ完成しお話が出来ます。

















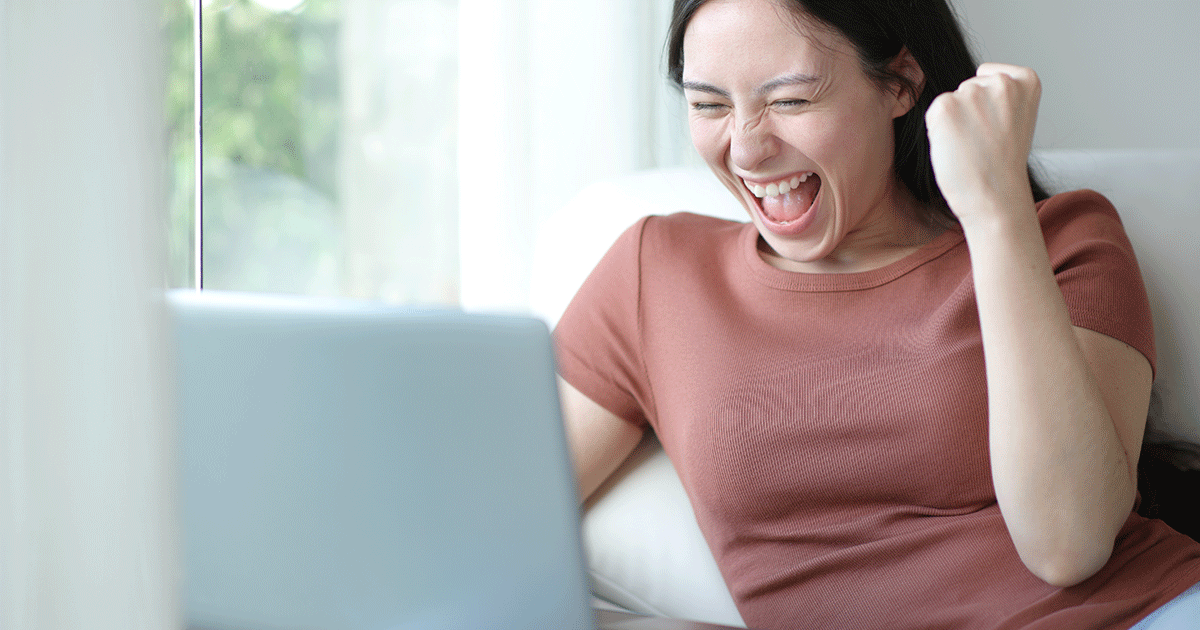



















お礼
この絵が理想とするものです。 ありがとうございます。