ちょっと話しが難しくなってしまったらごめんなさい。
まず、実際の血管には血が流れていますが、赤血球、白血球、血小板などが含まれています。その中の血小板というものは血液を固まらせる役割をもっています。(怪我したときに血が止まるのを想像してください)。なので、採血して試験管などに血液を入れると固まって実験どころの騒ぎではありませんよね。
じゃあなぜプレパラートを流れるのか…。
採血時にヘパリンを添加して血液が固まらないようにしてるんです。
つまり、あの実験で用いている血液はコレステロールが高かろうが血糖が高かろうが全員「サラサラ」なんですよ。
また、白血球は赤血球に比べ数が少なすぎるので観察できませんし、あのモニターに映っているのは殆どが赤血球なんですね。
流れやすかったり流れにくかったりしているのは「赤血球の変形能力」の差であって血液の粘度やコレステロール、中性脂肪とはなんら関係がありません。
よってあの実験で「流れが悪い=ドロドロ、不健康」という表現があるものはすべてインチキです。
ちなみにコレステロールや中性脂肪が高い状態が長年続くと血管壁に蓄積し、血管が詰まり易くなります。それが脳で起これば脳梗塞。心臓で起これば心筋梗塞です。これは医学的に証明されています。
コレステロールや中性脂肪が高い状態が長年続いたから100%脳梗塞になるわけではありませんが、危険度を減らすために基準値があり適正な数値を保つような生活をした方が病気のリスクも減らせる。だから治療するんです。
誰が強制するものでもありませんので自分が脳梗塞や心筋梗塞になってもいい、あるいはならない自信があるなら数値が高くてもほっておけばよいのです。しかし、それによっていざ治療となった時に医療費がかかるので、発症前に予防しましょうね。というのが国の考え方です。
※表現をわかりやすくするためあえて「サラサラ、ドロドロ」という表現を使いましたが医学的にそのような概念はありません。




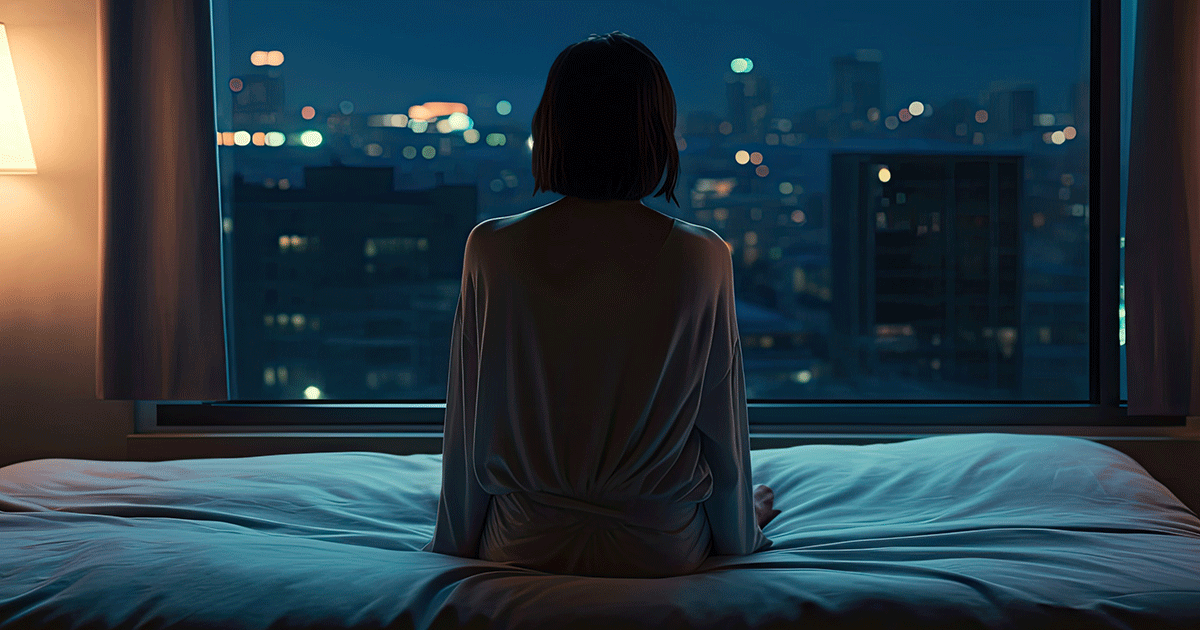




















お礼
今までずっと疑問に思っていたことが、完全に解消しました。 今日は、すっきり寝られそうです。 本当にありがとうございました。