回答遅くなりすみません。
結論から申し上げますが、残念ながらぼくにはわかりませんでした。
> 財務省の国債関係諸資料の過去の入札結果というところのデータを使っています。
こちら、ぼくもダウンロードしてみましたが、新発債の入札結果しか出てませんでした。
機関投資家が新発債に入札するならブローカー不要ですから手数料は要らない筈です。
ビッドアスクスプレッドという概念も発生しません。この概念は多数の売り手又は買い手が存在する市場に於いてしか成立しません。新発債の売り手は国しかいません。
また新発債の入札結果を見てもそれが1週間後に流通市場でいくらで決済できるのかということが特定できないんじゃないでしょうか。
するとシミュレーション自体に意味がなくなるのではないかと思えたのですが。
ただ過去データから1週間先の利回りなどを予測しているとのことなので、何か、ぼくのダウンロードしたデータがおかしかったか、別な見方があるのか。ちょっと知恵足らずでした。
債券に詳しくないので認識に誤りがあるかもしれません。
流通債券市場に詳しくないのに口を出してしまいましたので、知識不足に起因するのでしたら是非識者の方のフォローなりご叱責なりいただければと思います。
運用方法についてですが、1週間に一度売買するという前提はどうかなーと思います。
あくまでシミュレーションで研究目的なら、売買コストは寧ろ考慮しない方がいいんじゃないですか?
売買コストというのは金利と無関係の確定コストです。
1週間に1度売買すると仮に月に4回、年に48回として、金利と無関係の48回分の売買コストを考慮しなければいけません。
コストが仮に0.01%でも年に48回取引すると0.48%が確定コストです。
月に1回の売買ということにした場合には確定コストは年0.12%です。
売買回数が理論値の正当性に影響するという時点で何か違うような気がするんですが。
全体像がよくわかってないのでただの気のせいかもしれません。
> 残存期間とビッドオファーの積が取引手数料なのでは?
うーん。
全然わかりません・・・・すみません。
ビッドオファーは理論値として出て来るもんじゃないですから、何か根本的に違うような気はします。
流動性が無かったりすると約定するしないに関わらず100ベーシスポイント乖離してることだってあり得るわけですし。










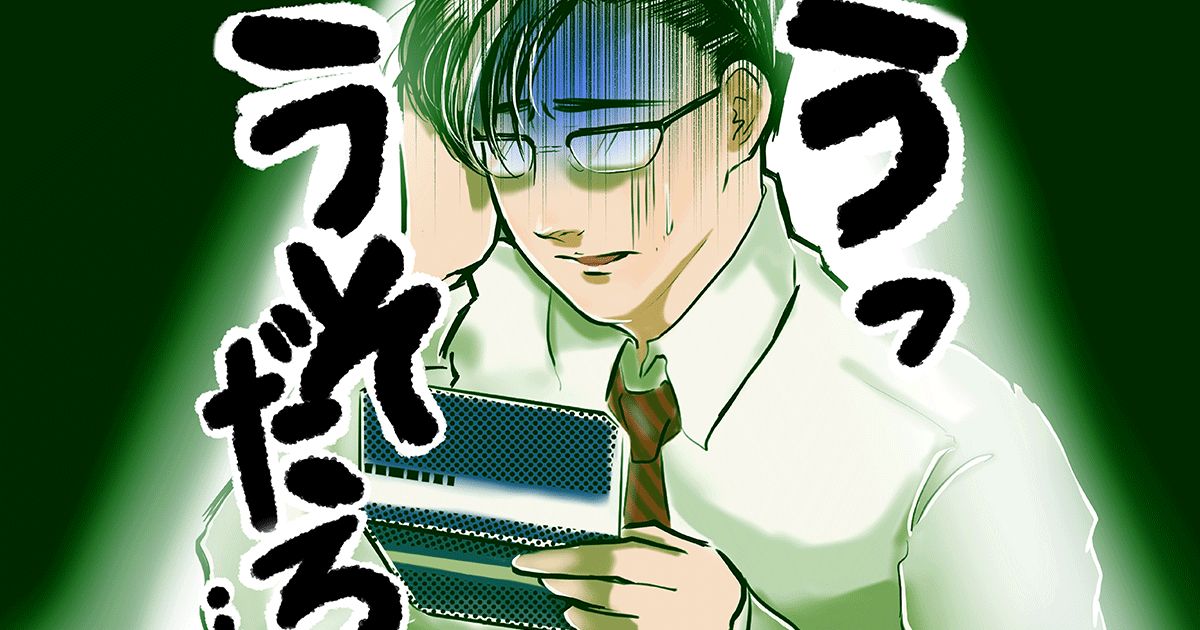




















お礼
ありがとうございました。追加いたします。 割引債の残存期間ですので、残存期間=デュレーションが成り立つと思います。なので、それをリスクと捉えることによって、残存期間とビッドオファーの積が取引手数料なのでは?と考えたのです。
補足
丁寧に解答していただきありがとうございます。 では、補足させていただきます。 どこからデータを持ってきたものかと言うと、財務省の国債関係諸資料の過去の入札結果というところのデータを使っています。 運用方法を説明する前に研究内容の説明からさせていただきます。 すでに過去のでーたから、現時点から1週間先の利回り(各残存期間の利回り)を予測したのですが、これに正当性があるかを実際に手数料を考えた時にどうなるか?を調べたいのです。(1週間の他に1日、2日、3日、4日先の利回りも予測済み) 運用方法は以下の通りです。二つの残存期間の債券を金額を同じにしてロングとショートをします。1週間後にまた同じようにロングとショートをします。それを永遠と続けていきます。 なので取引回数とリターンのトレードオフを調べる必要があるわけです。 ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 また、なにか説明不足な点がございましたら指摘していただけたら幸いです。