そりゃ一言でいえば、「持久力がつく」ということでしょうね。例えば100m走で持久力はほとんど必要ないでしょうが、「1日30レースやる」なんてことであれば、30レースこなせるだけのある程度の持久力は求められます。野球はピッチャーを除けば基本的に瞬発力が重要なスポーツですが、1日2試合するならそのぶんのスタミナは求められますし、プロ野球選手ともなれば1年のシーズンをこなせるだけの体力が求められます。プロ野球選手でも線の細い選手は夏場になると成績が落ちる人がいますよね。
結局のところ質問者さんがどれだけ持久力が求められる環境にあるかが重要でしょうね。「一日中立ってても疲れない」というのは主に求められるのは持久力です。短距離走の選手で、大会に出るのは年間数えられる程度、なんてのであれば持久力を持つメリットはほとんどありません。
有酸素運動と無酸素運動の比較でよく例に出されるのが、白身魚と赤身魚ですよね。ヒラメやタイのような近海魚は敵から逃げるために一瞬の瞬発力は求められますが長い距離を泳ぐ必要はないので白身、つまり無酸素運動優位です。
カツオやマグロなどは外洋を泳いでいるわけですから、スタミナ勝負です。だから赤身、つまり有酸素運動優位です。
ついでにいえば、人間は元々DNAレベルで「有酸素運動優位」「無酸素運動優位」が決まっています。もし質問者さんが「短距離走は極めて得意だけどマラソンが超苦手」であれば、元々有酸素運動の素養はあまり持ち合わせていないことになります。しかし、競技や日常生活でスタミナが求められるのであれば「そうはいってられない」というのもあると思います。






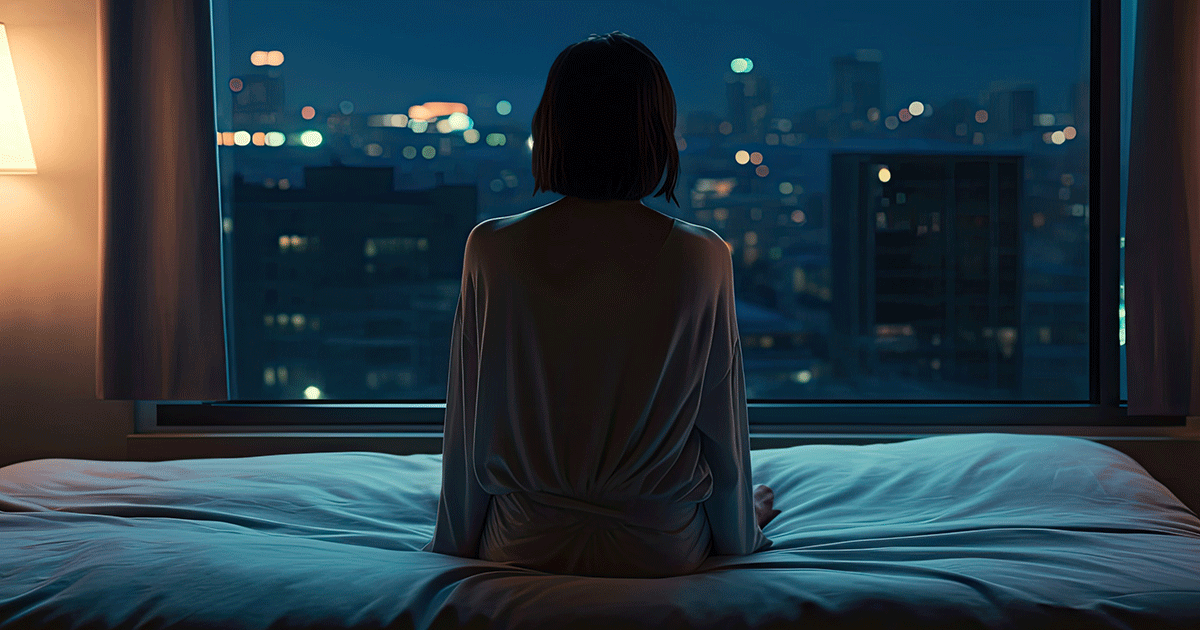




















お礼
ご回答ありがとうございます。 DNAレベルで優位性が決まっているとは、初耳でした。昔は走り方を理解していないまま走っていたので、今タイムを計ってみないとはっきりした優位性は分かりませんが…是非知りたいところです。 持久力はあらゆる面で必要となるので、最低限は確保しておきたいところです。というわけで最低2km、気分がのれば5kmぐらい走ろうと思います。