※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特性要因図の重要要因選定)
特性要因図の重要要因選定
このQ&Aのポイント
特性要因図を使って問題解決をする際に、重要な要因を選ぶ方法について知りたいです。
特性要因図には多くの要因があるため、その中から重要な要因を選ぶことは難しいです。どのような基準で重要要因を選ぶべきか教えてください。
特性要因図を活用したい場合、重要な要因を選ぶ方法を知りたいです。重要要因の選定にあたって参考になる情報源やツールがあれば教えてください。
ある問題に対して特性要因図を書いて、要因をたくさん出したとします(いわゆる孫骨が100個くらい)。
その中から重要要因を選ぶという行為が続くと思うのですが、その重要要因(例えば4~5個)は、どのように選び出せば良いのでしょうか。
確率的には4(or 5)/100 となると思うのですが、ひとつひとつ検証して選ぶとはとても思えません。逆に、ある程度絞れているのであれば、そもそも特性要因図自体が必要ないものになってしまうと思うのです。
いろいろな本やサイトを調べましたが、例は「まるで最初から決まっていた」という感じの解説ばかりで役に立ちません。『それぞれの参加者が重要だと思うものに○をつける』等と書いてありますが、その各自の判断基準を全ての孫骨(100個くらい)に当てはめて考えるのでしょうか。
いわゆる、「発表会向け」のこじつけ資料であれば重要要因をあらかじめ出しておいて、後付けで不要な骨を付けるという事になってしまうのでしょうが、本当に活用したいと考えている場合はどうすれば良いのでしょうか。




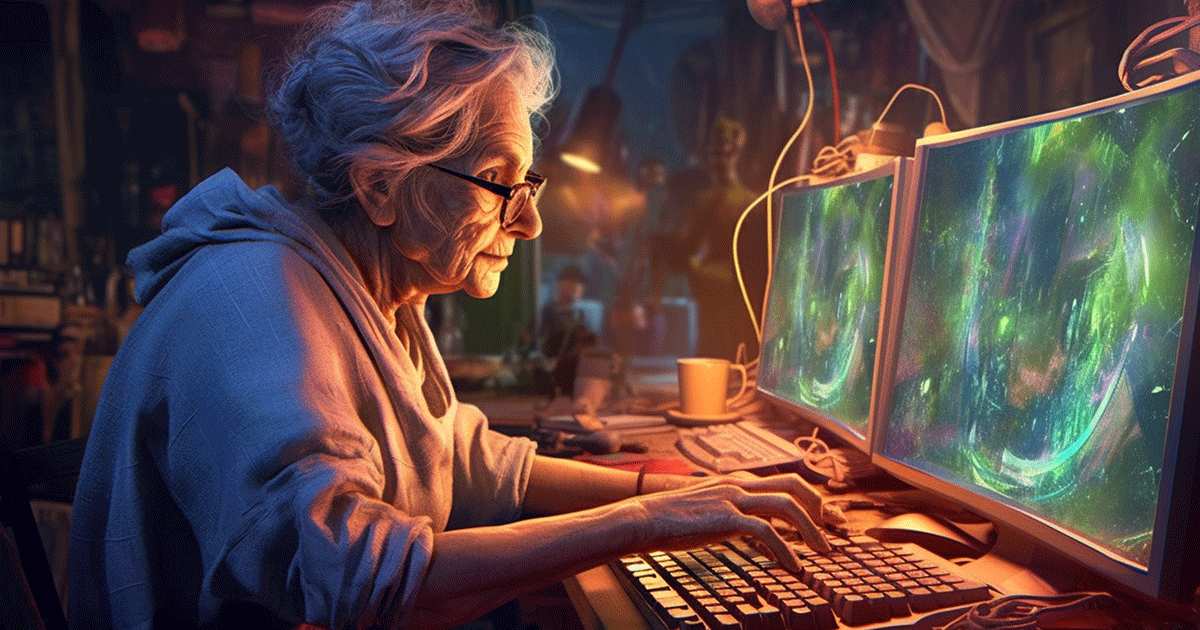


























補足
ありがとうございます。 > ●重み付けです。 > たとえば、多数決のようにね。アンケート方式が多いのではないかと思います。 評価の尺度が統一されているのであればアンケートや挙手方式でうまく行くと思います。 でも、価値観の違い(?)と言うのですか、そういったものがある以上、意見が収束せずに発散してしまうことが多いのです。 (グループの意思統一が図れていないのが問題だ!と言われてしまうかもしれませんが・・・) 特性要因図は使わない(使えない?)方向で進めた方が、メンバーにとって良いんでしょうかね。 日本科学技術連盟さんに教えて欲しいものです。