近年では神経(歯髄)をできるだけ残す方針が主流になっています。
しかし、歯髄は削る際の刺激や金属などによる熱伝導率で炎症を起こしやすくなっています。
僅かな刺激と若干のしみる痛み(冷水痛)であれば、暫くの間、あまり温度差のあるの物を避けて様子を見ます。
痛みの出ない程度の刺激が歯髄に加わると、歯髄は自ら「二次象牙質」を造り、外部との距離を保って刺激を避けようとします。これにより歯髄は健康なまま保存されます。
ただ、この反応には患者さん自身の自己治癒力の差が大きく影響し、理想通りに経過する場合と、なかなか二次象牙質形成が進まない場合、予後不良では歯髄が死んでしまう「歯髄壊死」という経過があります。
従来の歯科治療では歯髄温存の体制が整っておらず、医科では当然行なわれていた「予後観察」という治療評価が歯科では完成していませんでした。(大学では習うのですが)
処置を行なった歯を予後観察するのは当然であり、そこには必ず「予後不良」という評価もあります。
従って、予後不良は必ずしも歯医者の腕とは関係ありません。
そして予後不良であれば、残念ながら抜髄をしなければなりません。
ただし、冠セット後2年以内は冠の費用だけ(他の処置を除く)は歯医者の負担になります。
歯髄温存の成功率は状況にもよりますが、患者さんの年齢と共に低くなっていくのは事実です。しかし高齢での成功例もあり、逆に若くても歯髄死に至る例も多くあります。
また歯髄死に至っても安定する(感染して膿まない)場合もあるので、「歯髄を取るべきか残すべきか」、「自分の歯をどこまで残すか」などの線引きは非常に難しい問題です。
従って、予後不良の際の治療方針は主治医に委ねるしかありません。
ちなみに現在でも、予後不良は歯医者の未熟と決め付けている人が居ますが、これは古く誤った常識で考えている事に由来します。
また、国が義務付けた「2年間保証」制度も、この古く誤った常識に基づいています。
最近は、この2年保証制度によって、逆に保存可能でも抜髄や抜歯をしてしまう歯医者も増えつつあります。




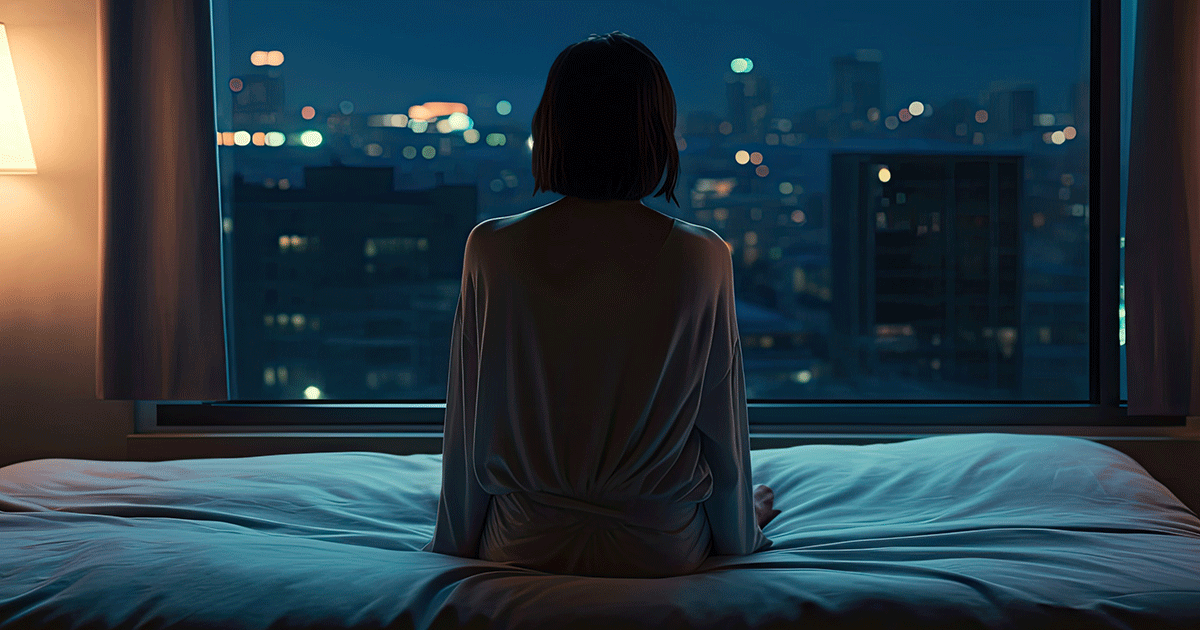


















お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 michael-mさんのアドバイス通り、冷たいものを避けて様子を見てみます。 そこで質問なのですが、二次象牙質を造ることができれば、痛みはなくなるのでしょうか? そして、どれくらいの間様子を見ればいいのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ございません。