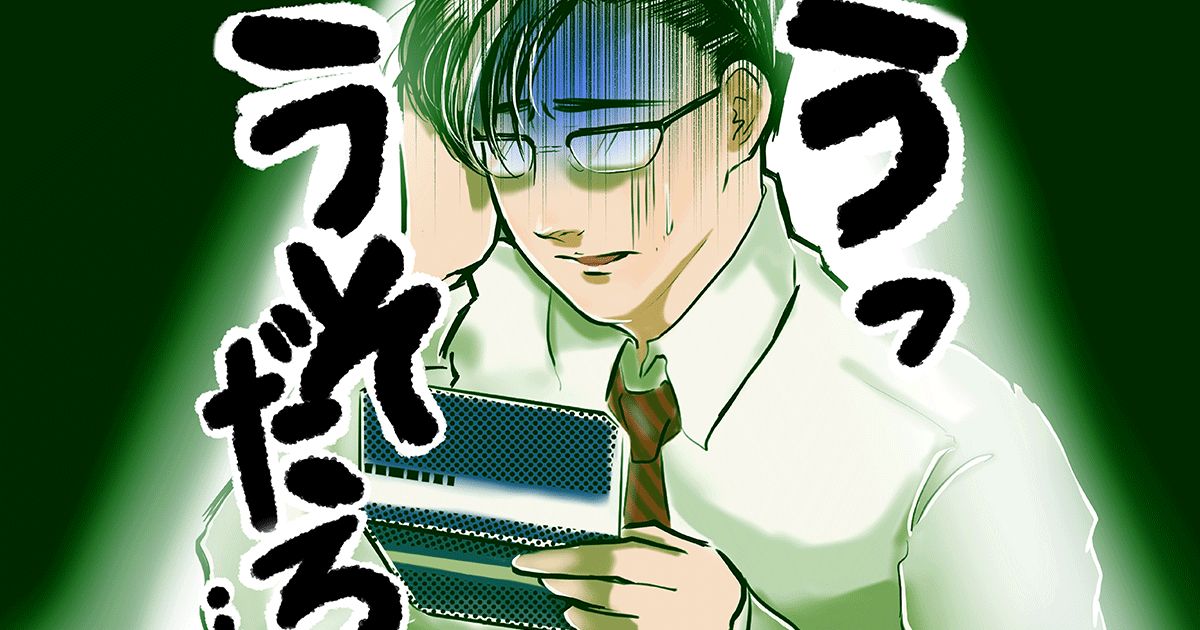- 締切済み
保険の選び方のポイントは?
うまく検索する事が出来なかったので投稿させて頂きます。 保険会社の選び方のポイントを教えてください。 今入ってる保険は第一生命です。 主人と私を合わせて10000円弱。 子供の学資保険を合わせると24000程度掛かっています。 現在同居で、来年の春から家を出る事を決めていますので、正直 この金額を払うのは無理です。 担当の方にお話したら、あまり金額を下げたくないような事を言われてしまいました。 確かに、保障は大事です。でも生活が成り立たなくては意味が無いと思います。 現在主人は22歳。特に大きな病歴もありません。 入社して4年経ちますが給料は月20万程度です。 子供は9ヶ月です。 ネットで出来る見積もり?とかもしてみましたがイマイチ組み立て方が解らず・・・ この場合、どういった感じにポイントを置いて保険を選べば良いのでしょうか? あと、お勧めの保険などありましたら参考までに教えてくださると助かります。