泌尿器科専門医として回答します。
嚢胞性腎腫瘤の発生頻度は高く50歳以上の剖検(死後の解剖確認)で50%以上みられる…そういう意味でポピュラーな疾患です。しかし良性と判断していいのは『すべての腎腫瘤性病変を否定した上』でのことであり、単純に考えていいものではありません。(主治医として管理下の元に患者さんに伝える言葉と学問的な扱い、本来の意義は等価ではありません。)
通常ポリープというと上皮細胞の実質性腫瘤でかつ悪性でないものを意味しますね。腎のう胞は肝のう胞と同じく『のう胞』という腫瘤で、まったく同じではありません。が、良性腫瘤という意味で同じ範疇に入れることがあります。
腎のう胞は腎臓の皮質に発生し、内容液は1)リンパ性の液体であることがほとんどですが、2)血性のものや3)石灰化を伴うものもあります。1)は問題がないといえますが、2)は悪性腫瘍の可能性(稀にのう胞壁に腫瘍を発生することがある)を否定できず3)に至っては腎癌に特徴的とされる所見にあたります。
問題なのは腎のう胞の場合、画像でしか鑑別は行われないこと、のう胞穿刺をしたとしても細胞診までしかできないことです。普通のポリープは組織を採取して診断する(=これを病理学的診断といい最終診断になりえます)のですが腎のう胞にはコレが許されないこと、またすることによる負担が大きいとされて選択ができないことがあげられます。つまり経過観察によって継続的に悪性の有無を判断していかなければならないということがいえるのです。また肝のう胞と比べれば数%といえども悪性腫瘍の合併例が確認されていること、またのう胞性腎癌という特殊なタイプが存在することから『一般化したお話がしにくい』ところがあるのです。
良性の腎のう胞を悪性と誤ることは現在の泌尿器科診断ではありえないと思いますが、上記悪性の兆候を認めた場合には画像のみで判断することは出来ないために拡大して切除することがあります。これを持って『誤り』とすることには医療者側からの反論は避けられないでしょう。
こうした単純性のう胞(単純性といっても必ずしも単数とは限りません)とはべつに多のう胞腎という病気があります。また多房性腎のう胞というものも今回の話題ではないと思いますので割愛します。
ここまで踏まえた上で、ご質問に答えていきますね。
単純性腎のう胞と診断された上で悪性腫瘍が合併していると判断されるのはコンマ数%です。しかし元々の母集団の大きさを思い出して下さいね。
さらに一応の診断で単純性のう胞とされていてもあくまでも確定診断とはいえない(医学的には病理診断以外での確定診断はありえない)ことを記憶していて下さい。
またのう胞性腎腫瘍の頻度は腎癌全体の数%から10%程度あります。
結論
確定診断し得ない腎のう胞性腫瘤はあくまでも仮診断であると心得よ。
以上です。





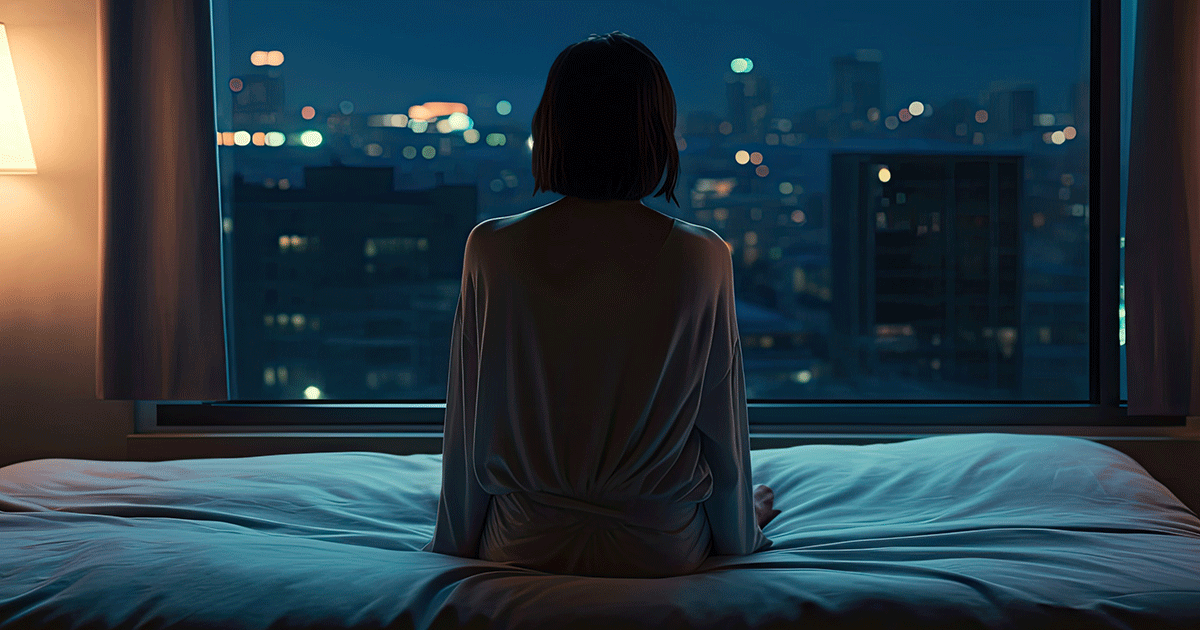


















補足
〉多房性腎のう胞というものも今回の話題ではないと思いますので割愛します。 多房性腎のう胞は腎のう胞と比べ危険性が違うのですか? 申し訳ありませんが、多房性腎のう胞についてもコメントいただきたいです。 よろしくお願いします。。