風邪(感冒)は身体の免疫機能が、疲労などが原因となって低下した(平衡を失った)ときに様々な細菌に犯されるものです。インフルエンザウィルスのように特定のビールスや細菌に感染するものとは全く違います。いわば身体の防御機能が低下したとき、普段は相手にしていない弱い敵に攻め込まれた状態です。ですから敵は雑多にいろいろあり、また感染過程で変異するので特定が難しく(した頃には治っていたり)、無数にある風邪の原因菌やその候補に効く(菌を殺すという意味)薬というのは厳密な意味では開発は不可能に近いのです。
風邪は体内への菌の進入で免疫機能が緊急発動して白血球などがんばるので、外界と接する「外堀」にあたる鼻腔や咽喉などの粘膜や体内の胃腸内壁に様々な炎症が起こり、体内では発熱などの全身症状が起こるのです。
しかし、風邪の菌というのは直接防げませんが、「風邪にかかる」過程、つまり感染の機序が分かってきています。その途中を阻害する薬が今開発されつつあり、また、身体の平衡が損なわれ、風邪にかかりやすくなる状態を簡単に見分けるマーカーも研究されています。つまり壊れかけた堀を直す方法や守りの弱ったことを知らせる見張りを作ろうとしているのです。それでもたぶん将来も風邪の根絶は難しいでしょうが、相当かかりにくくする方法は予防と初期治療のシステムとして確立されると思います。最も今でも過労と睡眠不足、過度なストレスを回避し、心身を健康に保つ努力をすることはつまりはそのシステムというわけです。
もう一つ、症状を緩和させると、かえって治療の逆効果ではという懸念ですが、たぶん発熱による発汗が解熱効果があるので、発熱を抑える消炎剤などが結果的に回復を遅らせることになることなどをいわれているのでしょうが、発汗による解熱で症状の進行が遅れたり改善するのはまだ回復の体力が十分にある感染初期のうちだけです。発熱も続けば体力を奪い、熱発による二次的な障害を体内のあちこちに生みます。「敵」は暴れまくり、ますます形勢不利になります。体温を一定以上あがらないように抑えることは免疫機能を十分に生かし体全体を管理する上で必要なことです。
基本的に炎症を起こしたところは本来の生体の機能が部分的に低下しているばかりでなく、それによって全身の機能も不全に陥りつつあるわけですから、いわゆる市販の総合感冒薬で炎症を起こした箇所にそれぞれ対症療法を加えるのは「風邪を身体から追い出す」最終目標に向けての身体全体の平衡を取り戻すためには地道な基本戦術だといえます。
免疫機能を活かすという意味では、ひと頃特効薬といわれたインターフェロンは免疫を高めるので、風邪のかかり始めに投与すると劇的に効くことがあります。一時安易に多用されたことがありましたが、発熱して体力が落ちてからでは逆に高熱になって熱性けいれんを起こしたりして危険です。それと高価な薬ですから、そういう使い方には「鼻風邪に使うそのインターフェロンはアジア・アフリカの子供の命を4,5人は救えるんだよ」と嫌みを言うことにしています。
薬は上手に意味のある使用をすべきです。そうしなければ、やがて薬に頼ることが普通になってしまいます。投薬の基本は「早めに少量から」。江戸時代から言われています。
ちょっと質問から脱線気味になってしまいました。あなたの自分で治そうという気持ちは大切です。薬も医者もそれを手助けするのにすぎないのです。








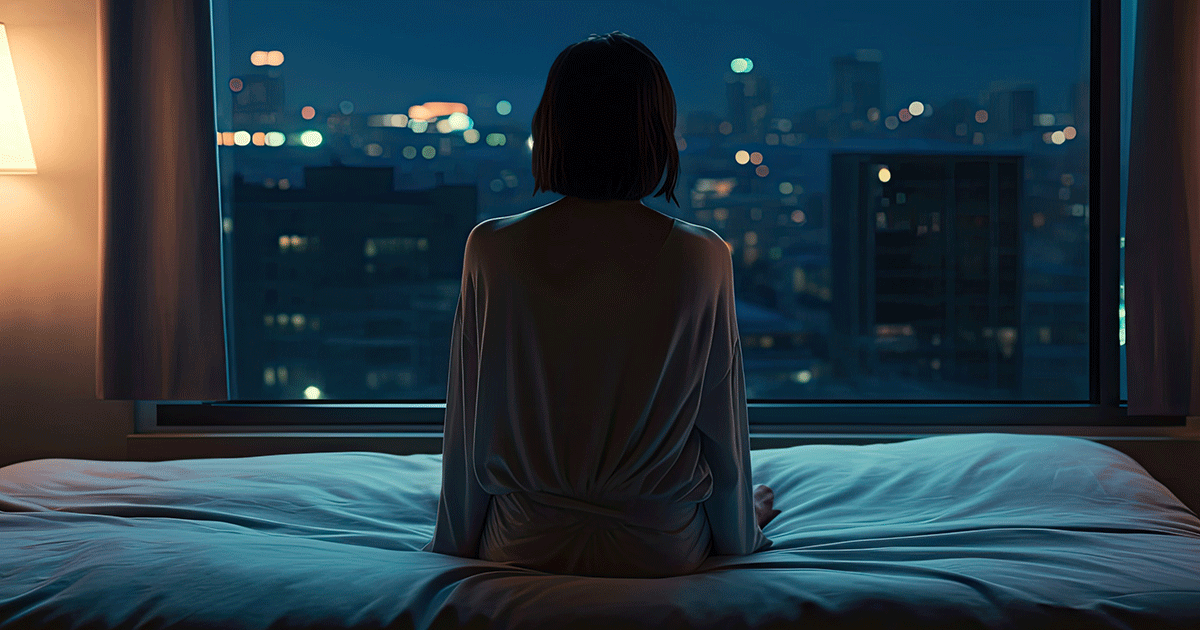





















お礼
詳しいご説明大変参考になります。