一体型PCにもいろんなものがありますが
わかりやすく説明すると
ノートPCの短所と、デスクトップPCの短所を
両方兼ね備える、地獄の底で生まれたパソコンです。
ノートPCの特徴は
専用部品が多く、メーカー保証が切れた場合
メーカー修理に出さざるを得ず、割高になること。
省電力低発熱の部品を使っているために、部品単価が高いこと
また同様の理由で、処理性能が高くないこと
デスクトップPCの特徴は、電池駆動できず
停電対策などの理由でUPSが必要な場合があること
持ち歩いて外出先で使うことが困難なことなどです。
長所を兼ね備えるという考え方はできなくはありませんが
実際には、大画面+省電力というだけのことで
電気代が安い代わりに
パソコンの購入費用は高いという傾向があります。
故障率は、数値化されて発表されたりもしますが
実際には、自分のPCが故障してしまえば
全体の故障率が低いことには、何の意味もなくなります。
ですから、故障したらどうするか?そこを考えるのが基本です。
今あずかっているCorei5機も、4年目のデスクトップ(スリムタワー)ですが
メモリースロットの四つのうち3番以外にメモリーを挿したら画面表示すら出ず
CMOSクリアもやってみてなお、3番だけなら、メーカーロゴまでは見れる
ただしBIOS設定は出ないし、エラーメッセージも出ないまま数分経つありさまで
「あ、これM/B交換するしか無いやつだ」
と思っているところです。ノートPCや一体型なら、手詰まりになっています。
それでも、一体型が盛んに売られているのは
流通コストにおいて、PCメーカーも量販店も有利だからです。
でも、それは消費者の利益ではありません。
もちろん電気代安く、PCメーカーに入る金が大きいのは
PCメーカーの利益に繋がります。
でも、それが消費者の利益になりやすいとは言えません。
パソコンの電気代は並のデスクトップPCを3年使い続けても、総計でせいぜい3万円です。
それと同等のCPU性能を求めれば
5万円のデスクトップ相当の一体型は10万円したりします。
あげく、3年保証が切れた頃に液晶が壊れたりすれば
外付けモニターなら2万円以下で新品が買えるのに
一体型なら交換修理に6,7万円かかります。
これでは、3年で買い替えを余儀なくされます。
省電力が、消費者の利益になることは、けっこう難しいものです。
どうみても、PCメーカーの利益だけが際立ちます。
ゆえに、パソコンに詳しい人ほど、セパレート構成のデスクトップPCを好みます。
反面、そういうPCは国内メーカーはほとんど作らなくなっている実状があり
そういうPCの市場が失われていくことに危機感を持っている人もいます。
そういった危機感は、ほとんどすべての分野において
「ほんとうはこういうのが良いモノなのです」
という熱狂的な支持を受けやすくなっています(笑)
自動車産業におけるマニュアルミッション車とか
携帯電話産業におけるいわゆるガラケーとか
カメラ産業における銀塩カメラとか、単焦点レンズとか
いろんな分野に、そういう古い良いものを支持する層がいます。
実際の市場は、そこを遠ざかり続けている現実があり
ですから、理路整然に説明することができるとしても
それがすべての人にとっての正しい答ではありません。
実際、パソコンを2,3年で買い替える前提でまわしている人は
故障するまで使うことは普通ありませんし
故障してもメーカー修理に待たされる程度で、大きな不満にはなりません。
ワードプロセッサーとウェブサイト利用だけのパソコンに15万円かけても
それが妥当な費用だと思っている人もいますから
割高感を感じず、正当な付加価値に見合う価格と考えているのでしょう。
ただ、私は、パソコン一台に10万円もかける余裕は無いので
(パソコン関係の出費総額が少ないとは言っていない)
一体型は選びませんし
ノートPCは、雑に扱える激安中古品しか使いません。
「壊れたら買い換えればいいじゃん」という考え方ができるのは
私にとっては、せいぜい1,2万円のものだからです。
メインマシンは、いわゆる自作PCですが
今使っているノートPCのCPU性能の4倍くらい速いCPUを昨年まで使っていて
今はそれが8倍くらいのものに入れ替わっています。
それでも、今回のアップグレードと前回のアップグレード費用を合わせても
10万円はかかりません。価格性能比的に考えると
デスクトップPC、特に自作PCのほうが大幅に有利になる傾向があります。
そういう利点を維持するためには
そういう市場を、衰退させない努力も必要だと考えられています。



















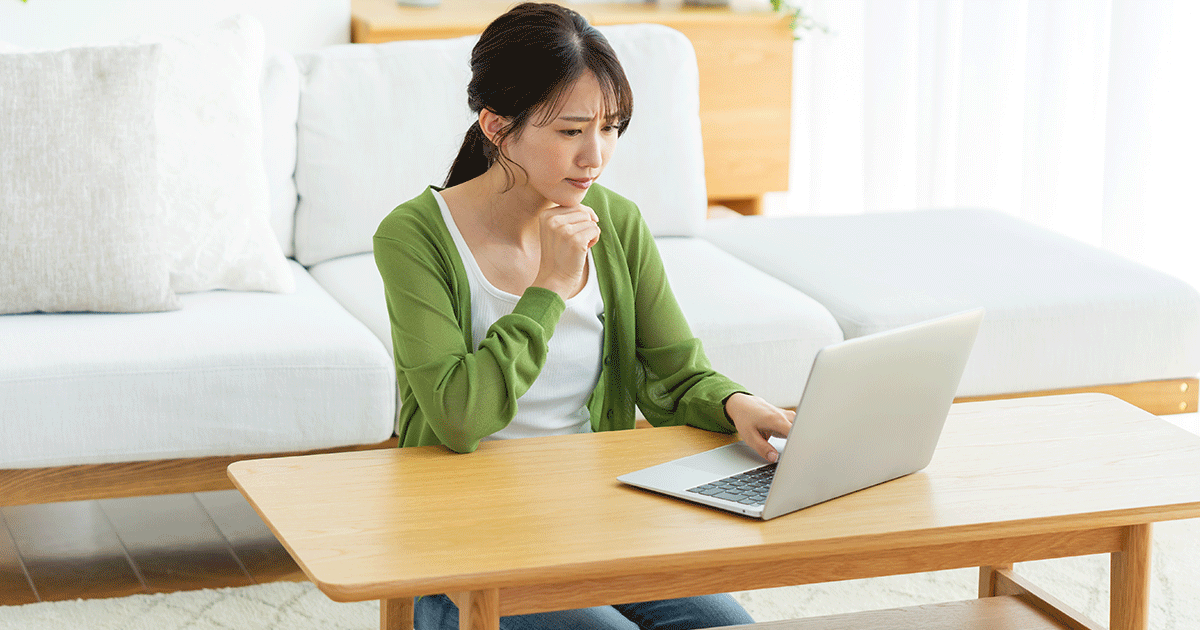















お礼
ご回答ありがとうございます。 拝見してなるほどと思いました。 周辺機器と言っても、今のところプリンターぐらいのものです。 ミドルと言うからには、その前後のタワーがあるのだとおもいますが、 なかなかのど素人であれば、見分けがつきません。 どのタイプであれ、品質と価格でお得感のあるおすすめのメーカーは、どこでしょうか? 使用範囲はオフィスとネットです。