最初、パソコンは単体でしか使えず、別のパソコンにデータや画像などを送りたいなら、フロッピーディスクなどに移して、別のパソコンに入れるしかありませんでした。USBメモリーなんて便利なものはなかったのです。
しかし、会社などでパソコンを使い出すと、やっぱり隣の人とか、課内とか社内とか、パソコンをつないで「データ共有」をしたくなります。このときにパソコン同士をつなぐために考えられたのがLAN:Local Area Network(ローカル・エリア・ネットワーク)です。
「LAN」という名前は「パソコン同士をつなぐ規格」の名称で、ローカルつまり社内などの狭い場所でつなぐだけの規格でした(もちろん、この頃はまだインターネットはありません)
会社同士を跨いで、建物の外までパソコン同士をつなげることをWAN:Wide Area Networkといいました。
今ではWANは事実上インターネットと同じ意味ですが、インターネットが普及する前は、大きな会社が自前で持っている通信線(たとえばトヨタが本社や研究所、海外拠点を結ぶ自社のネットワーク)などをさしたのです。
そのうちに、インターネットが発達して、どこのパソコンもネットにつながるようになります。そしてパソコン自体も家庭に2台3台と増えていきました。そうなると家庭の中で、電線を引いてLANをつなげるのはめんどくさいので、無線でLANを使える仕組みができたのです。
これが無線LANと呼ばれるものなのですが、今、家庭で無線LAN以外のやり方をしている人はほとんどいないと思います。
で、無線LANは電波ですから、使おうと思えば誰でも使えます。自宅の前の道路ならほかの人が無線LANに入り込むことも可能になります。通常はこれをパスワードなどで制限しているわけです。
この考え方を逆手にとって「誰でも自由に無線LANを使えるようにしよう」と考えた人たちがいました。当時の無線LANは規格や接続方法が各メーカーによってばらばらだったため、それをそろえて「その規格ならどんな無線LANでもどんなパソコン(今ならスマホ)でもつながるようにしよう」と動いた人たちがいたのです。
この「無線LANの規格をそろえて誰でもつながるようにした」のがWi-Fi(ワイファイ、Wireless Fidelity)で、Wi-Fi Alliance(米国に本拠を置く業界団体)が管理しています。
このWi-Fi Allianceが決めた規格を守っている機械にはすべてWiFiのロゴがつき、違うメーカーでも互換性が保障されているのです。
まあ、結局のところ今の無線LANの機械でWiFiの認証を受けないことなんてないので、事実上、無線LAN=WiFiになっているのです。
でも厳密にいえば、無線LANは「小さな場所(家庭とか社内とか)だけで、電波を使ってパソコンをつなげる規格」で、WiFiは「みんなが無線LANを自由に使えるようにする規格」です。
WiFiの規格ができたことで、スタバなどでインターネットに安心して接続できるようになり、インターネットの普及に一役買ったといわれています。これを「公衆無線LANサービス」とか「WiFiサービス」などといいます。
ただ日本では、公衆WiFiサービスが浸透する前に、携帯電話の通信速度がものすごく速くなったために、あまり普及していません。
外国ではほんとうにどこでもWiFiサービスが無料でありますので、日本にくるとみんな「日本は先端技術の国なのに、無料WiFiが少ない」とびっくりします。











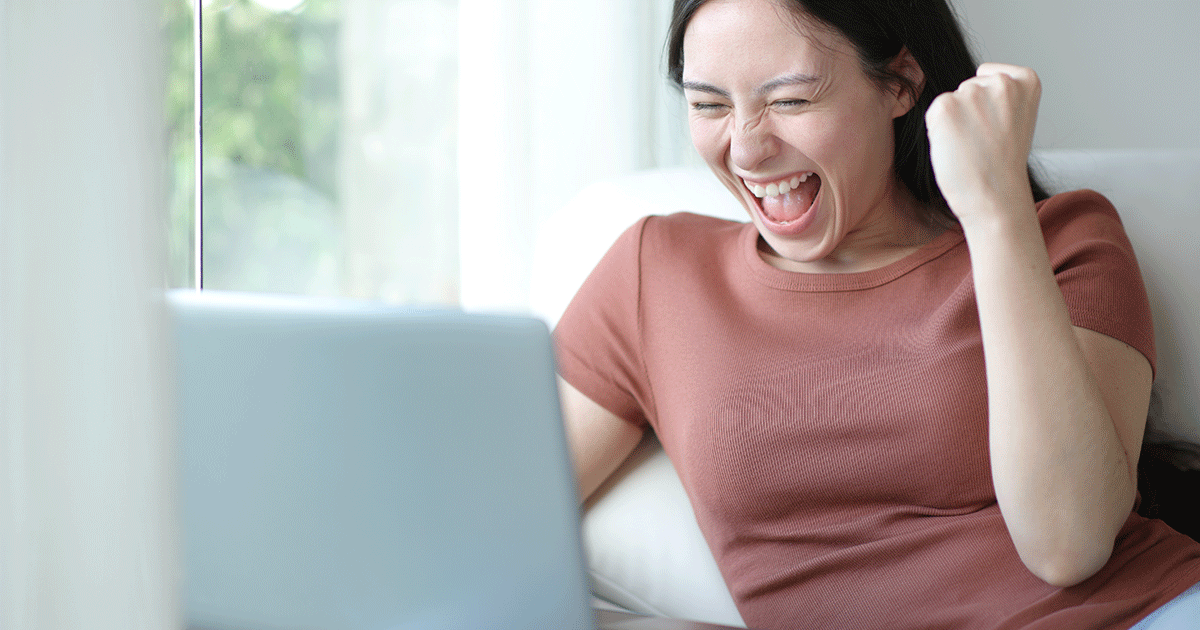
















お礼
WiFiの歴史や誕生の経緯まで説明いただき、ありがとうございました。